【2025年施行】育児・介護休業法改正対策ガイド
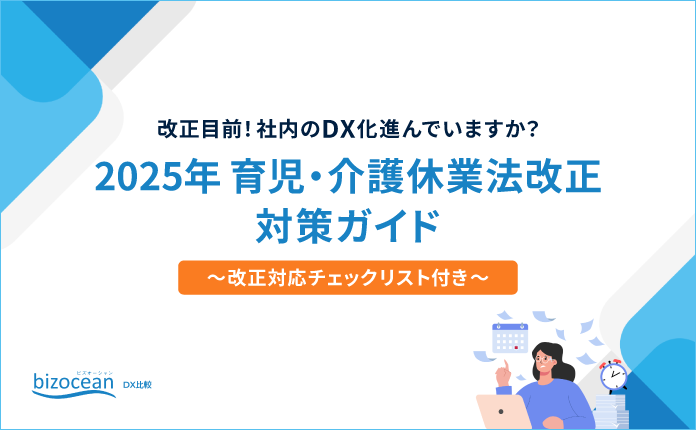
資料の概要
2025年4月と10月に改正される育児・介護休業法。
今回の改正は、育児・介護と仕事を両立できるよう、企業の対応義務を定めた重要な内容です。
本資料では人事・労務の方向けに、それぞれの改正ポイントと企業が取り組むべき対応策をわかりやすく解説します。必要な対応が分かるチェックリスト付き。
こんな方におすすめ
・育児・介護休業法改正の概要を知りたい方
・企業側の準備に必要な情報を知りたい方
・法改正対応の抜け漏れに不安がある方
・人事・労務部門のDXや効率化を検討している方
この資料で分かること
・育児・介護休業法改正の背景と概要
・育児・介護休業法改正:2025年4月1日施行のポイント
・2025年10月1日施行のポイント / 企業がとるべき対応
・改正対応チェックリスト
・担当者の負担を減らし、勤怠・労務管理を効率化するには
育児介護休業法改正の背景と目的
育児介護休業法とは、育児や介護を行う労働者が仕事と家庭を両立できるように支援する法律です。
2024年5月に改正法が成立し、2025年4月より施行が予定されています。
そもそも育児介護休業法はなぜ改正されるのでしょうか。ここでは、法改正の背景と目的について詳しく見ていきます。
少子高齢化と働き方の多様化への対応
育児介護休業法の改正は、少子高齢化に伴う労働力不足と、働き方の多様化への対応が主な目的です。
現在、労働力人口が減少する中で、育児や介護を理由に離職する人材の流出防止が課題となっています。
同時に、ライフスタイルや価値観の多様化を受け、時短勤務やテレワークなどの柔軟で多様な働き方を取り入れる必要性も高まっています。
これらに対応するために、仕事と家庭の両立を支援する法整備を行い、育児や介護をしている人も活躍できる職場環境の実現を目指しているのです。
仕事と家庭の両立支援の必要性
仕事と育児・介護の両立を支援し、離職を防ぐためには、育児介護休業法の整備と拡充が不可欠です。
特に、育児休業については、依然として男性の取得率が低く、育児負担が女性に偏っていることが就業継続の障壁となっています。
そのため、男性の育児参加を促進し、女性の就業継続を後押しする支援が求められています。
育児や介護を理由に仕事を辞めざるを得ない状況を改善し、誰もが働き続けられる環境を整えるためにも育児介護休業法改正が欠かせません。
改正法の目指すもの
育児介護休業法の改正は、男女ともに仕事と家庭を無理なく両立できる社会の実現を目指すための取り組みです。
そのため、育児や介護を行う労働者が、仕事と家庭の責任を果たせるよう、休業制度や働き方に関する制度が整備・拡充されます。
また、企業における両立支援の取り組みを促進し、労働者が安心して働き続けられる職場環境の実現も期待されています。
法改正を機に、仕事と家庭の両立に対する企業の意識改革と支援を後押ししていく方針なのです。
【育児介護休業法】2025年4月施行の主な改正ポイント
2025年4月に施行される改正育児介護休業法の主なポイントは以下のとおりです。
- 子の看護休暇の拡充
- 残業免除の対象拡大
- 育児のためのテレワーク推進
- 介護休暇の取得要件緩和
- 男性の育児休暇取得率公表の義務化範囲拡大
ここでは、各ポイントを詳しく見ていきましょう。
子の看護休暇の拡充
子の看護休暇の対象範囲が、小学校就学の始期に達するまでの期間から小学校3年生修了まで引き上げられます。
また、これまでの取得事由は子の病気・ケガや、予防接種・健康診断に限定されていました。改正後は、感染症による学級閉鎖や入園式(入学式)・卒業式も含まれるようになります。
さらに、継続雇用期間が6か月未満の場合は適用除外とされていましたが、改正後はこの基準が削除されました。
取得事項や年齢の拡充は、コロナ禍で増加した学級閉鎖への対応や、子どもの健康管理に関する親の負担軽減が狙いです。子育て中の労働者にとって、より利用しやすい制度になると期待されています。
残業免除の対象拡大
改正前は、3歳までの子を持つ労働者が残業免除の対象でしたが、改正後は小学校入学前まで対象が拡大されます。
対象範囲の拡大により、子育て期の長期にわたる時間的制約に対応し、柔軟な働き方が可能になるでしょう。
特に、保育園や幼稚園に通っている子どもがいる場合は、定時で上がりお迎えにいけるため仕事と子育ての両立が一層しやすくなるかもしれません。
育児のためのテレワーク推進
法改正により、育児のためのテレワーク導入が事業主の努力義務となります。
そのため、3歳未満の子を養育する労働者が育児休業をしていない場合、事業主はテレワークを提供できるよう努めなければなりません。
この改正は、コロナ禍をきっかけに広がったテレワークを、仕事と育児の両立に活用することを推奨する内容です。
育児期の労働者にとって、テレワークのような柔軟な働き方の選択肢が増えることは喜ばしい変化でしょう。
介護休暇の取得要件緩和
介護休暇とは、要介護の状態である家族の世話をする際に取得できる休暇です。
改正前は、勤続6ヶ月未満の労働者を介護休暇の適用対象から除外することを事業主に認めていましたが、法改正により廃止となります。
これにより、入社直後の労働者でも介護休暇の取得が可能になります。事故や急病により急に介護が必要になった際に、休暇を取りやすくすることで、介護離職の防止につなげられるでしょう。
男性の育児休業取得率公表の義務化範囲拡大
これまでは、育休取得状況の公表は従業員数が1,000人を超える企業に義務付けられていました。
しかし、法改正により、従業員数が300人を超える企業まで公表義務の対象が拡大されます。
これは、男性の育児休業取得を促進するため、企業の取り組み状況を「見える化」し、社会全体で男性が育児休業を取得しやすい雰囲気づくりをすることが目的です。
公表義務の対象拡大により、多くの企業で男性育休に対する意識改革が進むことが期待できます。
【育児介護休業法】2025年10月施行の主な改正ポイント
2025年10月からは、育児介護休業法のさらなる改正が施行されます。主な改正ポイントは以下のとおりです。
- 柔軟な働き方を実現するための措置の義務化
- 仕事と育児の両立に関する行こう聴取と配慮の義務化
ここでは、それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。
柔軟な働き方を実現するための措置の義務化
子が3歳から小学校入学前の労働者に対し、柔軟な働き方を可能にする措置の実施が事業主の義務となります。
そのため、事業主は以下のうち2つ以上の措置を講じる必要があります。
- 始業時刻変更等
- テレワーク等(10日以上/月)
- 在宅勤務等
- 短縮勤務措置
- 新たな休暇付与の措置
- 保育施設の設置運営等
子育て期の労働者が、家庭の事情に合わせて臨機応変に働けるようにすることで、仕事と育児の両立をサポートすることが狙いです。
企業には、労働者のニーズを踏まえた勤務制度の設計と適切な運用が期待されます。
仕事と育児の両立に関する意向聴取と配慮の義務化
改正法により、事業主は育児中の労働者の両立に関する意向を聴取し、配慮することが義務化されます。
従業員の妊娠・出産の申し出時があった際や、子が3歳になるまでの間に、個別に両立支援に関する意向を確認しなければなりません。
労働者の状況やニーズに応じて、勤務時間や勤務地、業務内容などを柔軟に調整することが求められます。企業は、労働者一人ひとりの事情に寄り添い、きめ細やかな支援を行いましょう。
育児介護休業法改正によって企業が対応すべきこと
2025年の育児介護休業法改正を踏まえ、企業には計画的な対応が求められます。具体的なポイントは以下のとおりです。
- 就業規則を見直す
- 労使協定を締結する
- 従業員を周知する
- 育児休暇取得状況の公表準備を始める
ここでは、各ポイントについて詳しく解説します。
就業規則を見直す
企業は、法改正の内容を反映し、育児・介護関連規定の見直しと整備を行う必要があります。
子の看護休暇や介護休暇の拡充、残業免除の対象拡大など、改正内容を踏まえて社内規定を改定しましょう。
新しい制度の導入に当たっては、適用対象者の範囲や手続き、給付内容などを明確に規定することが肝要です。
法改正の趣旨を理解し、労働者にとって利用しやすい制度設計を心がけましょう。
労使協定を締結する
育児・介護休業等の規定では、一定の事項について労使協定の締結が求められます。
法改正により、子の看護休暇や介護休暇の適用除外制度の廃止・縮小などが行われるため、協定内容の見直しが不可欠です。
法改正の内容と社内の実情を踏まえ、労働者と事業主で十分に協議した上で、適切な協定内容を定めます。
両立支援制度の円滑な運用に向け、事業主は労働者とのコミュニケーションを密に取りましょう。
従業員へ周知する
法改正の内容や社内制度の変更点について、従業員への丁寧な周知が欠かせません。
育児介護休業法の改正の目的や主なポイント、社内規定の改定内容などについて、適切なタイミングで説明しましょう。
管理職に対する研修は、部下の制度利用を支援する意識と知識の養成にも効果的です。全社的な理解浸透を図り、制度を利用しやすい職場風土づくりを目指しましょう。
育児休業取得状況の公表準備を進める
改正法により、育児休業取得状況の公表義務の対象が従業員300人超の企業に拡大されます。
そのため、今回から公表対象に当てはまる企業は、男性育休の取得状況の集計と開示に取り組まなければなりません。
自社の育児休業制度の利用実績を正確に把握し、公表に向けた準備を計画的に進めましょう。
外部への公表を見据え、両立支援の積極的な推進と取得状況の「見える化」に努めることが大切です。
育児介護休業法改正を機に職場環境を改善するメリット
育児介護休業法への対応は、企業にとって負担に感じられるかもしれません。
しかし、法改正を機に職場環境を改善することで以下のようなメリットを得られます。
- 優秀な人材の確保と定着
- 生産性の向上
- 企業イメージの向上
ここでは、各メリットについて詳しく見ていきましょう。
優秀な人材の確保と定着
育児・介護との両立支援制度の充実は、優秀な人材の確保と定着率の向上につながります。
仕事と家庭を無理なく両立できる職場環境は、労働者にとって非常に魅力的です。
自社が行っている両立支援の取り組みをアピールすることで、人材の獲得競争において優位に立てます。
また、結婚や出産などのライフイベントによる離職リスクの低減も見込めます。経験豊富な人材の長期的な定着にも寄与するでしょう。
生産性の向上
仕事と家庭の両立支援は、従業員のモチベーション向上と生産性のアップをもたらします。
柔軟で多様な働き方を推進し、従業員のワーク・ライフ・バランスを改善することで、仕事への貢献意欲の向上が期待できます。
時間に制約がある中で成果を出すことを意識した働き方は、業務の効率化やスキルアップにつながるでしょう。
従業員一人ひとりが能力を最大限に発揮できる環境を整えることが、企業の生産性向上の鍵です。
企業イメージの向上
仕事と育児・介護との両立支援に積極的に取り組む企業は、仕事と家庭のバランスを配慮してくれる企業として、ブランドイメージの向上と社会的評価の上昇が期待できます。
仕事と家庭の両立に配慮した柔軟な働き方は、企業の社会的責任(CSR)の実践としても高く評価されるでしょう。
近年、就職先や投資先の選定において、企業の両立支援の取り組みが重視される傾向が強まっています。
育児介護休業法への適切な対応は、優秀な人材や投資家の信頼獲得にもつながるため着目するべき要素です。
育児介護休業法改正に対応し働きやすい職場を作ろう
2025年4月と10月に段階的に施行される育児介護休業法の改正について、背景や目的、主な改正ポイントについて詳しく解説しました。
企業には、少子高齢化と働き方の多様化を踏まえた法改正の流れを理解し、法改正を見据えた体制整備が求められています。
就業規則の改定や労使協定の締結・見直しなど早期の取り組みと丁寧な対応を心がけましょう。
改正法を意識した働きやすい職場づくりは、優秀な人材の獲得や企業イメージの向上など、様々な面で企業にメリットをもたらします。
育児介護休業法への対応をきっかけに、多様で柔軟な働き方を実現させましょう。

