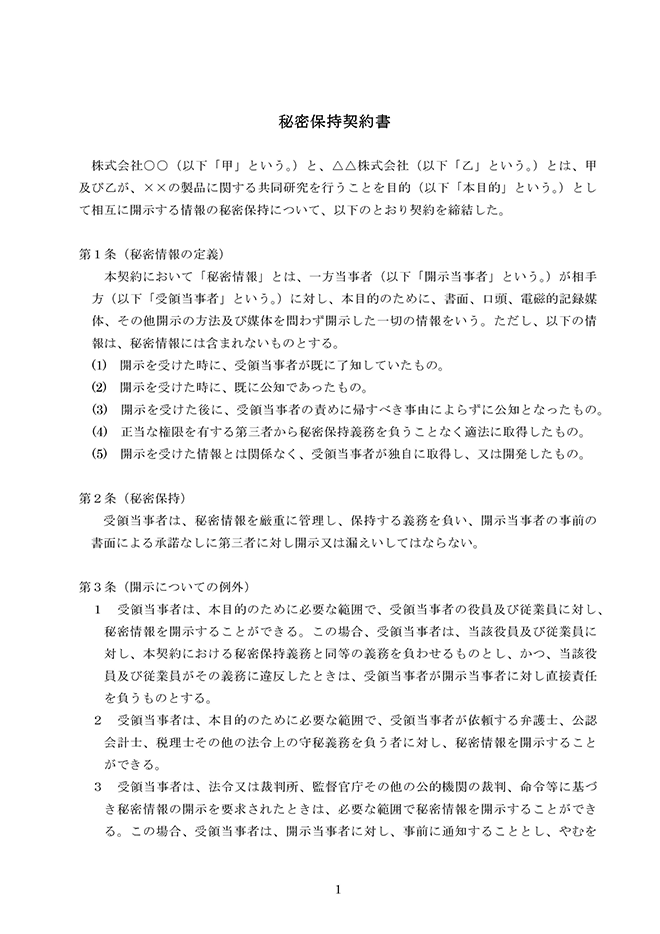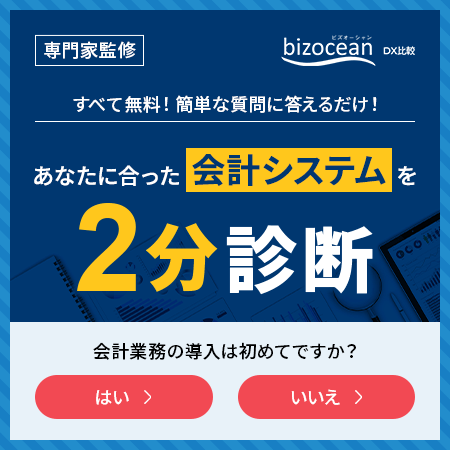[契約書の書き方] 第8回:秘密保持契約書③
![[契約書の書き方] 第8回:秘密保持契約書③](https://journal.bizocean.jp/assets_c/2021/06/kigyo-houmu-photo36-thumb-660x425-191.jpg)
今回は、秘密保持契約の解説の最終回として、損害賠償に関する規定や契約の存続期間の規定などについて解説します。

損害賠償義務
第7条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約に違反したときは、これによって相手方が被った損害を賠償しなければならない。
本条は、当事者の一方が秘密保持契約に違反した場合(秘密情報の開示・漏えい、目的外使用、返還・破棄の義務違反など)における、他方当事者に対する損害賠償義務について規定するものです。
仮にこのような規定がなくても、民法415条以下の規定により、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることは可能ですが、契約書上に損害賠償義務についての確認規定を設けておくことは、それぞれの当事者に対し、秘密保持契約に違反せずこれを守らなければならないことを自覚させる意義があり、決して無駄(過剰)な規定と考えるべきではありません。
また、上記規定例とは異なり、損害賠償額の予定(民法420条1項)を定めた場合などは、当事者間の特約としてその取り決めた内容に従って処理されることとなります。損害賠償の予定と、違約金、違約罰の各概念の違いについては、本コラムの第2回「取引基本契約書②」で解説しましたので、ご参照ください。
不正競争防止法上の「営業秘密」や「限定提供データ」に該当するものに関しては、その開示等の不正競争により営業上の利益が侵害された場合の損害額の推定規定が、同法5条に設けられています。秘密保持契約書の損害賠償に関する規定にかかわらず、上記営業秘密や限定提供データに該当するものについては不正競争防止法の規定に従うこととする場合には、紛争となった場合に混乱が生じないよう、秘密保持契約書に明記しておくべきです。
差止め
第8条(差止め)
甲及び乙は、相手方が本契約に違反し、又は違反するおそれがあるときは、その違反行為の差止めを請求することができる。
本条は、当事者の一方が秘密保持契約に違反した場合や違反するおそれがある場合における、他方当事者の差止請求権を規定したものです。
不正競争防止法上の「営業秘密」や「限定提供データ」に該当するものに関しては、同法3条に基づく差止請求権が認められます。これに対し、これらに該当しない秘密情報(本秘密保持契約第1条で定義したもの)については、差止請求権は法律上定められていません。解釈論上、民法上の債務不履行に基づく請求権として認められる余地はありますが、明確な判例理論は構築されていませんので、契約書において上記規定例のように明文規定を設けておくことが有用と考えます。
契約の存続期間
第9条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約の締結日から1年間とする。ただし、期間満了の2か月前までに、甲又は乙から解約の申し出がない限り、本契約と同一の条件でさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
本条は、秘密保持契約の存続期間について定めた規定です。
本コラムでは、前文に定めたとおり、甲社と乙社が共同して特定の製品の研究開発をする場合の秘密保持契約を想定していますので、その研究開発に要する期間と、当事者間で開示される情報を秘密として取り扱う必要のある期間を考慮して、存続期間を定めることとなります。契約締結の時点で未だ研究開発の終期等についての明確な見通しが立っていない場合などを想定しますと、上記規定例のただし書きのように、自動更新される旨の規定を設けておくことも考えられます。
契約の余後効
第10条(残存条項)
本契約の終了後においても、第6条(返還・破棄)、第7条(損害賠償)及び第8条(差止め)の各規定は、効力を有する。
本条は、秘密保持契約が終了した後も効力を持ち続ける残存条項について定めるものです。
どの条項を残存させるべきかについては、秘密保持契約の目的を考慮して決めることとなります。本コラムの規定例では、主に契約終了後の義務である秘密情報の返還・破棄や、損害賠償義務、差止請求権などの規定を対象とすることが考えられます。
協議事項
第11条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じたときは、甲及び乙が協議して解決する。
本条は、契約書に規定のない事項や契約条項の解釈をめぐって問題が生じた場合、当事者間の協議により解決することを定めたものです。
こうした協議事項に関する規定が存在することにより、仮に相手方が他方当事者と協議をすることなくいきなり法的手段に出たような場合、その他方当事者は、相手方が同規定に違反した事実を主張することができ、裁判所等において最初から法律上の任意規定の解釈・適用が問題とされることなく、紛争を解決し得る場合が出てくると考えられます(本コラム第5回の「協議事項」参照)。
紛争処理
第12条(紛争処理)
本契約に関して生じた紛争については、一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って仲裁により最終的に解決する。仲裁地は東京とする。
前条の協議によっても解決することができない問題が生じた場合、どのような紛争処理手段によって問題解決を図るかについて定めるのが、紛争処理条項です。
日本国内の当事者間での契約を想定した場合、裁判手続を選択した上で、専属的合意管轄について規定する※のが一般的と思われますが、本コラムでは敢えて、裁判手続ではなく、仲裁手続による紛争処理を定めることとした場合の規定例について解説します。
※裁判手続及び専属的合意管轄の規定例
本契約に関して生じた紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、裁判によって解決する。
仲裁合意があるにもかかわらず、当事者の一方が原告となって訴えが提起された場合、相手方である被告が仲裁合意の存在を示して申立てをすれば、訴えが却下されます。※※
※※仲裁法2条1項
この法律において「仲裁合意」とは、既に生じた民事上の紛争又は将来において生ずる一定の法律関係(契約に基づくものであるかどうかを問わない。)に関する民事上の紛争の全部又は一部の解決を一人又は二人以上の仲裁人にゆだね、かつ、その判断(以下「仲裁判断」という。)に服する旨の合意をいう。
同法14条1項
仲裁合意の対象となる民事上の紛争について訴えが提起されたときは、受訴裁判所は、被告の申立てにより、訴えを却下しなければならない。
(ただし書きは省略)
仲裁手続を選択するメリットとしては、原則として公開される裁判手続とは異なり、非公開で審理がされる点や、相手方当事者が外国企業の場合で、例えば中国のように、日本の裁判所の判決では強制執行ができないものの、いわゆるニューヨーク条約(外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約)により、仲裁判断があれば強制執行が可能というケースが考えられます。
仲裁合意条項には、仲裁機関、その仲裁機関の規則を適用して解決する旨、及び仲裁地を定めておくのが一般的です。上記規定例では、日本において最もオーソドックスな一般社団法人日本商事仲裁協会(JCAA)の商事仲裁規則に従うこと、及び、東京を仲裁地とすることを定めています。
後文
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
全ての契約条項を記載した後、最後に上記のような後文を設けるのが一般的です。
契約書末尾に設けられる当事者の表示に関しては、本コラムの第1回の「会社の誰が契約締結を行うか」において解説しましたので、そちらをご参照ください。
以上で秘密保持契約書の解説を終了します。次回からは、業務委託契約書をテーマとして解説する予定です。
(第8回・以上)