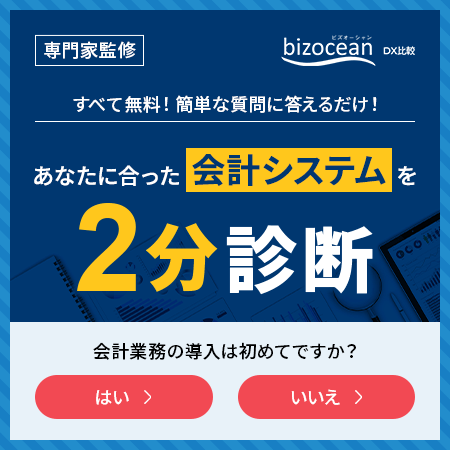法人税の中間納付とは? 義務となる企業や納付時期、金額の計算方法を解説

一部の企業には、「法人税の中間納付」が義務付けられています。企業に課される法人税のうち、一定の割合の額をその事業年度の途中で支払う制度であり、正確な計算や期限を守っての納付が求められます。
内容や納税額に誤りがあった場合、追徴課税の対象となる場合があるため、適切に処理しなくてはなりません。
本記事では、法人税の中間納付の概要から計算方法、注意点をわかりやすく解説します。

法人税の中間納付とは
企業は、一定の条件を満たした場合、法人税の一部を事業年度の中間となる時期に納める必要があります。この手続きを、「法人税の中間納付」と言います。
法人税の中間納付をする際は、その事業年度に納めるべき法人税額が確定していない状態です。
そのため、自社で納税額を算出しなければなりませんが、計算方法には「予定申告」と「仮決算」があり、いずれかを選択することが可能です。
また、納税する際は「中間申告書」という書類も提出しなくてはなりません。
制度の必要性
法人税の中間納付の制度が導入されている理由は、法人と国・自治体の両者にメリットがあり、納税の未払いを減らせるためです。
法人税の一部を早期に納めておくことで、企業側は資金繰りの負担を軽減させられます。
また、中間納付時に過剰に支払っていた分は確定申告後に還付されるため、いわゆる「払い損」にはならないのです。
国・自治体にとっては、税収入の安定や予算立案がしやすくなるというメリットがあります。企業の資金繰りの負担が減ることによって、倒産や法人税の滞納が減少するためです。
義務付けられている企業
法人税の中間納付が義務付けられているのは、以下の条件に該当する法人のみです。
- 設立2年目以降の法人
- 事業年度開始から6カ月以上経過している
- 前年度実績基準額が10万円以上
まず、法人設立1年目の企業は、前事業年度がないため対象外です。非営利型の組織である公益法人等も、対象外となります。
そのうえで、法人税の中間納付の対象となるかどうかは、「前年度実績基準額」が10万円を超えるかどうかで判定します。
前年度実績基準額とは、以下の計算式で算出される金額のことです。
前期実績基準額=前年度の法人税額×(中間期間の月数÷前年度の月数)
この金額が10万円を超えた場合、すなわち前年度の法人税額が20万円を超えた場合は対象企業となり、法人税の中間申告書と納付用紙が送付されてきます。
なお、上記の条件に該当しなくても、企業合併をした場合は中間納付が必要です。
納付時期・期限
法人税の中間納付の納付期限は、事業年度開始日から6カ月後の2カ月以内と定められています。
たとえば決算が3月末の企業の場合、中間納付の期限は11月末です。法人税の中間納付をする際、本来支払うべき法人税の額は確定していない状態です。
そのため、中間納付の納税額は、前期の法人税額の半分程度となります。
後日、詳細な法人税額が確定し、中間納付時に過払いとなっていた場合も、確定申告の後に還付されます。
法人税の中間納付の方法
法人税の中間納付の方法には、「予定申告」と「仮決算」があります。どちらを選ぶかは企業が自由に決められますが、予定申告の方がよく使われています。
それぞれの納税方法の概要を解説します。
予定申告
予定申告は、前年度の納税額の約半分を申告・納付する方法です。
予定申告の大きなメリットは、前年度の納税額が分かって入れば簡単に処理できる点です。
しかし、法人税額は所得に応じて算出されます。
そのため、もし今年度が前年度に比べて大幅に所得が下がった場合は、中間納付の金額が高額になり、大きな負担になる可能性もあるのです。
所得に大きな変動があった場合は、予定申告を採用しても問題ないかをよく確認しましょう。
仮決算
仮決算は、その事業年度の中間時点で一度決算を行い、法人税を算出する方法です。
その年の事業年度の所得に応じた納税額が算出できるため、予定申告のように納税による経営圧迫のリスクは低くなります。
しかし、年度末の決算と同様の処理をしなければならず、大きな手間と時間がかかります。
また、仮決算で算出した中間納付の金額が、予定申告で算出した金額より高い場合、仮決算での納税はできません。
【手段別】法人税の中間納付の計算方法
中間納付の方法は、それぞれ計算方法も異なります。
予定申告と仮決算のそれぞれで中間納付をする際の、税額の計算方法を解説します。
予定申告
予定申告での納税金額は、以下の計算式で算出します。
予定申告での納税金額=(前年度の法人税額÷前年度の月数)×6
※計算後に1円未満の端数と100円未満の金額が出た場合は、いずれも切り捨て
たとえば、前年度の法人税額が400万円、月数が12カ月だった企業の例を考えてみましょう。
この場合、予定申告での納税金額は、(4000000÷12)×6=1999999.9…です。1円以下の部分と、100円以下の部分は切り捨てるため、この企業における今年度の予定申告での納税金額は、199万9,900円となります。
仮決算
仮決算での中間納付金額は、年度開始日以後6カ月を1つの年度とし、上半期の実績から計算します。
例えば3月決算の企業の場合、4月~9月の実績に税率を掛けて、納付額を割り出します。同様に12月決算の企業の場合は、1月~6月の実績に税率を掛けて計算します。
なお、仮決算を行う際は、通常の決算と同じく以下の書類の提出が必要になります。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 勘定科目内訳明細書等
このほか、中間申告書も用意しなくてはなりません。時間がかかることが想定されるため、余裕を持って取り組み、準備不足のないようにしましょう。
法人税の中間納付に関する仕訳
では、実際に法人税の中間納付をした場合の仕訳方法を解説します。
中間納付時
まず、中間納付をした際の仕訳方法は以下のとおりです。
(例)予定申告方式により、1,000,000円分の法人税等を中間納付した。
|
借方 |
貸方 |
||
|
仮払法人税等 |
1,000,000 |
現金預金 |
1,000,000 |
期末決算時
続いて、期末決算時の仕訳方法です。中間納付時に納付した税額が本来の税額より少なく、追加で納付する必要があった場合は、以下のように仕訳をします。
(例)中間納付で1,000,000円を納付していたが、確定申告の結果、納付すべき法人税額が3,000,000円だと判明し、追加で2,000,000円の納付が必要と計算された。
|
借方 |
貸方 |
||
|
法人税、住民税及び事業税 |
3,000,000 |
仮払法人税等 |
1,000,000 |
|
未払法人税等 |
2,000,000 |
||
期末決算時(還付のケース)
中間納付時に納付した税額が本来の税額より多く、還付を受ける場合も仕訳が必要です。この場合、仕訳方法は以下のとおりとなります。
(例)中間納付で1,000,000円を納付していたが、確定申告の結果、納付すべき法人税額が600,000円だと判明し、過剰に支払った分が還付された。
|
借方 |
貸方 |
||
|
法人税、住民税及び事業税 |
600,000 |
仮払法人税等 |
1,000,000 |
|
未収法人税等 |
400,000 |
||
法人税の中間納付で注意すべきポイント
最後に、法人税の中間納付をする際の注意点を解説します。
納付期限に遅れるとペナルティが発生する
中間納付は正しい内容を申告し、納税期限は厳守しましょう。もし内容を偽ったり、少しでも納付期限に遅れたりすると、追徴課税として本来の納付金額に以下の税金が上乗せされます。
|
追徴課税の種類 |
概要 |
税率の目安 |
|
延滞税 |
|
年7.3%~ (場合により年1%) |
|
過少申告加算税 |
|
年10%~ (場合により課税なし) |
余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期日に遅れることのなく申告・納付することが重要です。また、内容が正しいか、丁寧なチェックも忘れずに行いましょう。
納税額0円でも申告はしなくてはならない
仮決算を行って中間納付をする場合、納税額が0円と算出されるケースがあります。
しかし、この場合も、中間申告書や貸借対照表といった必要書類は必ず提出してください。
中間申告書を始めとした必要書類を提出しなかった場合は、「予定申告での中間納付を選択した」と見なされ、前年度の法人税額の半分を納税する必要があります。
期日までに支払わなければ前述の追徴課税の対象にもなります。納税額0円の場合であっても、対応を怠らないようにしましょう。
合併をした場合は中間納付が必須
自社が吸収合併をし、かつその企業の事業年度が6カ月を超える場合は、中間納付の対象となります。
本来、法人設立2年未満の企業は、中間納付の対象外です。しかし、事業年度内に吸収合併を経て新たな企業が立ち上がっており、その企業の事業年度が6カ月以上になった場合は、合併前の企業(被合併法人)の前事業年度における法人税額を基準として中間納付をしなければなりません。
ただし、合併時の中間納付における納税額の算出はとても複雑です。自社で対応するよりは、専門家に依頼した方が良いでしょう。
法人税の中間納付についてのまとめ
法人税の中間納付は、前年度の法人税額が20万円を超える企業が対象です。
税額の計算には予定申告と仮決算の2つの方法があり、自由に選択できます。
納めるべき税額を誤っていたり、納付期限に遅れたりすると追徴課税の対象となる可能性もあるため、ミスなく処理しましょう。
まずは、自社が法人税の中間納付の対象企業であるか、前年度の納付額や納付のタイミングはどうなっているかを確認するところから始めると良いでしょう。
ただし、合併が絡むケースでは計算が複雑になる場合もあるため、必要に応じて専門家に相談することも検討しましょう。