タイムカードの保管期間は? 起算日や保管の注意点を解説
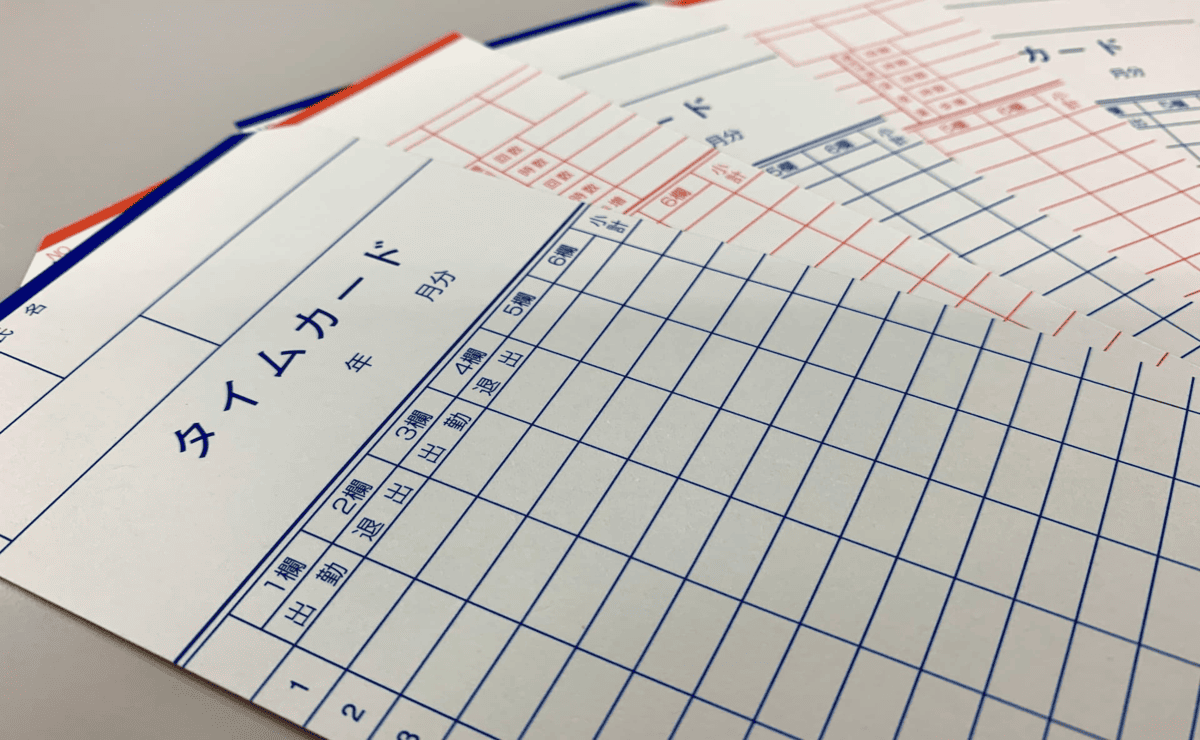
タイムカードの保管期間は現在は3年間で容認されていますが、労働基準法の改正で5年間に延長される可能性があります。曖昧なので、どのように法改正されているか明らかではない人も多いはずです。
今回は労働基準法に基づくタイムカードの保管期間、目的、対象等を解説します。保管には特殊なケースもあるので、注意点と一緒にしっかりと確認してトラブル防止に努めましょう。

【関連記事はこちら】
タイムカードとは? メリット・デメリットや勤怠管理システムとの違いを解説タイムカードの保管期間は?
労働基準法により、企業にはタイムカードの保管が義務付けられています。適切な管理を行わなければ、法令違反となるだけでなく、従業員とのトラブルにも発展しかねません。
ここからは、改正後のタイムカードの保存期間について具体的に解説します。
保管期間は5年に改正された
労働基準法によって定められているタイムカードの法定保管期間は、5年間です。2020年4月の法改正以前は3年間でしたが、賃金請求権の消滅時効に合わせて延長されています。
現在は経過措置期間中のため、当面の間は3年間の保管でも問題ありません。
経過措置終了後は5年の保管が必須
経過措置は近いうちに終了する可能性が高いです。その後は5年間の保管が必須となります。
企業は長期的な視点で、5年間の保管に対応できる体制を整えることが重要です。法改正の動向に注意を払い、適宜対応を見直しましょう。
タイムカード保管の目的
そもそも企業はなぜ、タイムカードを保管する必要があるのか疑問の方も多いはずです。
ここでは以下のように大きく二つに分けてタイムカード保管の主な目的を説明します。
- 法律を守るため
- 従業員との信頼関係構築のため
法律を守るため
タイムカードを適切に保管しておくと、従業員とのトラブルが発生した際に労働基準法遵守の証明として利用できます。これにより企業の法的リスクを抑えることが可能です。
労働時間管理の適正さを示す重要な証拠になるので、賃金や残業代未払いのような労働争議の際に企業を守る役割を果たします。労働基準監督署の立ち入り調査の際にも、適正な労務管理の証明として活用できるのです。
従業員との信頼関係構築のため
タイムカードの適切な管理は、公平で透明性の高い労務管理の基盤となります。
従業員の労働時間を正確に記録・保管しておくことで、不当な扱いへの懸念を払拭することが可能です。これらによって、労使間の紛争を未然に防ぎ、健全な職場環境の維持につなげられます。
タイムカード保管の対象と範囲
上記ではタイムカードの保管目的について説明しましたが、タイムカードの保管は誰にでも求められるのでしょうか。それとも、対象者や対象範囲が存在するのでしょうか。
ここでは、その対象者とタイムカード以外に保管が必要な関連書類について解説します。
雇用形態に関わらず全従業員が対象
企業は雇用形態に関わらず、全従業員のタイムカードを保管することが義務です。
保管期間内においては正社員だけでなく、アルバイトや派遣社員、さらには退職した従業員のタイムカードについても保管しておく必要があります。
管理監督者や裁量労働制適用者などの一部例外はありますが、彼らに対しても労働安全衛生法に規定されている「面接指導等の規定」の観点から保管が推奨されています。
保管が必要な関連書類
タイムカード以外にも、以下のような労働時間に関連する書類を保管する必要があります。
- 出勤簿
- 賃金台帳
- 残業申請書
- 休暇届
上記のように、労働時間に関連する書類や労働時間の実態を示す書類は保管しておくことで後のリスク防止につながります。
これらの書類は、タイムカードと整合性を取りながら管理することが重要です。
タイムカードの保管期間の起算日
タイムカード保管期間の起算日の取り扱いには注意が必要です。
ここでは、一般的な数え方と特殊なケースのそれぞれの数え方について確認していきましょう。
一般的な数え方
タイムカード保管期間の起算日は、対象期間の賃金支払日から始まります。例えば、4月分の勤怠記録に対する給与が5月25日に支払われる場合、起算日は5月25日です。
また月をまたぐ勤務の場合は、最後の賃金支払日を起算日とするのが一般的になっています。
特殊なケースの起算日
派遣社員の場合、例外として、起算日は派遣契約終了日になるため注意しましょう。また、長期休暇や休職期間中のタイムカードについても、通常の勤務と同様に扱うことが求められています。
さらに賞与や退職金の支払いが関係する場合は、最終的な精算日が起算日となることがあります。
タイムカードの保管方法
タイムカードの保管方法は、紙と電子化された方法の2つあります。
それぞれの特徴や注意点は異なるので、自社の規模や特性に合わせた選択をするための参考にしてください。
紙で保管する場合
紙のタイムカードを保管する場合は、紙の劣化を招く湿気や直射日光を避けて整理された状態にしておく必要があります。
年月ごとに専用のファイルやボックスを用意してファイリングし、必要な時にすぐに取り出せるようにしておくことが大切です。
また紙の紛失や盗難のリスクを考慮し、施錠できる場所での保管を推奨します。
電子化されたタイムカードの場合
タイムカードを電子化することで、紙保管で必要になるスペースの大幅な削減や検索の効率化が図れます。
またクラウドサービスで保存することで、万が一のデータ損失リスクも軽減されるはずです。
ただし電子化されたタイムカード保管を行う場合は、改ざん防止措置や適切なアクセス管理が必須となります。
タイムカード保管の特殊なケース
企業の状況によっては、タイムカードの保管に特殊な対応が求められるケースがあります。ここからは代表的な「企業が合併する場合」と「災害時の場合」の2つのケースについて解説します。
企業が合併する場合
企業が合併する際は、旧会社のタイムカードを引き継いで保管する必要があります。そのため、法定期間内は合併前の従業員の労働時間記録を適切に保管しなければなりません。
また合併に伴う人事システムの統合時には、過去のタイムカードのデータ移行を忘れずに行いましょう。
災害時の場合
被災後は可能な限り労働時間の記録を再現し、復元する努力が求められます。
自然災害によりタイムカードが損傷や紛失した場合は、速やかに労働基準監督署に相談することが重要です。バックアップデータの保管やクラウドサービスの利用などの対策を事前に決めておきましょう。
タイムカードの保管期間に関するQ&A
ここまでは、タイムカードの保管についての理解を深めてきましたが、最後にタイムカードの保管期間に関する代表的な質問と回答を紹介します。実務の際の参考にしてください。
タイムカードを誤って破棄してしまったら?
タイムカードを誤って廃棄した場合は、速やかに労働基準監督署に相談して適切な対応策を講じる必要があります。企業側はできる限り出勤簿、給与明細など他の記録から労働時間を再現し、復元に近づけましょう。
また再発防止のため、タイムカード管理のルールを見直し、従業員教育を徹底することが重要です。
保管期間が過ぎたタイムカードの処分方法は?
保管期間を過ぎたタイムカードは、個人情報保護の観点から適切に廃棄しなければなりません。シュレッダーでの裁断や、専門業者への委託など、確実な方法で処分することが望ましいでしょう。
廃棄の際は廃棄日や対象期間を記録し、適切に処分したことの証拠を残しておくことも大切です。
タイムカードの適切な保管で会社を守ろう
タイムカードの適切な保管は、法令遵守と企業の信頼性の確保につながるため、非常に重要です。保管期間、保管方法、対象範囲を正しく理解し、組織全体で適切な管理を徹底することが求められます。
安全で正確な労務管理は、企業の健全な発展と従業員の信頼獲得につながり、働きやすい職場環境の実現に期待できます。
そのためには、必要に応じて電子化やクラウド管理の導入も検討し、より効率的で確実なタイムカード管理を目指しましょう。


