契約書管理とは? 重要性から具体的な方法、システムの選び方まで徹底解説
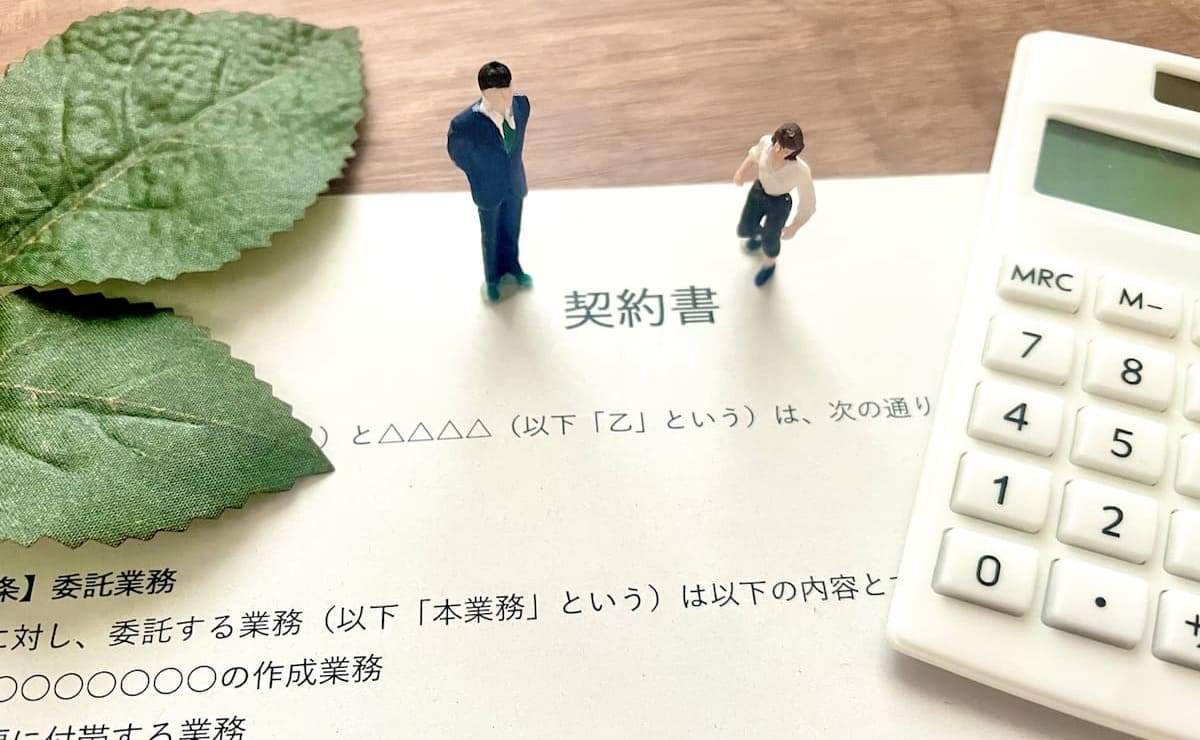
企業における契約書管理は、法令遵守と事業継続にかかわる業務です。
電子帳簿保存法の改正により、2024年1月から電子データで授受した契約書の保存要件が厳格化され、適切な管理体制の構築が急務となりました。
さらに、DX推進による紙と電子の契約書の混在やテレワークの普及による契約情報へのアクセス需要の高まりも、従来の管理方法を見直す大きな要因となっています。
本記事では、契約書管理の基本から具体的な管理方法、システム導入のメリットまでを詳しく解説します。これから契約書管理を本格的に始めたい方はもちろん、契約書の扱いに課題を感じている方はぜひ最後までご覧ください。

【この記事のポイント】
- 契約書管理は法令遵守や事業継続に直結し、不備があると情報漏洩や契約更新漏れなどの重大なリスクを招くため、適切な管理体制の構築が不可欠である。
- 管理方法には紙・Excel・専用システムがあり、専用システムは検索性向上や更新期限の自動通知による契約漏れ防止、セキュリティ強化、テレワーク対応などの多くの利点を持つ。
- システム選定では解決したい課題の明確化、必要機能の確認、誰もが使いやすい操作性、費用対効果とサポート体制の比較が重要であり、無料トライアルの活用が有効である。
契約書管理とは?
契約書管理とは、企業が締結した契約書を組織の資産として保管し、必要なときにすぐに活用できるように維持することです。
単に契約書を保管するだけでなく、契約内容、契約期間、更新条件、取引先情報などを正確に把握し、台帳などで一元的に管理することが求められます。これにより、「どの契約がいつまで有効か」「次の更新はいつか」などの情報をすぐに確認し、活用することが可能です。
理想的な契約書管理では、契約書の作成から締結、保管、更新、最終的な廃棄まで、契約のライフサイクル全体を体系的に管理します。
契約書管理を怠るデメリットとリスク
契約書管理が適切に行われていない場合、企業経営の根幹にかかわる問題を引き起こす可能性があります。
特に、情報管理の重要性が高まっている現代において、契約書管理の不備は企業の信頼性を大きく損なう要因です。
以下では、契約書管理を怠った場合に発生する主要なデメリットとリスクについて詳しく見ていきましょう。
事業機会の損失につながる
契約書管理が不適切な場合、過去の有利な契約条件を参照できず、新規契約の交渉において競争優位性を失う可能性があります。
例えば、過去に獲得した特別価格や独占的な取引条件を把握していなければ、それらを活かした戦略的な交渉ができません。また、契約内容について特定の担当者しか把握していない状況では、経営判断に必要な情報を迅速に入手できず、ビジネスチャンスを逃してしまうリスクが高まります。
取引先からの問い合わせに対しても、契約内容の確認に時間がかかることで対応が遅れ、企業としての信頼性を損なう恐れがあるでしょう。
不利益な契約更新や期限切れを招く
契約期限の管理が徹底されていない場合、不要な契約の自動更新により、本来支払う必要のないコストが発生し続けるリスクがあります。特に、複数のサービスやライセンスを利用している企業では、これらの無駄なコストが積み重なり、経営を圧迫する要因となりかねません。
逆に、事業継続に不可欠なライセンスやサービスの更新を忘れてしまうと、業務が停止し、取引先への納期遅延など重大な問題を引き起こす可能性もあります。
また、解約の申し入れ期間を過ぎてしまうと、意図に反して契約が継続され、解約したくてもできない状況に陥ることもあるでしょう。
情報漏洩やコンプライアンス違反を引き起こす
契約書の管理体制がずさんな場合、権限のない従業員による不正な閲覧や持ち出しなど、情報漏洩のリスクが著しく高まることがありえます。
契約書には自社の機密情報だけでなく、取引先の重要な情報も含まれていることがあるため、万が一の漏洩は両社の信用問題に発展する恐れがあります。
特に、個人情報や技術情報を含む契約書の漏洩は、法的責任を問われるおそれがあるだけでなく、企業の社会的信用を失墜させる結果となりうるため、注意が必要です。
また、外部からの監査や訴訟の際に必要な契約書を迅速に提出できない場合、法的に不利な立場に立たされるリスクも存在します。
契約書管理の具体的な方法
契約書管理の方法は、企業の規模や業種、管理すべき契約書の数によって最適な選択肢が異なります。
以下では、代表的な3つの契約書管理方法について、その特徴と適用場面を詳しく解説します。
- 紙とファイルでアナログ管理する
- Excelで管理台帳を作成する
- 契約書管理システムで一元管理する
紙とファイルでアナログ管理する
締結した紙の契約書をバインダーに綴じ、施錠できるキャビネットで保管する方法は、最も基本的な管理手法です。この方法の最大のメリットは、導入コストが低く、特別なIT知識が不要で、誰でもすぐに始められる点にあります。
しかし、契約書の数が増えるにつれて、必要な書類を探し出すのに膨大な時間がかかり、業務効率が著しく低下してしまいます。
また、保管スペースの確保が必要なうえ、火災や水害、盗難などによる物理的な紛失・劣化のリスクを常に抱えることになるでしょう。
Excelで管理台帳を作成する
Excelで契約管理台帳を作成し、契約書名、取引先、契約期間、更新日などの情報を一覧で管理する方法は、多くの企業で採用されています。紙媒体での管理に比べて検索性が向上し、契約期限の把握も容易なため、中小企業では一般的な管理手法となっています。
しかし、データの手入力によるミスや更新漏れが発生しやすく、人的エラーを完全に防ぐことは困難です。また、ファイルの同時編集ができないため、複数人での共同作業には限界があり、最新版の管理も煩雑になります。
契約書管理システムで一元管理する
現在最も効率的とされているのが、契約書管理に特化した専用システムを導入し、契約情報や電子化した契約書データを一元的に管理する方法です。高度な検索機能により、必要な契約書を瞬時に見つけ出すことができ、更新期限の自動アラートで契約漏れも防げます。
さらに、柔軟なアクセス権限設定により、情報セキュリティを確保しながら、必要な人が必要な情報にアクセスできる環境を構築することも可能です。
導入や運用にはコストがかかりますが、業務効率化やリスク低減効果を考慮すると、長期的には高い費用対効果が期待できるでしょう。
契約書管理システムを導入するメリット
契約書管理システムの導入は、単なる業務のデジタル化を超えて、企業の競争力強化に直結する戦略的な投資となります。
契約書管理システムを導入するメリットは、以下のとおりです。
- 契約書の検索にかかる時間を短縮できる
- 更新期限の通知で契約失効漏れ、無駄な更新を防止できる
- セキュリティを強化し、内部統制を図れる
- 場所を問わずに契約業務を進められる
それぞれのメリットを、詳しく解説します。
契約書の検索にかかる時間を短縮できる
従来の紙やExcelによる管理では、契約書を探し出すのに多くの時間と手間がかかっていましたが、システムを使えば、この負担を大幅に軽減できます。
取引先名、契約期間、契約金額などの条件で検索すれば、膨大な契約書のなかから必要な情報を瞬時に探し出すことが可能です。さらに、OCR機能により契約書本文をテキストデータ化することで、特定のキーワードや条文を含む契約書も簡単に見つけられるようになります。
これにより、従来は数時間かかっていた調査作業が数分で完了し、業務効率が飛躍的に向上します。
更新期限の通知で契約失効漏れ、無駄な更新を防止できる
契約書管理システムに搭載されたアラート機能は、一般に、契約の更新期限が近づくと自動で担当者に通知を送る仕組みになっています。
この機能により、手作業でのスケジュール管理では避けられない人的な確認ミスが根本的になくなり、契約管理の正確性が大幅に向上します。例えば、更新や解約の対応をうっかり忘れてしまうといった事態を未然に防ぐことが可能です。
また、事前に通知が来ることで、契約内容の見直しや取引先との再交渉といった準備を余裕を持って計画的に進められるようになります。その結果、不利な条件での自動更新を防ぎ、より有利な条件で契約を更新できるようになるでしょう。
セキュリティを強化し、内部統制を図れる
契約書管理システムでは、従業員ごとに閲覧・編集・ダウンロードといった操作権限を細かく設定できるものが多く、内部不正や誤操作による情報漏洩を防止できます。部署や役職に応じた適切なアクセス制限もでき、機密性の高い契約情報を確実に保護することが可能です。
また、いつ誰がどの契約書にアクセスしたかの操作ログが自動で記録されるため、不正利用の牽制効果があり、有事の際の追跡調査にも役立ちます。
加えて、多くのシステムではデータが暗号化されたうえで、セキュリティが確保されたデータセンターに保管されます。物理的な盗難や災害といった事態からも重要な契約情報を守ることができるでしょう。
場所を問わずに契約業務を進められる
クラウド型の契約書管理システムを導入すれば、インターネット環境さえあれば、自宅や出張先からでも契約書に安全にアクセスできます。
テレワーク中でも契約内容の確認や申請・承認といったワークフローを滞りなく進められるため、業務の停滞を未然に防ぐうえで有効です。
このような柔軟な働き方を支える仕組みは、働き方改革の推進だけでなく、災害時の事業継続計画(BCP)の観点からも重要な役割を果たします。
また、複数の拠点で常に最新の契約情報をリアルタイムに共有できるため、支社やグループ会社間での連携もスムーズになるでしょう。
自社に合った契約書管理システムの選び方
契約書管理システムの導入を成功させるためには、自社の状況に最適なシステムを選定することが重要です。
以下では、システム選定で失敗しないための重要なポイントを4つの観点から詳しく解説します。
- 解決したい課題や目的から選ぶ
- 必要な機能が搭載されているかを確認する
- 誰もが使いやすい操作性かを確かめる
- 費用対効果とサポート体制を比較する
それぞれのポイントを見ていきましょう。
解決したい課題や目的から選ぶ
システム選定の第一歩は、「検索業務を効率化したい」「更新漏れをなくしたい」「セキュリティを強化したい」など、自社が解決したい課題や導入目的を明確にすることです。
課題を具体的に整理することで、システムに求める機能の優先順位が明確になり、数ある製品のなかから自社に最適なものを選びやすくなります。例えば、契約書の検索に多くの時間を費やしている場合は、高度な検索機能を持つシステムを優先的に検討すべきでしょう。
一方で、多機能で高価なシステムを導入しても、使わない機能のために無駄なコストを支払うことになりかねません。導入前に「自社にとって本当に必要な機能は何か」を見極め、現場の業務フローや利用者の声を踏まえて選定することが大切です。
必要な機能が搭載されているかを確認する
自社の業務フローに必要な機能が搭載されているかを詳細に確認することで、導入後の運用効率の低下や追加コスト発生のリスクを最小限に抑えられます。
全文検索機能、柔軟なアラート設定、電子契約サービスとの連携機能など、基本的な機能の有無はもちろん、自社特有の要件に対応できるかチェックしましょう。
例えば、紙の契約書を大量に電子化する必要がある場合はOCR機能が重要になり、複雑な承認プロセスがある場合はワークフロー機能の柔軟性が求められます。
また、将来的な業務拡大を見据え、ユーザー数やデータ容量の拡張性があるものを選ぶと、増加する利用者やデータ量に対応できます。
誰もが使いやすい操作性かを確かめる
どんなに高機能なシステムでも、現場の従業員が使いこなせなければ、導入効果は十分に発揮されません。法務担当者などの専門職だけでなく、一般の従業員も直感的に操作できる、シンプルで分かりやすい画面デザインであることが求められます。
導入前には必ず無料トライアルを活用し、実際の業務を想定して検索のしやすさ、契約書の登録方法、承認フローの設定など、さまざまな機能を複数の部門で試しましょう。このとき、異なる職種やITスキルのレベルが異なるユーザーに操作してもらうことで、幅広い視点から操作性の評価が可能です。
操作が複雑なシステムは社内に定着せず、結局一部の従業員しか使わない状態に陥り、投資が無駄になるリスクがあります。
費用対効果とサポート体制を比較する
システム導入を検討する際は、初期費用や月額料金の安さだけでなく、導入によって得られる効果を総合的に評価する必要があります。契約書の検索時間短縮による人件費削減、契約漏れ防止によるリスク回避効果、セキュリティ強化による信頼性向上など、定量的・定性的な効果を考慮しましょう。
また、導入時のデータ移行支援、運用開始後の操作説明、トラブル時の迅速な対応など、ベンダーのサポート体制の充実度も重要な判断材料です。サポートが不十分な場合、想定外のトラブルが業務に大きな影響を与える可能性があります。
料金体系についても、ユーザー数課金、データ容量課金、機能別課金などさまざまな形態があるため、自社の利用規模や将来の成長を見据えて、最適なプランを選択することが求められます。
最適な契約書管理で、業務効率化とリスク対策を実現しよう
契約書管理は、企業のガバナンス強化や業務効率の向上、法的リスクの回避に直結する業務です。
近年では、電子帳簿保存法の改正やDXの推進により、従来のアナログな管理方法では対応が困難になってきており、デジタル化への移行が急務となっています。
契約書管理システムを導入することで、検索時間の大幅短縮、契約漏れの防止、セキュリティの強化、テレワークへの対応など、多くのメリットを享受できます。
導入を検討する際には、自社の課題を明確にし、必要な機能、操作性、費用対効果を総合的に検討することが成功の鍵です。無料トライアルを活用し、現場での運用イメージを持ったうえで、導入を進めていきましょう。

