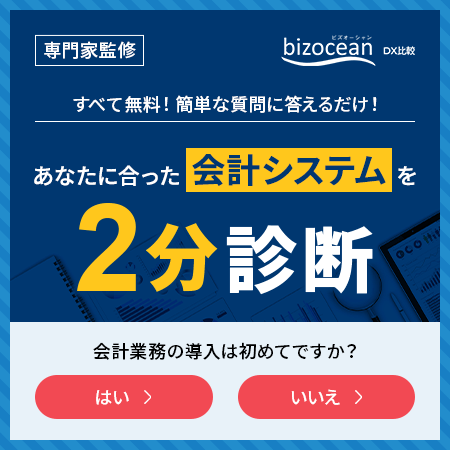パワハラ防止法で中小企業の対策が義務化!求められる取り組みと裁判の事例
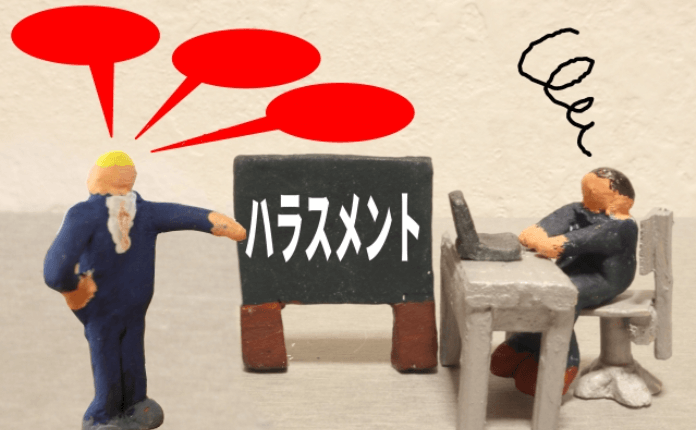
2020年6月1日に大企業、2022年4月1日には中小企業を対象に「パワハラ防止法」が施行されました。これにより、規模を問わずすべての企業にパワーハラスメントの対策が求められています。
今回は、この法律の具体的な内容と、企業が取るべき対策、そしてパワハラ裁判の事例についてご紹介します。
パワハラ防止法により、中小企業におけるパワーハラスメント対策が義務化
パワハラ防止法は、正式には「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(略称:労働施策総合推進法)という名称です。
2019年5月に労働施策総合推進法の改正が成立し、パワーハラスメントの防止についての項目が設けられました。2020年6月に大企業、2022年4月には中小企業を対象に施行されています。
中小企業については2022年3月末までを「努力義務期間」とし、この期間に法対応を進める企業が多く見られました。
パワハラ防止法は企業に対して、パワハラを防ぐための対策や生じた際の適切な対応を義務付けるものです。所属する従業員を対象としており、正社員、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトなどが当てはまります。
業務委託契約を結ぶフリーランスや、就職・転職活動中の求職者などは適用の範囲外です。
ただし、雇用を受けている対象者以外にも配慮をするべきであると示されています。
ここで、2022年4月から新たに施行の対象となった中小企業の定義について触れておきましょう。中小企業基本法第2条に中小企業者として定められているのは、下記の通りです。
〈製造業、建設業、運輸業その他〉
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
〈卸売業〉
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
〈サービス業〉
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
〈小売業〉
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
たとえ規模が小さな企業であっても、パワハラ防止にあたっての対策は必須となります。
パワハラ防止法の罰則規定と未対応のリスク
現時点では、パワハラ防止法には罰則が規定されていません。
しかし、必要に応じて厚生労働大臣より助言、指導また勧告が行われ、勧告に応じない場合は企業名が公表される可能性があります。
そうなると、世間からの「パワハラを放置する企業」という目線にさらされてしまい、従業員の士気の低下や取引先との関係性の悪化、求職者の減少などの恐れが生じます。ニュースやSNSで拡散されることにより、「ブラック企業」の烙印が押されてしまう事態も考えられるでしょう。
また、万が一パワハラの被害者が企業に対して訴訟を起こした際、行政からの指導に応じなかったという履歴があれば、企業にとって不利な判決が下される可能性が高まります。
パワハラを放置するリスクをしっかりと認識したうえで、対策を講じる必要があるでしょう
法律上の「パワーハラスメント」の定義と代表的な言動の類型
労働施策総合推進法第30条の2第1項および厚生労働省の「職場におけるハラスメント関係指針」によると、パワハラは下記のように定義付けられています
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害されるもの
(参照元:厚生労働省「職場におけるハラスメント関係指針 」)
この1〜3をすべて満たす言動が、パワーハラスメントとして認定されます。
一般的に「優越的な関係」といえば上司と部下、先輩と後輩のような上下関係をイメージする方が多いでしょう。
しかし、同僚や部下であっても、業務知識に差がある場合の言動や、集団による行為であれば優越的な関係に該当します。
たとえば、これまである業務を担当していた後輩が、新しく業務を引き継ぐ先輩に意図的に引き継ぎを行わないなどの言動は、パワハラと認定される可能性があります。
また、ここでいう「就業環境が害される」とは、精神的あるいは身体的な苦痛・不快感により、労働者が適切に業務を行えない状態を指します。
ただし、これについては一般的な労働者の感覚が基準とされます。上司からの叱責一つとっても、状況によって「指導」とみなされるケースもあれば「罵倒」とみなされるケースもあります。
つまり、労働者が「パワハラである」と訴えても、社会一般の労働者の感覚とすり合わせたうえで判断をすることが必要なのです。
パワハラには、代表的な6つの類型があります。
- 身体的な攻撃(暴行・傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
- 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
- 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
- 過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
- 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
(引用元:厚生労働省「職場におけるハラスメント関係指針 」)
職務上の立場を利用して上記に当てはまる言動をとる従業員がいないか、企業は常に目を光らせておかなければなりません。
パワハラ防止のために企業が取り組む具体的な対策
ここでは、パワハラを発生させないために企業が取り組むべき対策についてご紹介します。
1. 事業主によるパワハラに関する方針の策定・周知
企業に求められる取り組みの一つとして、パワハラにどのように対応するのかを明示することが挙げられます。
具体的には、どのような言動がパワハラにあたるのかを示し、該当する言動を禁止するという方針を従業員に向けて発信し、就業規則に定めます。このとき、パワハラが発覚した際の行為者への懲戒処分についても定めておきましょう。
加えて、「パワハラがあってはならない」という風土を醸成するために説明会や研修を実施するなど、積極的な啓発活動も必要です。企業としてパワハラに対する厳しい姿勢を見せることが、抑止にもつながります。
2. パワハラ相談窓口の設置
従業員からパワハラに関する相談・苦情を受け付けるための窓口を設置しましょう。まだパワハラだと確定していない段階の、「発生の危険性がある」というレベルの事案でも、幅広く相談に応じる必要があります。
窓口は、社内で担当者を選定する社内窓口と、外部に委託する社外窓口の2つの方法から、社内の状況に合わせて選ぶのが望ましいでしょう。
窓口設置後は、従業員に向けて連絡先の社内告知を行い、ハラスメントを受けた際には気兼ねなく利用するように伝えることも大切です。
窓口の運用にあたり、相談後の具体的な対応フローの取り決めも必須です。従業員に「形だけの窓口」だと思われては、パワハラの抑止力や情報収集の役割を果たせません。対応の流れが明瞭であれば、従業員も安心感を持って利用できます。
3. パワハラ発生時の迅速かつ適切な対応
窓口への相談や従業員からの申告によってパワハラが発覚した場合は、スピーディーかつ的確な対応が必要です。あらかじめ取り決めたフローに従い、被害者・行為者双方への事実確認を速やかに行いましょう。
もし、双方の言い分に相違があれば、必要に応じて第三者からの聴取も実施します。
パワハラが事実であれば、懲戒の規定に沿って行為者の処分を検討しましょう。被害者が安心して働けるよう、人員配置の変更をしたり、メンタルケアを行ったりします。
再発の防止に向けて、社内の啓発を強化する、対応フローで改善点があれば変更するなどの事後対応も欠かせません。
4. 相談者・行為者への配慮
パワハラの相談を受け事実確認を行う際は、被害者・行為者のプライバシー配慮の徹底が求められます。
従業員が安心して相談窓口を利用できるよう、プライバシーを守りながら解決にあたることを、あらかじめ全社に向けて発信しましょう。
また、パワハラを相談したことによって被害者に不利益が生じないよう配慮するだけでなく、就業規則にも明記しておくことが大切です。
第三者への事情聴取も、被害者・行為者の双方に伝えたうえで行います。聴取される従業員にも、守秘義務についての同意を得ておきます。
パワハラ防止法に対応する相談窓口の設置方法
相談窓口の設置は、企業のパワハラ対策として欠かせません。
社内の人員で対応する「内部相談窓口」と外部委託の「外部相談窓口」の、それぞれの特徴や運営の注意点についてまとめました。
内部相談窓口
会社の内部に相談窓口を設置する場合、人事部や総務部の社員が自部署と兼任して窓口業務にあたるのが一般的です。
相談のフローやプライバシーの保護についての注意事項をしっかりと理解するため、事前の研修や教育の時間をしっかりと取りましょう。
中小企業だと、窓口担当と相談者がお互いを知っているケースも多いため、相談することに対して消極的になる可能性があります。
そのため、対面だけでなくメールやTV会議、電話など相談方法の選択肢を複数用意し、気軽に話せる環境を整えておくのが大切です。窓口の相談員にも精神的な負担がかかるため、ストレスケアを欠かさないようにしてください。
外部相談窓口
社内の相談窓口に従業員を配置して運営するのが困難な場合は、外部の相談窓口に委託するのも一つの方法です。法律事務所や社会保険労務士事務所のほか、外部窓口のサービスを提供している企業も多数あります。
外部窓口は、相談者にとっては見ず知らずの第三者となるため、気軽に話ができる点がメリットです。相談を受けた際に社内の人事部門などと密に連携を取り、解決に向けて迅速に対応できる体制を整えておくことが肝心です。
パワハラに関する裁判の実例
ここでは、パワハラに関する裁判の実例をご紹介します。
パワハラだと認められた例とパワハラではないと判決が下された例、それぞれの詳細を確認し、自社での対策に役立ててください。
パワハラが認められた事例
東京高等裁判所で1993年に判決が下された「松蔭学園事件」は、高等学校が職員である女性教諭に対して行った、授業・担任などの仕事外し、職員室内や別の部屋への隔離、自宅研修などの命令、一時金の不支給・賃金の据え置きなどの行為がハラスメントだと認められた事例です。
被告の学校法人は、600万円の損害賠償を課せられています。
この事例は、パワハラ6類型のうち「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「過小な要求」に当てはまります。これらの行為は、女性教諭が労働組合員であることに対しての嫌がらせであり、退職を促す意図があると見なされ、判決に至りました。
パワハラではないと判決を受けた事例
東京地方裁判所で2008年に判決が下された「損保ジャパン調査サービス事件」は、原告の訴えがパワハラとは認められなかった事例です。
自動車事故の原因調査や損害額の査定・交渉を行う会社にて、複数の対人トラブルを抱える原告が、上司である被告から退職や異動の強要、暴言を受けたと訴えを起こしました。
原告が受けたとされる退職を促す言動や暴言があったという事実が認められず、異動辞令の内容についても不当なものではなかったため、パワハラには該当しないとされた事例です。
特定の言動が嫌がらせであるかどうかは状況によって異なります。この裁判では客観的事実に基づいて証拠を整理した結果、パワハラではないという判決に至りました。
パワハラ防止法への対策は、企業規模を問わず急務です。就業規則への規定や相談窓口の設置について未対応の企業は、ぜひこの記事を参考に取り組みを始めてみてください。