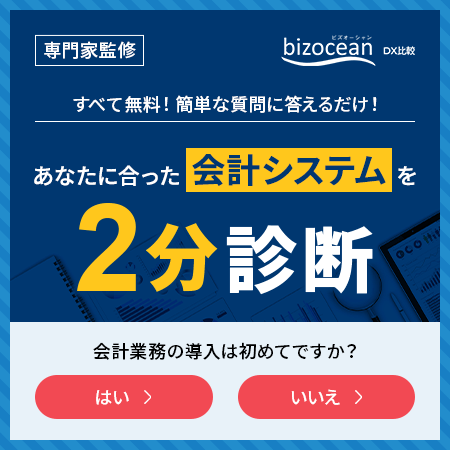人手不足における中小企業の解決策は? 導入すべき福利厚生や給料の引き上げとの違いを解説
~中小企業が福利厚生制度を設けることのメリットを紹介~
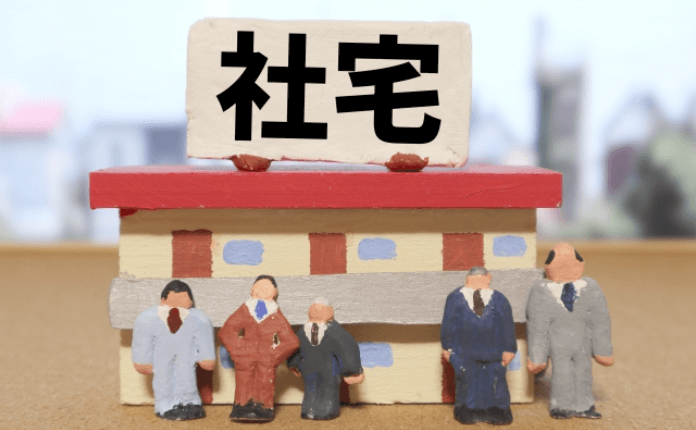
人手不足に悩む企業は、給料の見直しや福利厚生制度の導入など様々な解決策を取る必要があります。しかし、具体的にどのような事を行えばよいか分からず、悩まれている経営者や人事担当の方は少なくないでしょう。
本記事では、特に中小企業の方向けに、導入したい福利厚生制度や給与を引き上げることとの違いについて解説します。
人手不足で悩まれている中小企業の担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。

【この記事のポイント】
- 中小企業が人手不足を解消するには、給与引き上げだけでなく、福利厚生制度の充実が重要であり、採用競争力向上に直結する。
- 福利厚生は社員の税負担軽減や企業負担削減の効果があり、制度設計を誤ると給与とみなされ、課税対象となるリスクがある。
- 通勤交通費、社宅・寮、保険、食事補助などの制度は条件や上限を守り、事前に税務上の取り扱いを確認して導入する必要がある。
大前提は「圧倒的な人手不足」
福利厚生制度について考えるとき、前提となるのは「業種を問わず、全般的に人手不足の傾向が顕著である」ということです。
この原稿を書いているのは2022年1月です。現状ではコロナ禍の影響もあり、経済活動全体が停滞気味です。業種によっては人手不足というより、人が余っているような分野もあります。
その一方で、運輸関係や一部の建設・製造分野を中心に、人の募集をかけてもまったく反応がない、という話も散見されます。日本全体として少子高齢化、人口減少が進んでいるのは周知の事実です。
また昔に比べ、あらゆる人が情報を収集、検討することが可能となりました。「少しでも条件が良い会社に勤めたい」という要望はとても強いです。企業側も、求人を出す際には「具体的なメリットがみえる条件提示」が必要不可欠になっています。
中小零細企業にも福利厚生は必須
福利厚生制度というと、以前は大企業だけに許されている特権のように思われていました。しかし、上述の通り現在は「人手不足が慢性化している状態」で、かつ「企業の就業条件を比較検討することが簡単」な状況です。
そのため、中小零細企業であっても、一定の福利厚生制度くらい用意しないと、人を集めることはとても難しい状態なのです。
もちろん、大企業並みの福利厚生制度を用意することは、中小零細企業には困難です。資金量、保有する設備、人脈、あらゆる面で中小零細企業は大企業より厳しい状態です。しかし、その一方で「小さな会社の特性を活かした働き方」を上手に提示し、そこに福利厚生制度を絡めて、求人に成功している企業も存在します。
このような仕組みを構築するには、それなりの利益が必要です。しかし、逆説的には「それなりの利益を計上できるようになるためには、人を育てないと無理」ということも言えます。
この順番に関しては「鶏が先か卵が先か」の議論になりがちなのですが、企業としてある基準以上のステージに上がるためには、福利厚生制度の拡充は必要不可欠な時代になったのは、ほぼ間違いがないかと思います。
給与を引き上げることとの違い
ここまでの話を踏まえ、次のように感じた方もいらっしゃるかもしれません。
「つべこべ言わず、給与の金額を引き上げた方が良いのでは?」
これ、ある意味では正解です。やはり人材の質を引き上げていくには、人件費単価を上げていくのが一番簡単で、成功する確率も高いです。従って、福利厚生制度の拡充を目指すのは「ある程度人件費の単価が上がった後の話」であることは事実です。
その一方で、福利厚生制度をうまく使うと、単に人件費単価を上げたのとは異なるメリットがあります。それは社員に対する課税(社会保険を含める)です。例えば、次の2つを比較してみます。
①従業員Aに対する給与が30万円。
Aはその中から、仕事で役立つ資格を取得するため、3万円を払って専門学校に通った。
②従業員Bに対する給与が27万円。
加えて、Bが資格を取得するために、3万円の授業料を企業が負担した。
上の2つでは、税金や社会保険の負担が変わってきます。Aは30万円に対して賦課されるのに比べ、Bは27万円に対して賦課されます。従って、福利厚生制度を活用することで、従業員の租税公課負担が減らせるのです。
また、社会保険については企業側にも負担がありますので、その金額も減らすことができます。
給与として認定されてしまう可能性に注意
先ほどの事例では、わかりやすさを重視しているため、設定も簡素にしてあります。注意して頂きたいのは、福利厚生制度によっては、活用方法を間違えてしまうと給与認定されてしまうことがあるということです。
例えば、以下のような事例は、明らかに適切とは言い難いです。
この社員に対する税金や社会保険負担を引き下げる目的であることが、あまりにも露骨な事例です。
この場合、これらの福利厚生制度は税務的に認められず、給与に相当すると認定されてしまいます。もし給与と認定されてしまえば、あらためて給与として課税されるとともに、源泉徴収義務の違反も発生するため、企業側にも無用な負担が生じます。
福利厚生制度の大原則として、
- 福利厚生の目的に合致する
- 全従業員が平等に受けられる
- 常識の範囲内である
こういった条件があります。また、一部の制度については金額上の制限が設けられていることもあります。以下に紹介する具体的な福利厚生制度を活用する場合には、給与課税の可能性についてあらかじめ検討しておくことが大切です。
少し脅すようなことを書いてしまいましたが、きちんとルールを理解し上手に運用できれば、福利厚生制度は労使ともども利点があります。
具体的な福利厚生制度
以下、中小零細企業でよくみかける福利厚生制度をご紹介します。
通勤交通費
従業員に支給する通勤交通費は、給与として課税されません。ただし、実際の通勤方法や距離に応じて制限があります。「通勤交通費 非課税」といった単語で検索すると、情報が出てきます。
【関連記事はこちら】
交通費の非課税・課税の考え方|区分別の非課税限度額と注意点社宅や寮
企業側が社宅や寮を用意し、そこに従業員を住まわせる場合、企業が負担する家賃については給与として認定されません。
ただし、支払う家賃の50%以上の金額について、社員から社宅使用料を徴収する必要があります。社宅使用料が所定金額に満たない場合、その部分は給与認定されます。
社宅については、固定資産税の課税標準額等を基準に使用料を算定する方法もあります。大家さんの協力も必要なのですが、詳細は国税庁のタックスアンサー等で調べてみてください。
【関連記事はこちら】
社宅とは? 制度の基本的な知識や住宅手当との違いを解説!保険
生命保険や医療保険について、企業が契約者となり、従業員を被保険者として加入します。従業員に保険事故(死亡や病気)が発生した場合、企業に保険金が入り、それをあらためて従業員やその親族に支払います。
以前の記事でもご紹介した通り、最近では保険の種類もほんとうに増えてきました。また健康志向が高まっていることもあり、保険会社も福利厚生制度としての保険商品を開発するようになってきました。
実際の運用では「どこまでの社員が加入できるのか」といった辺りで、検討が必要です。また保険事故発生時に従業員や親族に支払う仕組みについて明確にしておかないと、トラブルにつながることもあります。「社員の死を利用して会社が保険金で儲けた」なんて悪評が立たないよう、注意しましょう。
その他、食事の補助や健康診断などもよくみかけます。
繰り返しになりますが、活用方法を間違えると給与と認定されてしまいます。制度ごとに条件も異なりますので、事前に調査をした上で導入をしていきましょう。