IT人材不足解消の鍵はリスキリング
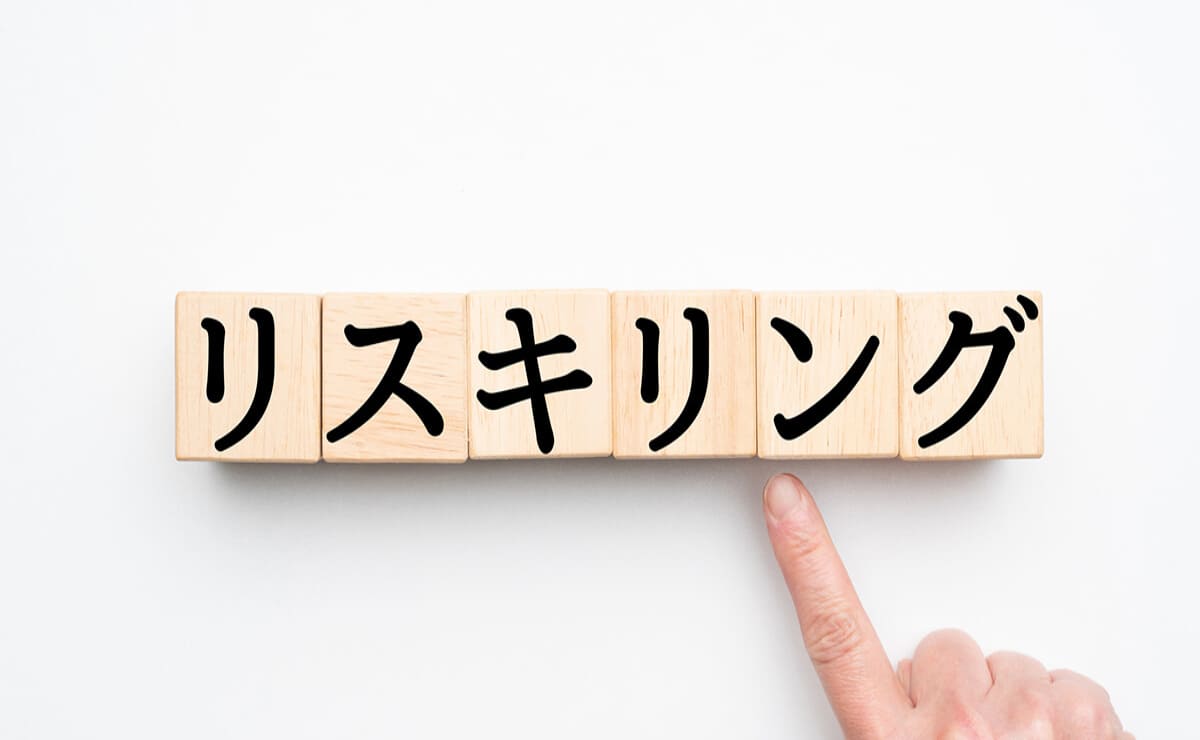
DXを推進する取り組みが広がりをみせる昨今、日本企業において1つの課題が顕在化しました。それがIT人材の不足です。
不足しているなら採用すればいい、そう思うかもしれませんが、ただでさえ労働人口の減少が著しい中で、専門のスキルを持った人材を雇用するのは、かなりハードルが高いといえます。
そこで、今回の記事では、DX時代の人材戦略における重要なキーワードである「リスキリング」について、詳しく解説したいと思います。
そもそもリスキリングって
まずは、そもそもリスキリングがどういう意味なのかについて説明します。
リスキリングとは、「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること」を指します。
(引用:リスキリングとは―DX 時代の人材戦略と世界の潮流―、リクルートワークス研究所資料)
2022年10月、臨時国会における岸田文雄総理の所信表明演説にて、リスキリングの支援に今後5年間で1兆円の予算を投じる方針を発表したことで話題となりました。
リスキリングとよく似た言葉
リスキリングが何か分かったところで、次は意味がよく似た言葉についてみてみましょう。
1.リカレント教育
リスキリングと混同されがちな言葉の1つに「リカレント教育」があります。
学ぶという点においてはどちらも同じですが、リスキリングが企業にとって必要な知識やスキルを戦略的に身に付けるのに対し、リカレント教育は、従業員自身が身に付けたい知識やスキルを自主的に学ぶことを指します。
また、リスキリングが仕事と並行して学ぶことを前提としているのに対し、リカレント教育は、「仕事の場から離れて学習し、再び仕事に就く」の繰り返しを指すため、学びの期間中は離職していることが想定されています。
2.アップスキリング
アップスキリングもまたリスキリングと混同されやすい言葉です。
アップスキリングは既に持っているスキルをもっと伸ばすために学習することを指すのに対し、リスキリングは企業の状況に応じて、新しいスキルを身に付ける必要があります。
3.OJT(On-the-Job Training)
リスキリングと意味がよく似ている単語として、最後にOJTが挙げられます。
OJTは、いまある業務を実践を通して身に着けることを指しますが、その一方でリスキリングは、いまはまだ存在しないもの、誰もできないものを身に付ける必要があります。
リスキリングのメリット
次はリスキリングのメリットについてみてみましょう。リスキリングを行うメリットには以下の3つが挙げられます。
1.IT人材不足の解消
リスキリングにより、組織全体で必要なIT人材を育成することが出来れば、わざわざ競争率の激しい社外から採用する必要がなくなります。
また、社内で人材育成を行うことで、採用コストや教育コストの削減につながります。
2.イノベーションの創出
リスキリングにより従業員が知識やスキルを身に付けることで、新たなアイディアが生まれ、これまでのビジネスモデルやサービスに変革をもたらすかもしれません。
3.企業文化の継承
新たな価値観や文化は、社内で変革を起こすうえで不可欠である半面、既存の企業文化に理解がないと、社内から反発を買ってしまう可能性があります。
リスキリングの場合、元からいる従業員を対象に再教育を行うため、社風や価値観、行動規範といった企業文化を保持しながら、自社を取り巻く環境の変化に対応していくことができます。
リスキリングの進め方
リスキリングの概要が分かったら、次はリスキリングの進め方についてみていきましょう。
推進の手順
リスキリングの推進は以下の3つの手順に従って行います。
ステップ1:必要なスキルの明確化
まずは、リスキリングによりどのようなスキルを取得する必要があるのかを明確化しなければなりません。
明確化の仕方としては、自社のDX戦略(デジタル化によりどのような変革を起こすのか)に必要となるスキルと、従業員が既に持っているスキルとを比較して、不足しているものを洗い出します。
この際、スキルデータベースやスキルマップを使用することで、スキルギャップが可視化され、より比較しやすくなります。
ステップ2.プログラムの作成
自社に必要なスキルがはっきりしたら、次はそのスキルをどのように取得するのかのプログラムを作成します。
例えば、スキル取得の方法は研修会のような形式なのかe-Learningのような自主学習なのか、または、リスキリングの対象は全従業員なのか一部対象者なのか、他にも、どのようなコンテンツを用意すべきなのかや、インセンティブを設けるか否かなど、リスキリングの制度を整備しましょう。
ステップ3.実践
どのようなスキルであっても、学習だけで身に付けることはできません。
そのため、実際の業務やプロジェクトなどの実践において、学んだスキルを活用するための場を用意する必要があります。
さらに、実践を通じて得た体験をリスキリングのプログラムにフィードバックを行い、それを繰り返すことで、より有意義なプログラムへとブラッシュアップできるでしょう。
留意すべきポイント
次はリスキリングの推進を行う上で留意したいポイントをみていきましょう。
ポイント1:全社的な協力体制
前述にもあるように、リスキリングは通常業務と並行して行うことを前提としているため、
受講者の所属部署や関係者から反発される可能性は少なくありません。
そのため、リスキリングを実施する際は、なぜリスキリングを行うのかやどのようなスキルが身につくのか、そのスキルが業務の中でどのように活きるのかなど事前に説明を行い、全社的な協力体制を得られるように心がけましょう。
ポイント2:主体的に取り組むための仕組み
リスキリングによる学習の効果を左右する大きな要因として、従業員自身の主体性やモチベーションが挙げられます。
そのため、リスキリングの制度や教育のプログラムを用意することはもとより、インセンティブを設けたり、公募制を取り入れるなどの工夫をすることで、より大きな効果を得ることができるでしょう。
ポイント3:外部サービスの活用
リスキリングのプログラムを全て自社で実施しようとすると、膨大な時間と手間がかかってしまう可能性があります。
そこで、自社で必要とするスキルに応じて、外部のサービスを活用するという手もあります。
国内外に数多く存在する学習コンテンツやプラットフォームを活用することで、時間を節約しながら、より良質なリスキリングを行うことが出来るかもしれません。
ポイント4:ノーコードシステムの利用
IT人材の育成は本来、長期的に取り組む必要がありますが、その一方でDX推進は多くの企業で喫緊の課題なのではないでしょうか。
そこでおすすめしたいのが、ノーコードシステムによる業務のデジタル化です。
ノーコードシステムとは、ソースコードの記述なしで開発できるシステムを指し、プログラミングに関連する専門知識を一切必要としません。
そのため、ノーコードシステムを上手く活用することで、リスキリングにより専門的なスキルを身に付けている途中であっても、社内DXを推し進めることができます。
リスキリング推進にはワークフローシステム
最後に、リスキリングの推進をサポートするツールとしてワークフローシステムをご紹介します。
ワークフローシステムとは、稟議をはじめとした業務手続きをデジタル化するシステムで、導入することでリスキリングに下記のような効果をもたらします。
1.ボトルネックの発見
ワークフローシステムを導入するには、既存の業務について、可視化し整理する必要があります。
「どの工程で」「誰が」「何をするのか」が明らかになることで、DX推進のボトルネックが表出するため、そこから必要なスキルを抽出することができます。
2.学習時間の確保
繰り返しになりますが、リスキリングは通常の業務と並行で行うため、学習に充てる時間を確保するのが難しい場合があります。
そこで、ワークフローシステムの導入により、申請業務の効率化および工数削減につながり、スキル習得に取り組む時間と心の余裕が生まれます。
3.コストの捻出
自社で行うにしても外部サービスを利用するにしても、リスキリングを行うにはある程度のコストがかかります。
ワークフローを利用すれば、社内文書のペーパーレスが推進され、紙代やインク代といった印刷コストはもちろん、拠点間での書面のやり取りで発生する郵送コストの削減が期待できます。
こうして捻出したコストを、設備やコンテンツ、講師料などに充てることで、より充実したリスキリングを行うことができるでしょう。
まとめ
冒頭にも述べたように、労働人口が年々減りゆく中で、いかにIT人材を自社に取り込むかは、DX推進における至上命題ともいえます。
ぜひ、今回ご紹介したリスキリングおよび、それをサポートするワークフローシステムを解決策の1つとしてご検討していただければと思います。

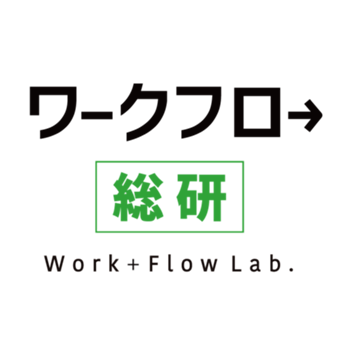 ワークフロー総研
ワークフロー総研
