近年注目を集める週休3日制とは

昨今「週休3日制」というキーワードを目にする機会が増えました。
しかしながら、週休3日について関心はあるものの、
- 「休みが増えるのは嬉しいけれど、1日の労働時間や給与はどうなるの?」
- 「業績の維持・向上はできるのか?」
- 「ちゃんと定着するのか?」
など、疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
そこで今回のコラムでは、メリットやデメリット、制度導入の際のポイントなど週休3日制の基本的な情報についてお伝えしたいと思います。
週休3日制には3種類ある
現在の日本企業では、週休二日制が一般的ですが、2021年6月に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2021(骨太の方針)」のなかで言及されたことがきっかけで、働き方改革の一環として週休3日制を取り入れる企業が増えつつあります。
しかし、一概に「週休3日制」といってもさまざまスタイルがあり、導入企業は自社の状況に併せて取り入れています。
1.給与維持型
「給与維持型」の週休3日制とは、給与水準を維持しつつ休日を増やす制度になります。
なお、「給与維持型」は、1日の労働時間はそのままのため、1週間での合計労働時間については、週休2日制の時に比べて減少することになります。
- 【週休2日制の1週間あたりの労働時間】8時間(1日あたり)×5日間=40時間
- 【週休3日制の1週間あたりの労働時間】8時間(1日あたり)×4日間=32時間
そのため、「給与維持型」を導入する際は、現状よりも高い生産性が求められるようになります。
2.労働時間維持型
「労働時間維持型」は、1週間あたりの総労働時間を変えずに週休3日制を取り入れる制度を指します。
この場合、1日あたりの労働時間が週休2日制と比べて長くなります。
- 【週休2日制の1日あたりの労働時間】40時間÷5日間=8時間
- 【週休3日制の1日あたりの労働時間】40時間÷4日間=10時間
労働時間維持型の取り組み事例
株式会社zozo
株式会社zozoは、働き方の多様化の観点から、2021年に従業員の希望によって、週休2日制と労働時間維持型の週休3日制を選択できる、選択式の制度を導入しました。
この制度では、従業員は半年に1回週休3日制に変更するかどうか選ぶことができ、制度の対象である部門の従業員100人のうち、およそ2割から4割が常時週休3日制を選択しており、モチベーションの向上や残業時間の削減などの効果を得ています。
3.給与減額型
「給与減額型」の週休3日制は、1日の労働時間はそのままで、週に3日休む制度を指します。
なお、減った給与を補填する手段として副業が考えられるため、「給与減額型」の週休3日制の導入を考える場合は、併せて副業に関する規定についての見直しも行うといいでしょう。
給与減額型の取り組み事例
塩野義製薬株式会社
塩野義製薬株式会社では、2022年の4月から従業員が「給与減額型」の週休3日制を選択できる制度を導入しました。
この制度では、利用の事由が問われることなく年度単位で申請が可能で、週休3日制を選択すると、週休2日制の場合の80%相当の給与が支払われることになります。
また、週休三日制の導入と同時に副業規定の見直しや自己投資支援制度の整備が同時に行われました。
運用開始からそれほど時間が経過していないので、現状まだ効果検証中ですが、副業や自己投資による従業員のスキルアップが期待されています。
週休3日制は義務化されるのか?
徐々に拡がりをみせつつある週休3日制ですが、義務化については、現状具体的な政策があるわけではありません。
前述にある、「経済財政運営と改革の基本方針2021(骨太の方針)」でも、「選択的週休3日制度について、育児・介護・ボランティアでの活用、地方兼業での活用などが考えられることから、好事例の収集・提供等により企業における導入を促し、普及を図る」と記載されています。
また、「令和4年就労条件総合調査」(厚生労働省)によると、完全週休2日制より休日日数が実質的に多い制度(月1回以上の週休3日制、3勤3休、3勤4休など)を導入している企業は、全体の8.6%に留まっています。
週休3日制のメリット・デメリット
昨今の新しい働き方として注目を集める週休3日制ですが、一長一短があります。
週休3日制のメリット
1.ウェルビーイングの向上
近年のビジネスシーンにおいて、その重要性が高まるウェルビーイングとは、「肉体的・精神的・社会的に満たされた状態」を指します。
週休3日制を導入することで自由に使える時間が増え、休養や趣味、習い事、家族との時間に充てることができるため、ワークライフバランスを整えやすく、従業員の心身の充足が期待できます
2.人材獲得
週休3日制を導入することで、求職者に対して、多様な働き方に対応している企業としてアピールすることができるため、人材獲得の面で有利になります。
3.離職の防止
週休3日制を導入することで、仕事と家庭を両立させやすくなるため、これまで、家庭のやむを得ない事情により、退職を余儀なくされてきた人材の流出防止につながります。
4.生産性の向上
特に給与維持型の場合は、今までより少ない時間でこれまでと同じかそれ以上の成果を出す必要が出るため、必然的に生産性向上のための仕組みが整います。
また、従業員も業務効率化を意識しながら労働に従事することが期待できます。
5.コスト削減
週休3日制を導入することで、従業員の通勤や残業の手当の削減が期待できます。また、場合によっては、オフィスの稼働も減らすことができるので、光熱費など経費削減にもつながるかもしれません。
週休3日制のデメリット
1.人事労務業務の煩雑化
現状、週休3日制が試験的あるいは選択的に導入されていることが多いため、週休2日制と3日制の従業員が混在しており、勤怠の管理や人事評価などの業務で、担当者の負担が大きくなる可能性があります。
2.ビジネスチャンスを逃すリスク
週休3日制の導入により、顧客の問い合わせに対する迅速な対応や取引先との円滑なコミュニケーションが妨げられてしまい、せっかくのビジネスチャンスを逃してしまうリスクが考えられます。
3.従業員間のコミュニケーションの減少
休暇が増えるということは、必然的に1日分の従業員どうしのコミュニケーションが少なくなります。
コロナ禍では、リモートワーク導入時も従業員間のコミュニケーションを問題視する声が少なくなかったですが、コミュニケーションの減少を補う体制を整えないまま導入してしまうと、進捗が把握できないなど、業務に影響を及ぼす可能性も考えられます。
週休3日制を導入するためのポイントとは
上記のメリットやデメリットを踏まえた上で、自社で週休3日制を取り入れるにはどのような点に留意すればいいのか、導入のポイントについてまとめました。
1.方針の決定
前述にもあるように、週休3日制にはメリット・デメリット、また、さまざまなタイプがあるため、それぞれの検証を入念に行った上で自社に合ったスタイルを見極める必要があります。
そもそも、何のために週休3日制を導入するのか(目的)や、導入することでどのような効果を期待するのか、それらを実現するための運用方法や、想定される課題と対応策を十分に検討し、導入方針を決定しましょう。
2.ワークフローの見直し
特に給与維持型の週休3日制の場合、生産性の向上が必要となるため、既存業務のワークフローの見直しは不可欠です。
週休3制のもとで業務を円滑に遂行するためにも、現在行っている業務の棚卸を行い、ボトルネックの洗い出しや、それを解消するためのソリューションの導入などを検討しましょう。
3.基幹システムの見直し
前述にもあるように、週休3日制を導入すると、勤怠管理や人事評価、給与計算などに少なからず影響を与えます。
そのため、勤怠管理システムや人事システムなどの基幹システムのリプレイスを余儀なくされるケースもあるでしょう。
この際、1部の業務だけではなく社内体制全体を意識した導入計画を設計することで、組織全体の業務効率化につなげることができます。
週休3日制の導入をアシストするワークフローシステム
さて、ここまで週休3日制の概要について説明してきましたが、いざ導入しようと思っても、何からはじめていいのか分からないという人も少なくないのではないでしょうか。
そこで、そんな人たちにおすすめしたいのがワークフローシステムです。
ワークフローシステムとは、稟議をはじめとした業務手続きを電子化するシステムです。
導入することで、以下のような理由から週休3日制の導入をサポートします。
ワークフローシステムが週休3日制の導入に役立つ理由
1.ワークフローを可視化できる
前述にあるように、週休3日制のもとで生産性を上げるには、ワークフローの見直しが不可欠です。
ワークフローシステムを導入する際は、必然的にオンライン上でワークフローを再現する作業が発生するため、ボトルネックや、既存業務において変更が必要な箇所を発見することができます。
また、週休3日制を導入した後にも、ワークフローの継続的な改善に役立てることができます。
2.システム連携でさらに効率化できる
製品にもよりますが、ワークフローシステムの中には、さまざまな外部システムやクラウドサービスと連携することできるものがあります。
ワークフローシステムと他システムを連携することで、各システムごとで行われていた業務手続きをワークフローシステムに集約することができるため、業務の効率化につなげることができます。
多様な働き方に対応できる
ワークフローシステムを導入することで、書類の作成や申請、承認といった、業務手続きに伴うあらゆる作業を電子化することができます。
そのため、オフィスに来なくて、自宅のPCやスマホから作業ができるため、テレワークの定着も可能になり、週休3日制と合わせて、多様な働き方に対応することができます。
まとめ
多様な働き方が求められるようになって久しい昨今において、新しい働き方の導入に足踏みする企業も多い中で、先行企業の効果次第では、週休3日制が義務化される日もそう遠くないのかもしれません。
いきなり全てを変えてしまうことは難しいかもしれませんが、まずはワークフローシステムを導入することで、週休3日制や多様な働き方の基盤を整えてみるのはどうでしょうか。

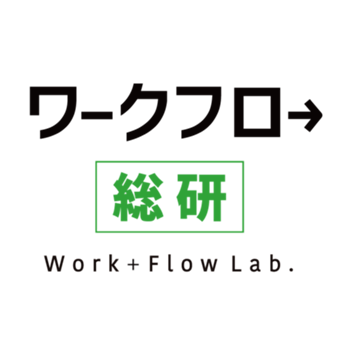 ワークフロー総研
ワークフロー総研
