マルチプルとは? 指標と計算方法・メリット・デメリットを解説
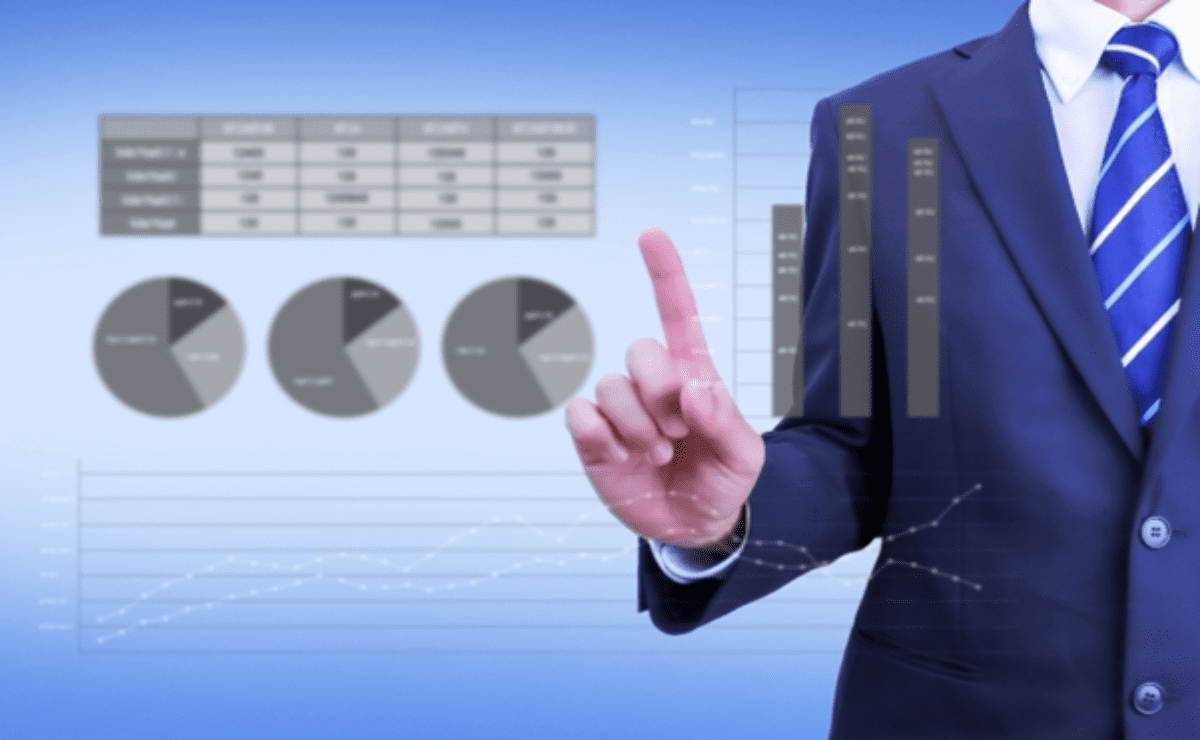
マルチプル法とは、企業価値を測る手法の一つです。
企業価値はさまざまな手法で算出できますが、マルチプル法はその中でもシンプルかつ簡単に計算できる点が特徴です。
本記事では、マルチプルの概要、他の手法との違い、使用する指標や実際の算出手順などを解説していきます。

マルチプルとは?
マルチプル(multiple)は英語で「倍数」を意味する単語です。経済においては「企業価値の倍率」を意味する言葉として用いられます。
マルチプル法とは類似する企業同士を比較することで、企業価値や株式価値を導き出す手法です。
特定の指標において、ある企業ともう一方の企業を比較した際、両者の差が何倍であるかを見て企業価値を比べることができます。
マルチプル法とほかの手法との違い
企業価値や株式価値を計算することを、バリュエーションといいます。
バリュエーションには以下の3種類があります。
- マーケット・アプローチ
- インカム・アプローチ
- コスト・アプローチ
マルチプル法は、上記のうちマーケット・アプローチに該当する手法です。ここでは、3種類のバリュエーションについてそれぞれ解説します。
マーケット・アプローチ
マーケット・アプローチでは、市場取引に焦点を当て企業価値を算出します。特定の指標における倍率で企業を比較するマルチプル法も、マーケット・アプローチのうちのひとつです。
マーケット・アプローチには、マルチプル法のほかに市場株価法という手法があります。市場株価法では、ある期間での平均株価を比較することで企業価値を評価します。
インカム・アプローチ
インカム・アプローチでは、利益予想やキャッシュフロー予想を基に企業価値を評価します。代表的なものとしてはDCF法があります。
マルチプル法などのマーケット・アプローチでは、企業と企業を比較することで相対評価的に企業価値の算出をおこないますが、インカム・アプローチは絶対評価的に算出する点が特徴です(ただし、DCF法による企業価値の算定では割引率など類似会社のデータを使用する係数が登場しますので、その点においては相対評価となります)。
コスト・アプローチ
コスト・アプローチでは、純資産の額から企業価値の評価します。
貸借対照表に記載された純資産を基におこなう簿価純資産法と、資産や負債のすべて、あるいは算出に大きな影響を与える一部の科目を時価に置き換えて計算する時価純資産法の2種類があります。
短時間で、手軽に算出できる点が特徴です。
マルチプル法で求められる価値の種類
マルチプル法によって市場価値や投資価値を見極めることになりますが、求める指標は以下の2つです。
- 企業価値
- 株式価値
これらは投資家などが投資先を選定するうえで、重要な判断基準になります。実際に株式を買ったり売ったりする「価格」が理論的に導き出される「価値」よりも安ければ割安、高ければ割高だと判断することができます。
それぞれ見ていきましょう。
1.企業価値
マルチプル法は、もともと企業価値を評価するための手法として作り出されたものです。企業価値は株式価値と債権者価値の和となります。
マルチプル法のうち、代表的なEV/EBITDAマルチプル(EBITDAマルチプル)という手法では、株式市場に上場する複数の類似企業のEV(Enterprise Value、企業価値のこと)とEBITDA(後述参照)の倍率を用いて、評価対象企業の企業価値を算出します。
上述の通り複数の企業を比較しながら、その価値を導き出せる点が特徴です。ただし企業価値は、ひとつの手法に絞らず複数の手法を併用することで、より正確に測ることができます。
マルチプル法と並行して、DCF法など他の手法でも評価をおこなうと良いでしょう。
2.株式価値
株式価値と企業価値との関係は上述の通りですので、計算式を組み替えると株式価値=企業価値-債権者価値となります。
EV/EBITDAマルチプルを例に取ると、算出した企業価値から純有利子負債(有利子負債及び有利子負債同等物から現金及び現金同等物を差し引いた正味の有利子負債の額)を差し引くことで株式価値を求めることが可能です。
マルチプル法を用いるメリット・デメリット
ここでは、マルチプル法のメリットとデメリットを解説します。
マルチプル法を用いる際には、メリットとデメリットを理解したうえで、適切に活用しましょう。
マルチプル法のメリット
マルチプル法のメリットは以下のとおりです。
- 計算方法がシンプル
- 客観的な相対評価
それぞれ見ていきましょう。
計算方法がシンプル
計算方法がシンプルで扱いやすいことが、マルチプル法のメリットのひとつです。
具体的な計算方法については後述しますが、マルチプル法は、企業価値の算出に用いられる幾つかの手法のなかでも、比較的簡単に扱うことができます。
計算にあたって必要なデータも少なく、企業価値を知りたい企業と、その比較対象となる企業のデータがあれば事足ります。
また、計算がシンプルなことは、単に時間や手間を削減するだけでなく、ヒューマンエラーを減らす効果もあります。
客観的な相対評価
マルチプル法では、企業価値を知りたい企業の比較対象として、業界や規模が近い上場企業のデータを用います。
上場企業のデータは、株式市場で常に多くの評価に晒されているため、客観性が高い比較対象となります。
マルチプル法のデメリット
続いて、マルチプル法のデメリットを見ていきましょう。
以下の項目を紹介します。
- 比較対象とする企業を選定する必要がある
- 市場の変動が大きい状況下では使いにくい
それぞれ解説します。
比較対象とする企業を選定が難しい
マルチプル法を用いて対象企業の企業価値を算出する際には、比較対象とする上場企業を適切に選ぶ必要があります。
このとき比較対象の企業は、業界や規模が対象企業に近いものを選ばなければいけません。
大きくかけ離れていると、正確な企業価値を算出することができないので、比較対象の選出はマルチプル法で最も難しい部分といってもいいでしょう。
特に対象企業の独自性が強く、類似点の多い比較対象を見つけられない場合は、苦労しがちです。
市場の変動が大きい状況下では使いにくい
上場企業のデータを参照するマルチプル法は、リアルタイム性が高い一方で、短期間で市場が大きく動いている際には適しません。
マルチプル法で用いる指標と計算方法
マルチプル法では、次のような指標が用いられます。
- PBR(株価純資産倍率)
- PER(株価収益率)
- EBIT(利払前・税引前利益)
- EBITDA(利払前・税引前・償却前利益)
一つずつ解説していきます。
PBR(株価純資産倍率)
PBR(Price Book-value Ratio:株価純資産倍率)は、企業の純資産に対して株価がどの程度あるのかを示す指標です。
PBRを求める計算式は以下のとおりです。
PBR=株価÷BPS(1株あたり純資産)
PBRを見れば、ある時点の株価が本来の株式価値よりも割安なのか割高なのかを判断することができます。
一般的にPBRの値が低ければ割安、高ければ割高と判断されます。
PER(株価収益率)
PER(Price Earnings Ratio:株価収益率)は、株価が1株あたりの純利益の何倍まで買われているかを示す指標です。
PERは以下の計算式で求めることができます。
PER=株価÷EPS(1株あたり純利益)
PERはPBRと同じく、ある時点の株価が割安なのか、割高なのかを判断する際に用いられます。こちらも値が低いほど割安、高いほど割高と判断されます。
EBIT(利払前・税引前利益)
EBIT(Earnings Before Interest and Taxes:利払前・税引前利益)は、企業の税引前利益から、支払利息を足し戻した数値です。受取利息があれば差し引きます。
EBITを求めるための計算式は、以下のとおりです。
EBIT=税引前利益+支払利息−受取利息
EBITは主に、創業直後のスタートアップやベンチャー企業の企業価値を表す際に用いられます。
創業直後の企業は借入額が大きく、それにともなう支払利息も大きいため、実際の収益力に対して利益が少なくなってしまいます。
EBITを用いれば、借入金が大きい企業であっても、その企業の収益力が分かりやすいです。
EBITDA(利払前・税引前・償却前利益)
EBITDA(Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization:利息・税金・減価償却費及び償却費控除前利益)は、企業の税引前利益から、支払利息、税金、減価償却費を足し戻した金額です。
EBITとの違いは、減価償却費を足し戻すかどうかで判断します。
EBITDAを求める際の計算式は、以下のとおりです。
EBITDA=税引前利益+支払利息-受取利息+減価償却費
(簡易的に営業利益+減価償却費で算出されることが多いです。)
創業直後のベンチャー企業やスタートアップは借入金が多く、その利息によって利益が少なくなることは前述のとおりです。
しかし、設備投資が多い企業の場合も減価償却費が影響し、利益が小さくなります。
EBITDAを用いれば、借入金や減価償却費が大きい企業であっても、その収益力を測りやすくなります。
また、税金や減価償却費は国によって計上の基準や方法が異なるため、EBITDAは外国籍企業と比較する際にも有用な指標といえます。
マルチプル法を用いて価値を算出する手順
マルチプルを用いて企業価値を算出する際には、以下の5つの手順を踏んでいきます。
- 類似企業の選定
- 採用マルチプルの選定
- 財務情報等の収集・整理
- マルチプルの算出
- 企業価値および株式価値の算出
一つずつ見ていきましょう。
1.類似企業の選定
まずは、評価対象企業と、業種・業態・規模ができる限り近い上場企業を数社選定します。
例えば、評価対象企業がBtoB向けクラウド型ソフトウェアの開発を主たる事業として展開している場合、単に上場しているソフトウェア開発企業をスクリーニングして上から順に選定していけばよいというわけではありません。
ソフトウェア開発企業の中でもオンプレミス型ではなくクラウド型のソフトウェアを自社開発していること、さらにBtoB向けであることが重要です。
また、収益や利益、従業員数や拠点数といった規模感を示す項目をチェックし、概ね同水準の企業を選定してください。
2.採用マルチプルの選定
様々なマルチプルがありますが、一般的に採用されるのはEV/EBITDA、PER、PBRの3つです。
よほど特殊なケースでない限りは、この3つのマルチプルを採用しましょう。
3.財務情報等の収集・整理
マルチプルの算出に必要な財務情報等を、各企業のホームページに掲載されているIR情報や株式情報サイトなどから収集し、表計算ソフトに整理していきましょう。
なお、可能な限り同条件の情報を収集することが重要です。
例えば、財務数値は直近期の数値を用いること、株価はいずれも同じ日の終値ベースで整理するなどといったことです。
4.マルチプルの算出
各企業のマルチプルを算出した上で、これらの最大値・最小値・平均値・中央値を算出しましょう。
他社とあまりにも値が乖離していて平均値・中央値の算出に影響を与えるような企業は、類似企業から除外することも検討します。
ここまでくれば、企業価値と株式価値を算出するための材料がそろったことになります。
5.企業価値および株式価値の算出
EV/EBITDAマルチプルでは、はじめに企業価値を算出し、企業価値から純有利子負債を差し引いて株式価値を算出します。
PERとPBRについては、株式価値から先に算出するのが一般的です。企業価値を求める場合は、株式価値に純有利子負債を加算します。
以上でマルチプル法による企業価値と株式価値が算出できますが、各マルチプルで算出した企業価値や株式価値はどの程度の開きがあるのか、最大値と最小値で算出した場合のレンジはどこからどこまでなのか、重なる部分はあるのかといったことを比較することが重要です。
そのような場合は、表計算ソフトで「フットボールチャート」と呼ばれるグラフを作成すると、視覚的に分かりやすくなります。
また、これまで述べてきたように、マルチプル法だけで企業価値と株式価値を判断することは、基本的にありません。
DCF法や純資産法などの様々なバリュエーション評価で算出し比較することで、多角的・総合的な投資判断が可能になるのです。
マルチプルについてのまとめ
マルチプル法とは、ある指標を用いて対象企業を他の企業と比較することで、企業価値や株式価値を導き出す手法です。
企業価値を求める方法は幾つかありますが、マルチプル法はその中でもシンプルで扱いやすく、客観的な数値が出やすい点がメリットです。
反面、どの企業を比較対象にするかの選定が難しく、市場の変動が大きいときには使いにくいといったデメリットもあります。
M&Aに際して、自社の企業価値を把握しておきたい場合は、ぜひ活用してみてください。

