売価還元法とは? メリット・デメリットと評価方法をわかりやすく解説
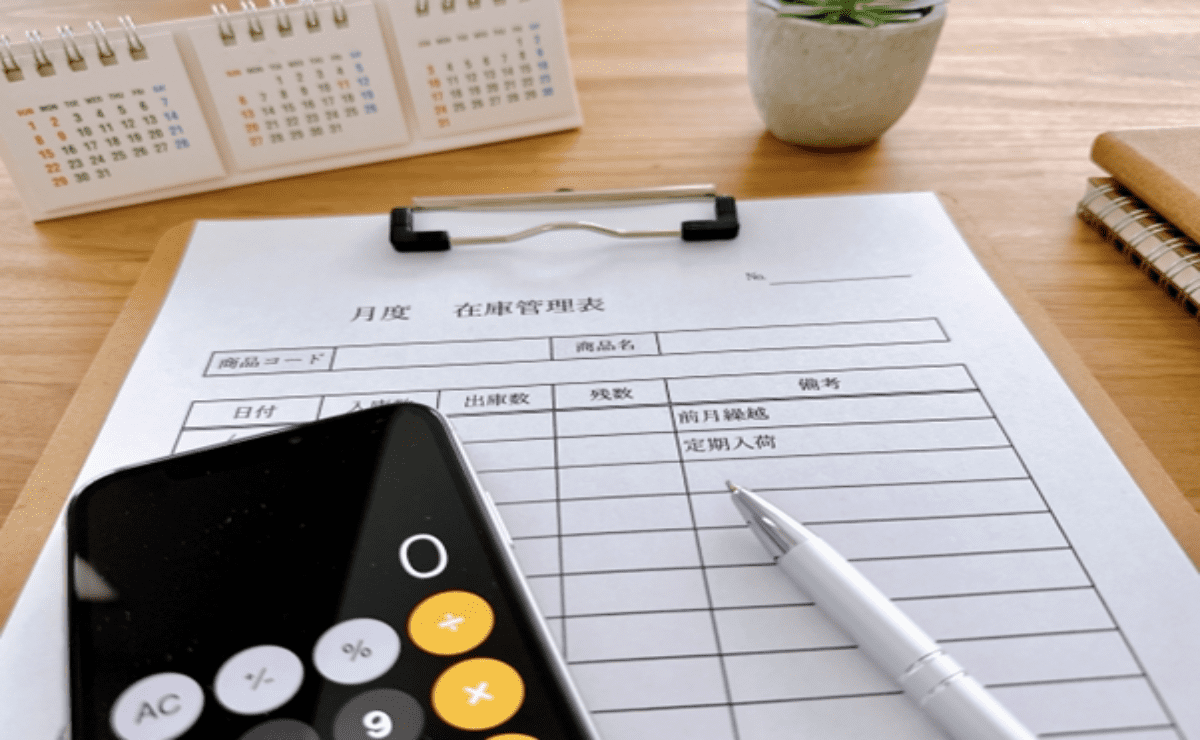
売価還元法とは棚卸資産の評価方法の1つです。売価還元法は比較的容易に棚卸資産を評価できるなどのメリットがある一方、知っておきたいデメリットも存在します。
実際に取り入れる前に、詳しい評価方法や特徴について理解しておくことが大切です。この記事では、売価還元法とはなにか、用いるメリットやデメリットのほか計算手順を解説します。

売価還元法とは
売価還元法とは、棚卸資産における評価方法の1つです。
棚卸資産の評価方法では、品目別に評価する手法が多く、多数の品目を扱う業種では莫大な工数がかかります。
しかし、売価還元法は、値入率や回転率などを用いて棚卸資産をグループ化し、それぞれの原価を求める方法です。
他の評価方法と比べると比較的容易で、価格変動が起きても在庫の評価額と実際の価格との差が抑えられることから、小売業などで利用されています。
原価法の種類
売価還元法の理解を深めるために、原価法の種類について解説します。
- 総平均法
- 移動平均法
- 先入先出法
- 個別法
- 最終仕入原価法
各方法には独自の特徴があり、企業のニーズに応じて選択されます。
総平均法
総平均法は、期首在庫と期中の仕入れを合算し、その総額を総数量で割ることで平均単価を算出する方法です。
総平均法は、在庫の平均単価を計算し、安定したコスト管理ができます。在庫が頻繁に変動する場合でも、一貫した原価計算が可能になるためです。
移動平均法
移動平均法は、新しい在庫が入るたびに平均単価を再計算する方法です。
移動平均法は、在庫の変動に即応して平均単価を更新します。これにより、最新の仕入価格が原価に反映され、より正確なコスト管理が可能となるためです。
移動平均法は、在庫価格の変動に敏感に対応し、リアルタイムでの原価管理に優れています。
先入先出法
先入先出法(FIFO)は、最初に仕入れた在庫が最初に消費されると仮定する方法です。
先入先出法は、古い在庫から順に使用することで、在庫の鮮度を保ちます。これにより、在庫の回転率が向上し、廃棄リスクが低減されます。
個別法
個別法は、各在庫の原価を個別に管理する方法です。
個別法は、高価なブランド品や少量多品種の在庫管理に最適です。各在庫の原価を正確に追跡することで、コスト管理の精度が向上します。
高価な機械や特定のブランド商品など、個々の原価を詳細に管理する必要がある場合に用いられます。
最終仕入原価法
最終仕入原価法は、最も新しい仕入れの単価を在庫の評価基準とする方法です。
最終仕入原価法は、最新の市場価格を反映します。これにより、現時点での在庫価値を正確に評価でき、価格変動に迅速に対応できます。
売価還元法を用いるメリット
売価還元法を用いるメリットは、棚卸資産をグループ分けするため、資産をまとめて評価できることです。
また、原価率を用いて計算するため棚卸資産を受け入れるたびに計算する必要がありません。
品目ごとの細かな管理や計算がないため、比較的容易に棚卸資産を評価できます。
売価還元法を用いるデメリット
売価還元法を用いるデメリットは、棚卸資産のグループ分けの難易度が高いことです。
値入率や回転率の類似性などを用いてグループ分けを行いますが、明確な基準などがなく判断が難しいです。
業種や状況によっても差が生まれるため、グループ分けがうまくいかないケースも多く、棚卸資産の評価が適切でない可能性もあります。
【計算】売価還元法による評価方法
売価還元法を用いた評価方法は、以下の4つのステップで行います。
- グループ分けをする
- 原価率を算出する
- 評価額を求める
- 税務上の事前届出
各ステップについて詳しく解説し、具体的な計算例を交えて説明します。
1.グループ分けをする
棚卸資産を値入率の違いによりグループ分けすることが必要です。値入率とは、棚卸資産の販売価額に対する利益額の割合です。
例:
販売価額:100円
利益:20円
値入率:20%(20円 ÷ 100円)
値入率が同じであれば原価率も同じになります。したがって、原価率を統一するために、値入率の近い商品をグループ化します。
2.原価率を算出する
売価還元法では、棚卸資産の販売価額に原価率を乗じて評価額を算定します。原価率は以下のように計算されます。
<原価率の計算式>
原価率=原価/販売価額
<例>
原価:80円
販売価額:100円
原価率:80%(80円 ÷ 100円)
売価還元法には、「売価還元原価法」と「売価還元低価法」があり、会社の方針によりどちらかを選択します。
3.評価額を求める
原価率を用いて決算日時点の棚卸資産の評価額を求めます。
<評価額の計算式>
評価額=販売価額×原価率
<例>
販売価額:200,000円
原価率:80%
評価額:160,000円(200,000円 × 0.80)
4.税務上は事前の届出が必要
法人税の計算において売価還元法を適用する場合は、税務署に対して事前の届出が必要です。
法人税法上の棚卸資産の評価方法は、届出をしない場合は法定の評価方法である最終仕入原価法が適用されます。
会社の方針として売価還元法を適用したい場合には、「棚卸資産の評価方法の届出書」を税務署に提出することを忘れないようにしましょう。
売価還元法についてのまとめ
売価還元法の特徴は棚卸資産をグループ分けして、算出した原価率によって評価を行うことです。評価の方法は複数あるため、業種などによって適切な方法を選択する必要があります。
ぜひこの記事を参考に、他の評価方法との違いも含めて業種にあった特徴を理解しておきましょう。
【書式のテンプレートをお探しなら】

