嘱託社員とは? 他の社員との違いを詳しく解説
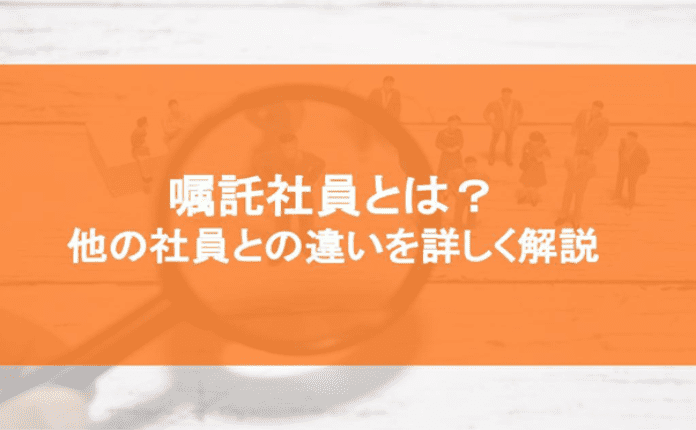
嘱託社員は、主に定年後に企業と一定期間の再雇用の契約をして働いている社員のことです。契約社員の一種ですが、正社員や派遣社員とはどのような違いがあるのでしょうか。
今回は、高齢化社会で増加していく嘱託社員のメリットや他の社員との違いについて、詳しく解説します。経験豊富な人材である定年退職者を雇用する際の参考にしてください。

嘱託社員(嘱託職員)とは?
「嘱託」は「しょくたく」が正しい読み方です。まずは、嘱託社員とは何かについて解説します。
嘱託社員とは
「嘱託」とは、正式な雇用契約や任命によらずに特定の仕事を任せることです。嘱託社員は、正社員とは異なる形態の雇用契約を組織と結び、特定の業務に従事する社員のことを指します。
厚生労働省が隔年で実施する「就業形態の多様化に関する総合実態調査」では7,499事業所のうち19.7%が「嘱託社員がいる」と回答しています。
参考:「就業形態別労働者がいる事業所の割合(令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査)」|厚生労働省
嘱託社員の定義
法律に嘱託社員の明確な定義はありません。ただ、厚生労働省の「就業形態の多様化に関する総合実態調査」では、嘱託社員を「定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する者」としています。
- 有期期間の雇用契約である
- 特定の業務に従事する(部署異動がない)
- 定年退職後再雇用された
以上の条件全てに該当する人が、嘱託社員と呼ばれることが多いです。大きな括りでは、非正規労働者の有期雇用契約労働者となります。
嘱託社員を雇用するメリット
ここからは、嘱託社員を雇用するメリットを解説します。
経験豊富な社員の知見と経験を、即時活用できる
高年齢者の雇用に関する調査では、定年退職後に嘱託社員として再雇用される方の8割超が退職前と同じ仕事をしているという結果が報告されています。
この結果から、企業は定年退職した社員に対し、培ってきた業務知識を引き続き活かしてほしいと考えていると言えるでしょう。会社の業務内容や専門的スキルを持つ人材を、採用コストを最小限に即時活用できるのは大きなメリットです。
参考:「高年齢者の雇用に関する調査(企業調査)」|独立行政法人労働政策研究・研修機構
業務委託の嘱託社員として、就業機会が確保できる
2021年4月の「高年齢者雇用安定法」の改正により、65歳までの雇用確保が義務となり、70歳までの就業確保努力義務が追加されました。
就業確保については直接雇用だけではなく、業務委託契約の締結も認められています。65歳以上の嘱託社員は雇用契約ではなく、業務委託契約を結ぶという活用方法が増えてくるでしょう。
業務委託は雇用契約と異なり、仕事の進め方・方法を個人に全て委ねるというものです。雇用ではないので勤怠管理もありませんし、賃金ではなく報酬として対価を支払います。社会保険に加入させなければならないということもありませんので、業務委託によって会社の福利厚生費が増えるということもありません。
働き方に多様性が生まれる
嘱託社員は、正社員と同じ労働日数・労働時間である必要はありません。労働日数・労働時間は社会保険や雇用保険の加入要件に関わってきます。そのため、再雇用の嘱託社員では労働日数・労働時間を減少させ、雇用保険のみ加入しているというケースも多く見られます。労働者からの「扶養内で働きたい」といった要望に応えることも可能です。
人材確保がしやすい
内閣府の「高齢者の経済生活に関する調査」によると、60歳以上の高齢者の20.6%が「働けるうちはいつまでも」収入の伴う仕事をしたいと回答しました。少子高齢化社会では、新卒の労働者より定年退職後の働く意欲のある高齢者を採用する方が時間・費用コストともに節約できることでしょう。
嘱託社員を雇用する際の注意点
ここからは、嘱託社員を雇用する際の注意点について解説します。
不合理な待遇差は法律違反
不合理な待遇差は、パートタイム・有期雇用労働法違反として是正を求められる場合があります。
たとえば、以下のような待遇の差が違反事例に該当します。
- 正社員と同じ労働条件で働いているが、有期雇用社員に繁忙期手当が支給されない
- 正社員と異なる職務内容で働く有期雇用社員に、夏季休暇・冬期休暇が付与されない
嘱託社員の基本給や各種手当、休暇などの待遇に正社員と比較して差を設ける場合、職務の内容や責任の重さから不合理な差となっていないか留意しましょう。
嘱託社員のモチベーション維持が難しい
嘱託社員の定年前後での仕事の変化について、約4割の企業が「定年前と同じ仕事であるが、責任の重さが軽くなる」と回答しています。
責任の比重が賃金や手当・待遇に反映されることもあり、定年前に比べて仕事は楽になったが給与も減ったと、仕事へのモチベーションが低下する方もいます。定年前に再雇用制度や嘱託社員の労働条件についての説明を入念に行い、対象者が安心して勤務できるようにしましょう。
参考:「高年齢者の雇用に関する調査(企業調査)」|独立行政法人労働政策研究・研修機構
5年超えたら無期転換ルール
嘱託社員は大きな括りでは、有期雇用契約の社員です。有期雇用契約を結んだ社員は、契約を更新して雇用期間が通算5年を超えた場合、本人の申し込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されます。
この無期転換ルールは、有期雇用契約の社員である嘱託社員にも適用されます。ただし特例として、適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた場合には、定年後引き続き雇用される期間は無期転換の申込権が発生しないという制度(有期特措法)もあります。
嘱託社員と他社員の違い
同じ社員でも、嘱託社員は契約社員や正社員、派遣社員とは明確な違いがあります。それぞれの社員との違いについて解説します。
嘱託社員と契約社員の違いとは
嘱託社員と契約社員には、以下のような違いがあります。
- 嘱託社員は教育コストが節約できることが多い
- 嘱託社員は正社員転換制度の対象外にできる
- 嘱託社員には無期転換ルールの特例がある
嘱託社員は、有期雇用の契約社員の一種です。非正規労働者という点は共通していますが、再雇用者が多い嘱託社員は、企業の業務内容から風土まで熟知しています。よって、初期の教育コストがかからない点が契約社員とは異なります。
また、契約社員などの非正規社員は面接試験などによって正社員へ転換させることができます。この正社員転換制度は、対象者要件の書き方によっては嘱託社員を対象外にすることが可能です。
さらに、定年後の再雇用嘱託社員については特例として、無期転換ルールを免れる有期特措法があります。契約社員のように、雇用期間が通算5年を超えた場合でも無期労働契約に移行する必要はありません。
嘱託社員と正社員の違いとは
嘱託社員と正社員の違いは以下のとおりです。
- 雇用期間の定めの有無
- 特定の業務に従事すること
- 勤務日数・勤務時間
まず、嘱託社員と正社員は、雇用期間が決まっているかどうかが異なります。正社員は雇用契約期間の定めがない無期雇用契約ですが、嘱託社員は1年や3年などの任期や期間が定められた有期雇用契約です。
また、正社員は部署異動によって従事する業務が変わることがありますが、嘱託社員は特定の業務にのみ従事することがほとんどです。
勤務日数や勤務時間にも違いがあります。正社員は週5日週40時間のフルタイムで勤務される方が多いですが、嘱託社員は業務の内容や本人の希望を踏まえて柔軟に決めることが可能です。
嘱託社員と派遣社員の違いとは
嘱託社員と派遣社員には、以下のような違いがあります。
- 雇用契約を結んでいる企業
- 3年の期間制限
嘱託社員と派遣社員は、雇用契約を結ぶ対象が異なります。嘱託社員は、勤務する企業と有期雇用契約を結びます。一方、派遣社員は派遣元の企業と有期もしくは無期雇用契約を結んだうえで期間を定めて企業に派遣されます。
派遣社員にとって、派遣先企業は業務の指示命令を受け就業する場所に過ぎず、雇用契約は派遣元企業にあります。社会保険・雇用保険の加入や、健康診断の義務も派遣元企業にあります。
また、派遣社員は同一の組織単位(いわゆる「〇〇課」など)に対し、3年の期間制限があります。嘱託社員の場合は5年を超えた場合の無期転換ルールがありますが、派遣社員のような3年の期間制限はありません。60歳以上の派遣労働者の場合も、この3年の期間制限は対象外となります。
嘱託についてのまとめ
嘱託社員は正社員とは異なる雇用契約を企業と結び、特定の業務に従事する社員のことです。主に定年を迎えた労働者が企業と再雇用の契約を結んで働く契約社員の一種であり、「高年齢者雇用安定法」の改正により、今後増加していくことが予想されます。
企業にとっては、経験豊富な人材をコストを抑えて採用できることが大きなメリットです。ただ、正社員とは雇用形態が異なるため、嘱託社員の取り扱いを十分に理解したうえで導入するようにしてください。


