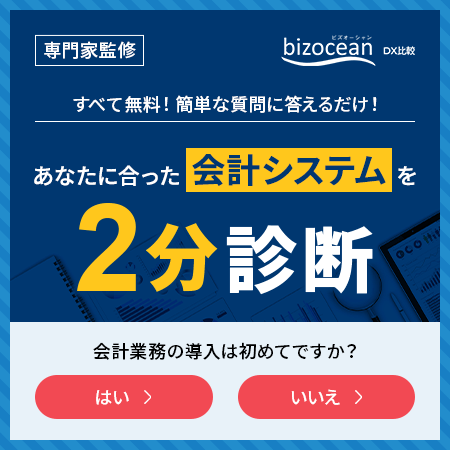残業60時間は違法? 残業代の計算方法や対処方法を解説

残業が月60時間を超える場合、労働者には50%増しの割増賃金が法律によって保証されています。
2023年4月からは、中小企業についてもこの規則が適用されており、労働者の残業代が増加している企業も多いでしょう。
ただし、月60時間以上の残業は、割増賃金を支払えば認められるとは限りません。場合によっては違法になるため、残業規定や違法性について理解しておく必要があります。
この記事では、残業60時間の違法性や残業代の計算方法、対処方法を解説します。

残業60時間は違法?
まずは、残業60時間超えの違法性について解説します。
違法となる場合
労働基準法では、1日8時間・週40時間の法定労働時間が定められており、これを超える残業は認められていません。
ただし、決算や繁忙期といった特別な事情によって残業が必要になる場合は「36(サブロク)協定」の締結によって従業員に残業させることが可能になります。
36協定とは、労働基準法36条に規定されている残業(時間外労働)を行うために必要な手続きのことをいい、従業員の代表と経営者・会社代表などの使用者が時間外労働について結ぶ協定のことです。
36協定を締結しないで行った残業(時間外労働)は1分であっても違法となります。
36協定が締結されていたとしても、残業の限度時間は原則として「45時間(1年単位変形労働時間制を採用している場合は「42時間」。以下同じ。)」と定められています。
しかし、特例規定である「特別条項付き36協定」の場合は、1年間に最大6月までの上限付きで、超過可能時間を45時間以上(1月当たり100時間未満、かつ、2~6か月のそれぞれの1月当たりの平均で80時間以下であること)とすることも可能です。
つまり、特別条項付き36協定が締結されており、かつ年6回までの臨時的な業務に従事する場合であれば、残業時間が60時間を超えても違法にならないということです。
なお、特別条項付き36協定は「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる場合」に限り締結することができるため、特別条項付き36協定をすぐに締結することはできません。
罰則
36協定を締結していない状態で従業員を残業させると、労働基準法違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があります(労働基準法119条1号、36条6項2号)。
残業時間の長さに関わらず、従業員を残業させる場合は36協定の締結が必要になるため、十分注意しましょう。
残業時間が60時間を超えても違法にならないケースは、特別条項付き36協定が締結されており、かつ年6回までの臨時的な業務に従事する場合のみです。
臨時的な業務が年7回以上になるなど、ルールを逸脱した場合は罰則の対象となります。
罰則とならない例外もある
「特別条項付き36協定」が締結されている場合は、1年間に最大6回までの上限付きで、超過可能時間を45時間以上とすることができます。
この場合、残業60時間超えは違法になりませんが、特別条項が付いていた場合も時間外労働に上限が設けられているので注意が必要です。
なお「残業」は法的な用語ではなく、労働基準法では「時間外労働」と呼びます。
具体的には、時間外労働を次の範囲内に収める必要があります。
- 年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 過去6か月間の時間外労働と休日労働の合計が1月あたり平均80時間以内
時間外労働と36協定
ここでは、時間外労働と36協定について詳しく解説します。
法定外残業と法定内残業
残業時間には「法定外残業」と「法定内残業」があります。
法定外残業とは、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える残業のことです。
一方で、法定内残業は、法定労働時間内の残業を指します。
例えば、所定労働時間が7時間の場合、1日1時間の残業であれば法定労働時間である1日8時間を超えないため、「法定内残業」となります。
36協定と残業時間の原則
36協定とは「時間外労働及び休日労働に関する労使協定」のことで、労働基準法第36条に定められています。
従業員の代表と経営者・会社代表などの使用者が36協定を締結し、労働基準監督署に届け出たうえで、就業規則にその旨を記載します。それによって、法定労働時間を超えて従業員を残業させることが可能になります。
ただし、36協定の締結によって認められている時間外労働は月45時間、年360時間が限度で、休日労働は別途管理が必要です。
また、時間外労働に対しては、基本給に25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
残業60時間の手取りはいくら?計算方法も紹介
残業60時間の場合、手取りはいくらになるのでしょうか。
ここでは、従業員の視点で計算方法を紹介します。
残業の計算方法
まずは、残業代の基本的な計算方法を押さえておきましょう。
残業代は「基礎時給 × 割増率 × 残業時間」で求められます。
基礎時給
基礎時給とは、「基礎賃金 ÷ 所定労働時間」によって求められる時給のことです。
時給制の場合は、すでに1時間あたりの賃金が明確になっているため、基礎時給を計算によって求める必要はありません。
基礎時給を求めるために必要な「基礎賃金」は、残業代を除く普段の給料から、労働基準法で定められた次の手当とボーナスを差し引いたものです。
- 通勤手当
- 家族手当
- 住宅手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 1か月を超える期間ごとに支払われるボーナスなどの賃金
- 臨時に支払われた賃金
地域手当・役職手当・資格手当など、上記以外の手当は基礎賃金に含まれます。
割増率
時間外労働の割増賃金率は、残業区分に応じて次のように定められています。
|
割増賃金の種類 |
割増率 |
|
時間外労働のうち月60時間までの部分 |
25%以上 |
|
時間外労働のうち月60時間を超える部分 |
50%以上 |
|
休日労働(法定休日の労働) |
35%以上 |
|
深夜労働(22:00~翌朝5:00までの労働) |
25%以上 |
条件が重複する場合は、表に記載されている割増率以上で賃金を支払う必要があります。
例えば「休日労働 + 深夜労働」の場合「休日労働35%以上 + 深夜労働25%以上」になるため、割増率は60%以上となります。
残業時間
残業代の計算に用いる「残業時間」とは、企業ごとに定められた所定労働時間を超えて従業員が働いた時間のことです。
労働基準法で用いられる「時間外労働」とは意味が異なるので注意しましょう。
例えば、所定労働時間が「1日7時間・週35時間」と定められている企業で1日1時間残業すると、法定労働時間である1日8時間以内に収まることになります。
しかし、所定労働時間を過ぎた分は「法定内残業」となり、残業代が発生します。
土日祝日が休みの企業で休日出勤を行い、代休を取得しない場合も、残業代の支払いが必要です。
残業代の計算例
時間外労働のうち、月60時間までの部分の割増率は25%以上ですが、月の残業時間が60時間を超えた場合は、超えた分について50%以上の割増賃金の支払いが必要です。
具体的な計算例を見ていきましょう。
<条件>
1時間当たりの基礎賃金:1,200円
時間外労働:70時間
(深夜労働や休日労働はないものとする)
- 60時間までの残業代:1,200 × 1.25 × 60 = 90,000円
- 60時間を超えた10時間分の残業代:1,200 × 1.50 × 10 = 18,000円
この例では、90,000円 + 18,000円 = 108,000円が当月の残業代となります。
残業60時間の影響と対処法
残業が60時間を超えると、従業員の心身に大きな負担がかかります。具体的なリスクと改善するための対処法を見ていきましょう。
過度な残業が続くと身体的・精神的に危険
月80時間以上の残業を「過労死ライン」といい、過労死の危険が高まるとされています。
月60時間超えの残業が続くと過労死ラインに近づいていくため、大きなリスクを伴うことになります。
休めないことによる精神的な負担も増えていくため、「月80時間以上を超えていなければ問題ない」と考えることは非常に危険です。
従業員と企業の双方が過度な残業が続くことによる危険性を理解することが、長時間労働の是正に向けた第一歩といえるでしょう。
専門家への相談も検討したい
従業員は、自身の健康と労働者の権利を保護するために、専門家への相談を検討することが大切です。
月60時間を超える残業は、労働基準法が定める上限を超える可能性があります。状況が改善されない場合は違法性が疑われるため、労働問題に強い弁護士や労働基準監督署へ申告することをおすすめします。
タイムカードなど、労働実態を示す証拠になるものも残しておきましょう。
https://katsuura-law.com/zangyo-dai
残業60時間のまとめ
月60時間を超える残業が続くと、過労死ラインに近づいていきます。企業は、従業員の労働時間を正しく把握し、問題に気付いた時点で速やかに勤務体制を見直すことが大切です。
一方の従業員側は、違法性が疑われる場合に労働基準監督署へ申告するなど、専門家への相談を検討することが重要です。
また、残業に対しては、ルールに沿って適切な賃金が支払われなければなりません。2023年4月1日以降、中小企業では、60時間超の残業には50%以上の割増率が適用されるため、未払いがあれば弁護士への相談もおすすめです。
未払いの可能性がある場合は、まずは本記事を参考にしながら自身の残業代を計算してみましょう。