ストレスチェックの高ストレス者とは? 企業の適切な対応方法を解説
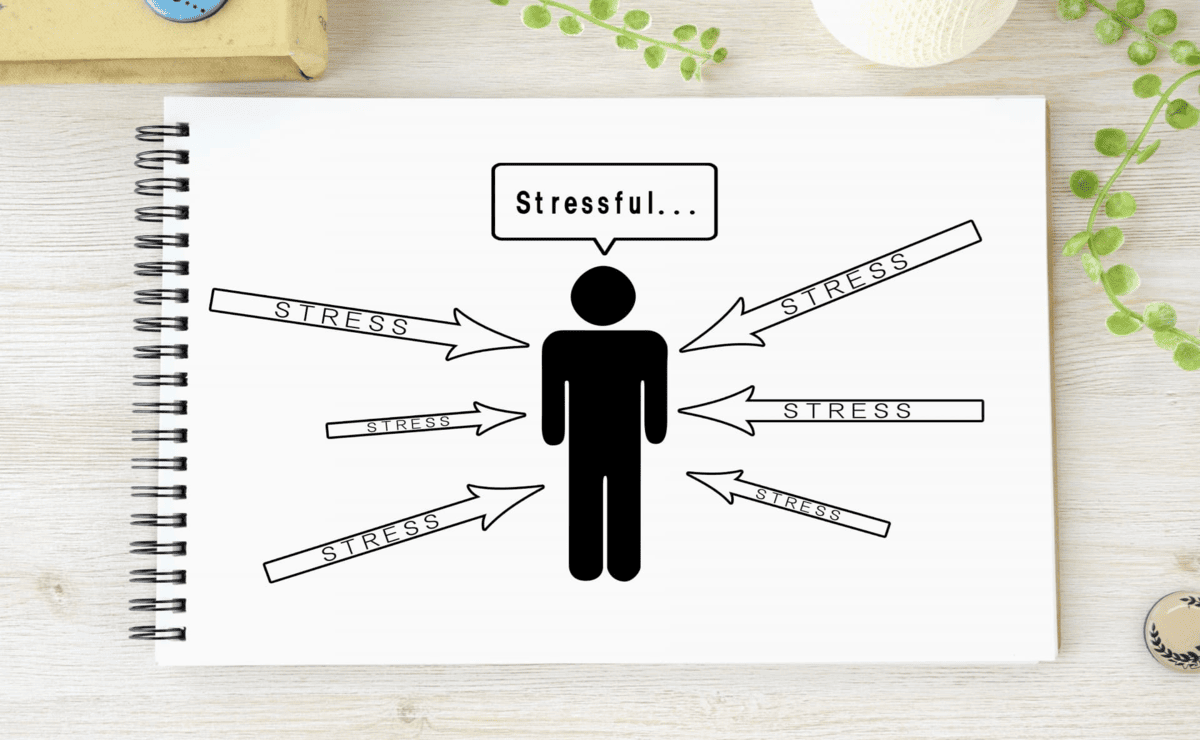
ストレスチェックは、従業員が自身のストレスに気づくために企業内で行う検査のことです。チェックで高ストレス者と判断された際、セルフケアを行ったり医師の面接指導を受けたりする場合があります。
本記事では、そのような状況において高ストレス者となる判断基準や特徴について解説していきます。
高ストレス者と判断された場合の企業の適切な対応についても紹介するので、チェック義務化の対象となった担当者は参考にしてください。

ストレスチェックにおける高ストレス者とは
高ストレス者とは、ストレスチェックを行った際に心身のストレスにおける自覚症状が高い、またはストレスの原因や周囲のサポートが著しく悪い状態の労働者のことです。
具体的には、チェックの結果が以下のようになると高ストレス者と判定されます。
- 「心身のストレス反応」の数値が高い
- 「心身のストレス反応」の評価点数の合計が一定以上、かつ「仕事のストレス要因」および「周囲のサポート」の評価点数の合計が著しく高い
ただし上記の基準に当てはまらない場合でも、医師や保健師の判断で高ストレス者と判断されることもあります。
高ストレス者の判定基準
高ストレス者の判定基準は、以下のいずれかに該当する基準を指します。
- 事業者が衛生委員会での調査審議や実施者(医師や保健師など)の意見をもとに決定する基準
- 厚生労働省の「職業性ストレスチェック簡易調査票」に基づく項目を使用した基準
事業者が独自の判定基準を設ける場合は、衛生委員会での調査審議や実施者の意見を参考にして各事業場の特性を踏まえて決定する必要があります。
厚生労働省の「職業性ストレスチェック簡易調査票」を使用する場合は、以下3つの項目の評価点数に基づいて高ストレス者を判定します。
- 心身のストレス反応
- 仕事のストレス要因
- 周囲のサポート
高ストレス者の割合と特徴
高ストレス者の割合は事業場によって異なりますが、多くの事業場で5〜20%程度存在していることが明らかになっています。企業ごとに一定の割合で存在しているのです。
高ストレス者は、職場の人間関係やサポート体制の不足、仕事の質的・量的負荷の高さなどが原因となっていることが多くなっています。
【関連記事はこちら】
ストレスチェックとは? 目的や実施方法、従事者や事後の対応をご紹介ストレスチェックの高ストレス者に対する企業の適切な対応方法
企業を安定的に運営するために、高ストレス者に対しての適切な対応を知っておくことは重要です。
ここでは、以下の高ストレス者に対する企業の適切な対応方法について解説していきます。
- 面接指導を受けやすい環境を整える
- 職場環境の改善に取り組む
- 高ストレス者のプライバシーに配慮する
- 医師の意見を踏まえて措置を講じる
面接指導を受けやすい環境を整える
企業はプライバシーに配慮した面接指導の実施体制を整備することで、高ストレス者が面接指導を受けやすい環境を整える必要があります。
面接指導の日時や場所の柔軟な設定、Web面接の選択肢を用意するなど、高ストレス者の都合に合わせた対応が求められるのです。
また、面接指導の目的や重要性を従業員に周知し、高ストレス者が抵抗感なく面接指導を申し出られるよう啓発活動を行うことも重要でしょう。
職場環境の改善に取り組む
企業は高ストレス者が所属する部署の職場環境改善やストレスに向けた組織的な対策に取り組むことが期待されています。
高ストレス者が多い部署では、業務の見直しや人員配置の適正化、コミュニケーションの活性化といった職場環境の改善が必要です。
また、ストレスチェックの集団分析結果を活用し、組織全体のストレス要因を特定して対策を講じましょう。
【関連記事はこちら】
企業が従業員の健康管理に取り組むべき理由とは? 効果的な施策も紹介!高ストレス者のプライバシーに配慮する
企業には高ストレス者に対する不当な扱いを防止するために、面接指導の結果を適切に管理しプライバシーに配慮した行動が求められます。
特に面接指導の結果に関しては、高ストレス者本人の同意なく事業者に提供することはできません。
このような状況下においては高ストレス者の情報を取り扱う担当者を限定し、守秘義務を徹底することで高ストレス者のプライバシー保護に対して積極的に努めましょう。
医師の意見を踏まえて措置を講じる
企業は医師の意見を参考にしつつ、高ストレス者に対する労働時間の調整や業務内容の変更などの就業上の措置を講じてください。
例えば、高ストレス者の業務量軽減、配置転換など医師の指導をもとにストレス要因を取り除くための対策を実施しましょう。
ただし就業上の措置を講じる際は、高ストレス者本人の意向を尊重して不利益な取り扱いにならないよう注意が必要です。
ストレスチェックの高ストレス者に対する医師の面接指導
ストレスチェックにおける高ストレス者に対しては、医師による面接指導が重要な役割を果たします。
ここでは、高ストレス者に向けた面接指導の目的と重要性、実施プロセスについて詳しく見ていきましょう。
面接指導の目的と重要性
面接指導の目的は、脳血管疾患や虚血性心疾患等の発症リスクが長時間労働をしている者との関連性が強いという医学的知見を踏まえたうえで、長時間労働等による高ストレス者におけるメンタルの不調を未然に防止し、適切なケアにつなげることです。
高ストレス者は放置するとメンタルの不調を発症してしまうリスクが高いため、早期の面接指導が必須です。面接指導を通じて高ストレス者のストレス要因や状況を特定し、適切な対処方法を見出しましょう。
また、医師側は高ストレス者に指導を行うだけでなく、事業者が自ら就業上の措置を適切に講じられるよう意見を述べることも重要です。
面接指導の実施プロセス
ストレスチェックの制度上、企業が対応するためには高ストレス者本人からの直接面接指導の申し出が必要です。
本人より申し出を受けてから1か月以内に面接指導を実施し、医師が勤務状況や心身の状態を確認しましょう。
面接指導の実施に当たっては、高ストレス者のプライバシーに配慮して職場の上司や同僚に知られないよう注意しなければなりません。
面接指導の結果は高ストレス者本人の同意なく事業者に提供できませんが、医師の判断で必要な情報を事業者に伝えることができます。
ストレスチェックの高ストレス者を放置するリスクと企業の責任
ストレスチェックにおける高ストレス者を放置することは、従業員と企業の両方にとって大きなリスクとなります。
ここでは、高ストレス者を放置した場合のそれぞれのリスクと、企業の安全配慮義務について解説していきます。
従業員へのリスク
高ストレス者を放置した場合、従業員はメンタル不調の発症や悪化、パフォーマンス低下のリスクにさらされます。
高ストレス状態の長期化は、集中力や生産性の低下だけでなく、うつ病や食欲不振、睡眠障害などになり、休職や離職につながることもあるのです。
メンタル不調は本人の生活の質が低下するだけでなく、家族や同僚など周りにも影響を与えるため、早期の対応が求められています。
企業のリスク
企業が高ストレス者を放置した場合、安全配慮義務違反による民事訴訟や労働紛争のリスクが生じます。
高ストレス者のメンタル不調が原因で生産性が低下したり、休職・離職者が増加したりすると、企業の業績に悪影響を及ぼす可能性もあります。
さらに、高ストレス者への対応を怠ると精神疾患による労災事故につながる恐れがあり、企業の社会的信用の失墜にもつながりかねないため注意しましょう。
安全配慮義務と企業の法的責任
安全配慮義務は、労働契約法第5条に基づいた従業員の心身の健康確保に対する企業の法的責任です。
企業は従業員が安全かつ健康的に働くことができるよう、労働環境を整備して健康管理を行うことが義務となっています。
もし安全配慮義務に違反し、高ストレス者を放置することで従業員のメンタル不調や健康被害が生じた場合は企業が損害賠償責任を負ってしまいます。後述するフォローとケア方法をしっかり参考にしてください。
ストレスチェックの高ストレス者へのフォローとケア
ストレスチェックによる高ストレス者への適切な対応は、面接指導後も継続的に行う必要があります。
ここでは、高ストレス者へのフォローやケアの具体的な方法について詳しく紹介していきます。
- 継続的なサポートを提供する
- 社内外の相談窓口を設置し周知する
- セルフケア支援と啓発活動を行う
継続的なサポートを提供する
企業は、面接指導後も高ストレス者に対する定期的な状況確認と必要な支援を継続的に提供する必要があります。
高ストレス者の状況に応じて産業医や保健師による面談を定期的に実施し、ストレス状態の改善を確認しつつ進めましょう。
必要に応じて、専門機関と連携し、高ストレス者に対する適切な治療やカウンセリングの提供をすることも効果的です。
ストレスチェックをこのように活かしていくために、チェック後はできる限り集団分析を行ってください。
社内外の相談窓口を設置し周知する
企業は高ストレス者が相談しやすい社内外の窓口を用意し、積極的に案内していきましょう。
社内に相談窓口を設置する場合は、高ストレス者のプライバシーに配慮して相談内容が職場の上司や同僚に知られないよう注意してください。
社外の相談窓口を活用する場合は専門性の高い相談員を配置して、高ストレス者のニーズに合った具体的なサポートを提供することが求められます。
セルフケア支援と啓発活動を行う
企業は高ストレス者のセルフケア能力向上のための情報提供や研修を実施し、啓発活動を行うべきです。
企業側がストレスマネジメントやリラクゼーション技法など、高ストレス者が自身でストレスに対処するためのスキルを身につける機会を提供しましょう。
メンタルヘルスに関する正しい知識や理解を深めるための啓発活動を行い、高ストレス者に限らず、全従業員のメンタルヘルスリテラシーの向上を図ることが重要です。
高ストレス者に適切に対応し従業員の健康を守ろう
ストレスチェック制度の効果的な運用と高ストレス者のメンタルヘルス不調の予防には、企業の適切な対応が欠かせません。
もし高ストレス者を放置してしまうと、従業員の健康リスクだけでなく、企業経営に関しても影響がもたらされるため、早期の対応が求められています。
本記事を参考に高ストレス者の定義と判断基準を理解し、セルフケアや医師による面接指導などの対策を確実に実施することが重要です。
面接指導を受けやすい環境整備、プライバシーへの配慮、就業上の措置、職場環境の改善など高ストレス者に応じた適切な対応を行うことで、従業員の心身の健康を守り、企業の生産性向上につなげていきましょう。


