ストレスチェックの対象者とは? 企業が知っておくべき範囲と条件
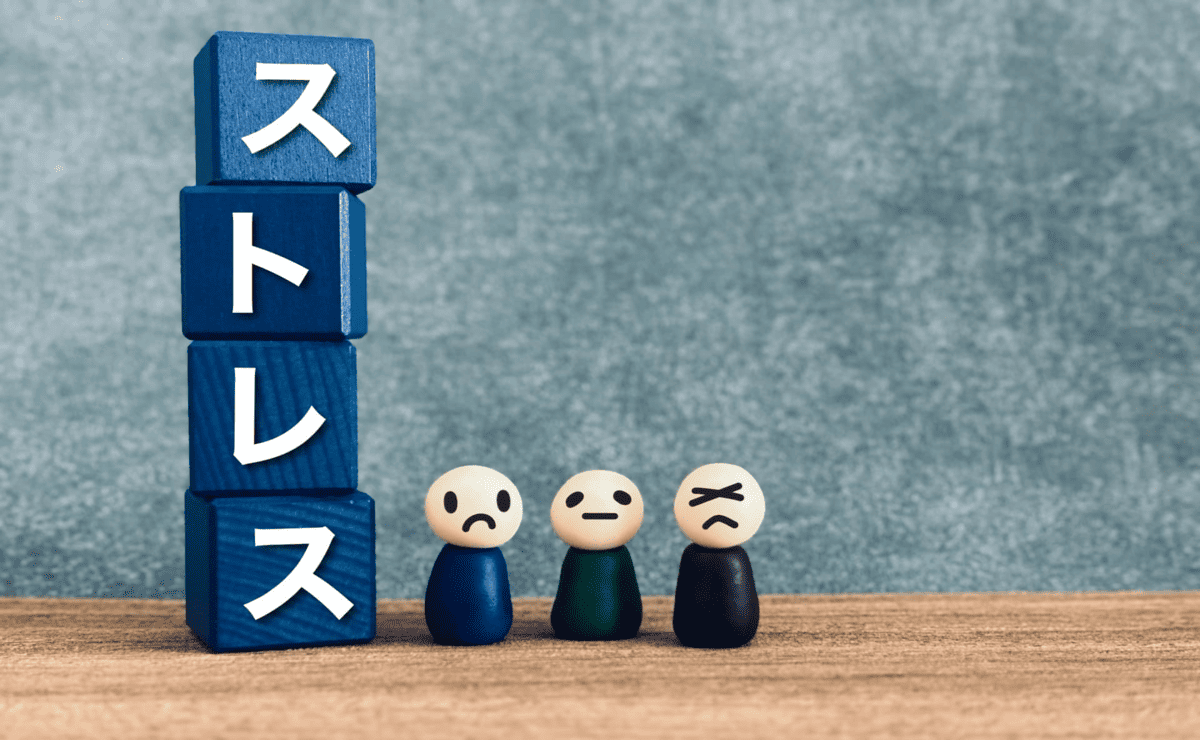
ストレスチェックは、2015年12月の労働安全衛生法改正により義務化されました。
目的は、メンタルヘルス不調による休職者の増加や、精神障害の労災認定件数の増加を背景に、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することです。
本記事ではストレスチェックの実施対象となる企業や受検対象となる労働者、受検対象外となるケース、注意点などを詳しく解説します。正確な取り組みのために参考にしてください。

ストレスチェックの実施対象となる企業
ストレスチェックの実施対象は、労働者数が50人以上の企業と定められています。対象企業の詳細と、「常時使用している労働者」の定義について詳しく見ていきましょう。
常時50人以上の労働者がいる企業が対象
労働者数が50人以上の企業はストレスチェックが義務であり、50人未満は努力義務です。常時使用する労働者の数は、正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトも含めて判断します。
また、本社と支社、支店などを合わせて50人以上となる場合も義務の対象です。
「常時使用している労働者」の定義
ストレスチェックの対象となる常時使用している労働者とは、契約期間や労働時間に関わらず継続的に雇用している労働者のことです。
期間の定めのない労働契約を締結している労働者や、1年以上の有期雇用契約を結んでいる労働者が該当します。
パートやアルバイトであっても、1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であれば常時使用する労働者に含まれます。
ストレスチェック実施の前には、常時使用する労働者の範囲を正しく理解しておきましょう。
ストレスチェックの受検対象者となる労働者
ストレスチェックの受検対象者には、一定の条件があります。ここでは受検対象者の条件と、雇用形態別の判断基準について詳しく見ていきましょう。
受検対象者の条件
ストレスチェックの受検対象者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で、期間の定めのない労働契約または1年以上の契約労働者です。
加えて、1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上である必要があります。期間の定めのない労働契約を結んでいる正社員や、1年以上の有期雇用契約を結んでいる契約社員が対象です。
なお、常時50人未満の労働者を使用する事業場については、当分の間、ストレスチェックの実施が努力義務とされています。
雇用形態別の受検対象者の判断基準
ストレスチェックの受検対象者は、正社員、契約社員、パート・アルバイトの雇用形態ごとに条件が異なるため確認が必要です。
正社員は原則として全員が受検対象となりますが、契約社員やパート・アルバイトは契約期間と所定労働時間によって対象か否かが判断されます。
派遣社員の場合は派遣元に実施義務がありますが、職場の状況を正確に把握するために派遣先で受検させることが望ましいです。
雇用形態別の受検対象者の判断基準は以下の通りです。
|
雇用形態 |
契約期間 |
所定労働時間 |
対象の可否 |
|---|---|---|---|
|
正社員(一般社員) |
期間の定めなし |
フルタイム |
対象 |
|
正社員(役員) |
期間の定めなし |
フルタイム |
対象外 |
|
契約社員 |
1年以上(更新含む) |
4分の3以上 |
対象 |
|
契約社員 |
1年以上(更新含む) |
4分の3未満 |
対象外 |
|
契約社員 |
1年未満(更新予定なし) |
4分の3以上 |
対象外 |
|
契約社員 |
1年未満(更新予定なし) |
4分の3未満 |
対象外 |
|
パート・アルバイト |
1年以上(更新含む) |
4分の3以上 |
対象 |
|
パート・アルバイト |
1年以上(更新含む) |
4分の3未満 |
対象外 |
|
パート・アルバイト |
1年未満(更新予定なし) |
4分の3以上 |
対象外 |
|
パート・アルバイト |
1年未満(更新予定なし) |
4分の3未満 |
対象外 |
ストレスチェック受検対象外となるケース
ここまで、ストレスチェックの受験対象者の要件について解説してきました。
では、受検対象外となるケースにはどのようなものがあるのでしょうか。ストレスチェックの受検対象外となるケースは以下の通りです。
- 休職中の労働者
- 海外出張者
- 派遣社員
- 出向者
ここでは上記のケースについて詳しく見ていきましょう。
休職中の労働者
病気療養、産休、育休、介護休暇等で休職中の労働者は、ストレスチェックの対象外です。
ストレスチェック実施時点で休職中の労働者は、受検義務がないため、復職後に改めてストレスチェックを受けてもらう必要があります。
ただし休職の原因がメンタルヘルス不調である場合は、主治医と相談の上、慎重に検討することが重要です。
海外出張者
海外出張者はストレスチェックの対象ですが、現地法人所属者は対象外です。日本の企業に籍を置いたまま海外で勤務している労働者は、ストレスチェックの対象となります。
一方、海外の現地法人に雇用されている労働者は、日本の労働安全衛生法の適用を受けないため受検対象にはなりません。
派遣社員
派遣社員のストレスチェックは派遣元事業者に実施義務があり、派遣先は集団分析時に含めるのが望ましいです。
派遣元が実施したストレスチェックの結果を踏まえたうえで面接指導を実施し、その面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案した情報を派遣先に提供することで、職場全体の状況を把握することができます。
また、派遣先が独自にストレスチェックを実施する場合は、派遣元との役割分担を明確にしておきましょう。
出向者
出向者のストレスチェック実施は、出向元と出向先のどちらに労働契約関係があるかで判断してください。出向先との間に労働契約関係がある場合は、出向先で受検することになります。
ただし出向元と出向先の双方に雇用関係がある場合は、勤務実態を踏まえてどちらでストレスチェックを実施するかを判断しましょう。
ストレスチェック対象者における注意点
ストレスチェックを実施する時には、いくつかの注意点を抑えておかなければいけません。以下では労働者の受検義務と、受検率向上のための工夫について詳しく見ていきましょう。
労働者には受検義務がない
労働者のストレスチェック受検は義務ではないため、企業は強制することができません。
ストレスチェックを受けるかどうかは労働者の判断に委ねられます。受検を拒否しても不利益な取扱いをしてはならないのです。
ストレスチェックを実施する際は、ストレスチェックの目的や意義を十分に説明しましょう。労働者の理解を得ることで、高い受検率を確保することが重要です。
受検率向上のために工夫する必要がある
ストレスチェックの受検率を上げるには、その目的を丁寧に説明し、労働者の理解を得ることが重要です。
ストレスチェックが労働者自身のメンタルヘルス不調の早期発見・予防につながることや、職場環境の改善に役立つことを伝えるのが効果的でしょう。
受検しやすい環境を整えるため、実施時期や方法について労働者の意見を聞くことも有効な手段です。労働者には受検義務はないことも考えると、労働者と企業の相互理解と協力が欠かせません。
ストレスチェックを適正に実施して、職場環境の改善につなげよう
ストレスチェックは、メンタルヘルス不調の未然防止と職場環境の改善を目的とした制度です。企業は、ストレスチェックの対象者の範囲を正確に把握し、受検率向上を図りながら確実に実施することが求められます。
また、ストレスチェックの結果を有効活用することで、従業員が心身ともに健康で働きやすい職場づくりにつなげることが重要です。
ストレスチェックを通じて、メンタルヘルス不調の早期発見と予防、職場のストレス要因の特定と改善を進めてください。働きがいのある職場環境の実現を目指しましょう。


