出勤簿は手書きでもOK? 法律上の要件と正しい書き方・管理方法を解説
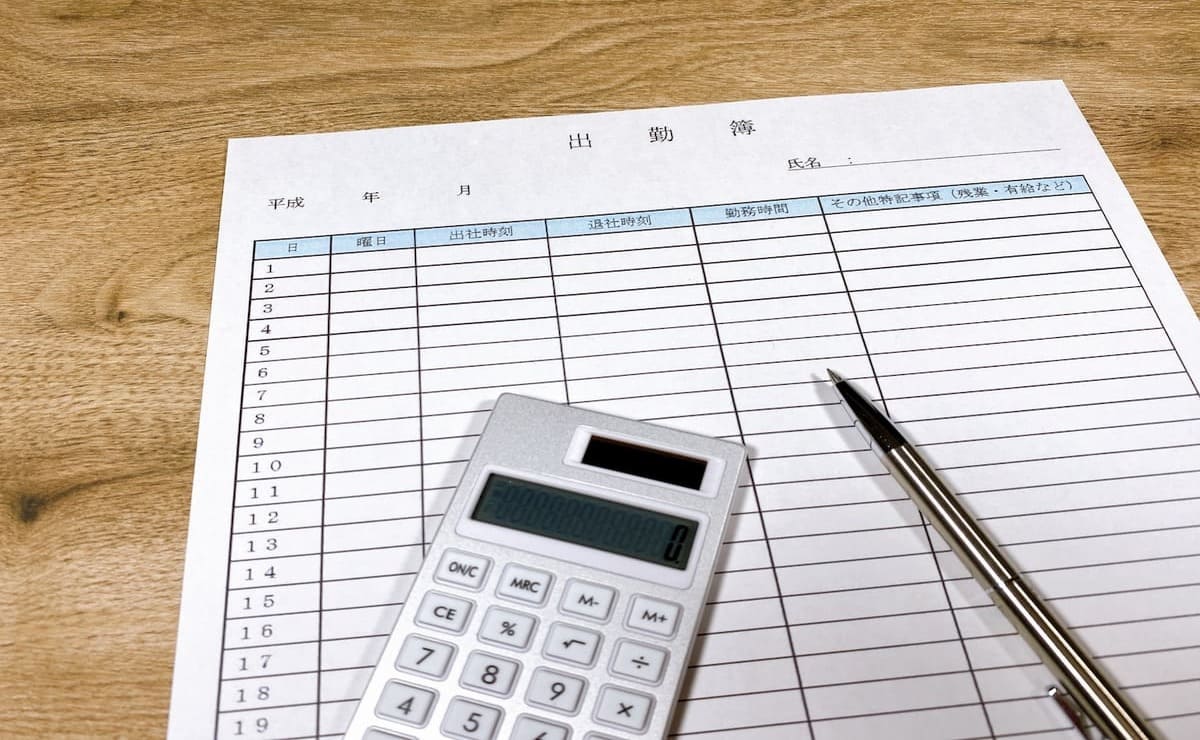
デジタル化が進む現代でも、多くの中小企業では手書きの出勤簿が使われています。しかし、「手書きの出勤簿は法的に問題ないのか」「どのような記載が必要なのか」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、手書きの出勤簿の法的な位置付けから、正しい書き方、管理上の注意点までを詳しく解説します。

【この記事のポイント】
- 出勤簿は手書きでも法的に問題なく、労働時間の正確な記録が求められる。
- 出勤簿には、始業・終業時刻、休憩時間、時間外労働の有無などを客観的に記録する必要がある。
- 出勤簿は法改正により原則5年間の保存が必要だが、当面は3年間でも差し支えないとされている。
出勤簿は手書きでも法律上問題ない?
労働基準法の改正により、使用者には労働時間の客観的な把握が義務付けられています。この要件を満たすためには、必ずしもデジタルシステムが必要なわけではありません。
ここでは、手書きの出勤簿の法的な位置づけと、客観的な記録として認められるための要件を詳しく解説します。
「客観的な記録」と認められれば、手書きでも問題ない
労働基準法では、労働者の健康確保や過重労働の防止を目的として、労働時間の客観的な把握が義務付けられています。2019年4月施行の働き方改革関連法により、この義務はより明確になり、管理監督者も含むすべての労働者が対象になりました。
手書きの出勤簿であっても、適切な運用方法を守れば、法的に「客観的な記録」として認められます。ただし、タイムカードやICカード、PCログなどの機械的な記録と比較して信頼性が劣る可能性があるため、運用には注意が必要です。
手書きでも「客観的な記録」と認められる要件
手書きの出勤簿を合法的に運用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 労働者本人が、毎日の始業・終業時刻をその都度記入すること
- 管理者が後からまとめて記入したり、記憶に頼った記録はNG
- 管理者が記入内容を定期的に確認し、署名や押印で承認を行うこと
- 実際の労働時間と記録に乖離がないか、定期的に検証する仕組みを整備すること
これらを守らない場合、「客観的な記録」として認められず、労働基準法違反に問われる可能性もあります。
自己申告制に関するガイドライン
手書きの出勤簿の運用は自己申告制に該当するため、厚生労働省が定める「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に従う必要があります。このガイドラインでは、次のような対応が求められています。
- 労働者に対して、正確な労働時間の記録・申告の重要性を周知する
- 必要に応じて実態調査を行い、申告内容との乖離を確認する
- 乖離がある場合は原因を調査し、記録の修正や業務改善などの是正措置を行う
自己申告を正しく機能させるためには、形式だけでなく、実態との整合性が非常に重要です。
手書きの出勤簿の正しい書き方
手書きの出勤簿を適法に運用するためには、法令で定められた項目を漏れなく記載する必要があります。
記載方法にも細かなルールがあり、これらを守らないと賃金未払いなどのトラブルにつながる恐れがあるため、注意が必要です。ここでは、手書きの出勤簿に記載すべき必須項目と、その正しい記載方法を詳しく解説します。
労働日・労働日数などの必須項目を記載する
出勤簿には、労働基準法施行規則第54条に基づき、以下の項目を記載する必要があります。
- 労働日
- 労働日数
- 始業・終業時刻
- 休憩時間
- 時間外・休日・深夜労働の時間数
これらは労働時間を正しく把握し、適正な賃金を支払うための基礎情報であり、労働基準監督署でも重点的に確認されるポイントです。
労働日は実際に勤務した日付を、労働日数は月間の合計勤務日数を記載し、有給休暇や欠勤日も明確に区別して記録します。市販のテンプレートを使用する場合でも、これらの必須項目がすべて網羅されているかを必ず確認し、不足があれば適宜追加しましょう。
始業・終業時刻を1分単位で記録する
労働時間は原則として1分単位で計算しなければならず、15分や30分単位での切り捨ては違法行為となるため注意しましょう。従業員には、実際に業務を開始した時刻と終了した時刻を「8:57」「18:03」のように1分単位で正確に記録してもらう必要があります。
「9:00」「18:00」のようなきりのよい時刻ばかりが並んでいる出勤簿は、実態を反映していない可能性が高く、労働基準監督署から指摘を受けやすくなります。遅刻や早退の時間も同様に1分単位で記録し、実労働時間に基づいて給与を計算しなければなりません。
休憩時間を正確に記入する
労働時間の途中に与えた休憩時間は、開始時刻と終了時刻を明確に記録し、実際に労働から解放された時間を正確に把握しなくてはなりません。労働基準法では、下記のとおり休憩を与えることが義務付けられています。
- 労働時間が6時間を超える場合:45分以上
- 労働時間が8時間を超える場合:1時間以上
休憩時間が正しく記録されていないと、実労働時間の算出が不正確になり、時間外労働手当の未払いなど、重大な法令違反につながる恐れがあるため注意が必要です。電話番や来客対応などで休憩が中断された場合は、その時間を労働時間として扱い、あらためて休憩を与える必要があります。
時間外労働や休日労働の時間も明記する
法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働や、法定休日に行った休日労働は、通常の労働時間とは別に、明確に記録する必要があります。これらの労働時間は25%以上の割増賃金の対象となるため、日付ごとに何時間の時間外労働を行ったかを正確に記載します。
深夜労働(22時から翌5時)に該当する時間帯も、さらに25%の割増率が加算されるため、他の時間帯と区別しての記載が望ましいでしょう。36協定で定められた時間外労働の上限を超えていないかを確認するためにも、これらの記録は極めて重要です。
手書きの出勤簿を管理するときの注意点
手書きの出勤簿は、その性質上、管理面で特に注意すべき点が多く存在するため、知識として知っておかなくてはなりません。適切な管理を怠ると、法令違反や労使トラブルにつながる可能性があるため、慎重な運用が求められます。
ここでは、手書きの出勤簿を管理するうえで特に重要な、4つの注意点を詳しく解説します。
賃金台帳への転記ミスを防ぐ
出勤簿の内容を賃金台帳へ転記する作業は、計算ミスや書き間違いなどのヒューマンエラーが発生しやすい工程です。数字の見間違いや入力ミスによって労働時間や賃金額に誤りが生じると、賃金未払いや過払いなどの深刻なトラブルに発展しかねません。
ミスを防ぐためには、転記作業にダブルチェック体制を導入することが重要です。1人目が入力した内容を、2人目が必ず確認するようにしましょう。特に時間外労働の集計や割増賃金の計算は複雑なため、エクセルなどの表計算ソフトを活用して、計算過程を可視化するとより安心です。
訂正・修正時のルールを社内で統一する
出勤簿に記入ミスがあった場合は、修正液や修正テープを使わず、誤った箇所に二重線を引き、訂正印を押して正しい時刻を記入するのが原則です。この方法により、誰がいつ修正を行ったのかが明確になり、後日の改ざん疑惑を防ぎ、記録の信頼性と透明性を担保できます。
訂正理由も併せて記載し、なぜ修正が必要だったのかを明らかにしておきましょう。この修正ルールは就業規則や勤怠管理規程に明記し、入社時研修などで全従業員に周知することが大切です。
法律で定められた保管期間を遵守する
出勤簿を含む労働関係重要書類は、労働基準法第109条により5年間(当面の間は経過措置として3年間)の保管が義務付けられています。この保管期間の起算日は、従業員ごとに最後の記載がされた日、つまり退職日や解雇日から数え始めます。
労働基準監督署の定期監督や申告監督の際には、過去3年分の出勤簿の提出を求められることがあるため、いつでも取り出せるよう、整理して保管しておきましょう。
年度ごと、部署ごとにファイリングし、インデックスを付けるなど、検索性を高める工夫も有効です。
紛失や情報漏洩のリスクに備える
紙媒体である手書きの出勤簿は、紛失、盗難、火災、水害などの物理的リスクに常にさらされているため、厳重な保管体制が不可欠です。施錠可能なキャビネットや耐火金庫での保管を基本とし、閲覧権限のない従業員が見られないようにアクセス制限も設けましょう。
出勤簿には氏名、勤務時間などの個人情報が含まれるため、情報漏洩は企業の信用失墜につながる重大な問題となります。万が一に備え、定期的にスキャンして電子化し、パスワード付きファイルでバックアップ保管することも有効な対策です。
出勤簿を手書きで作成するメリット
デジタル化が進む現代でも、手書きの出勤簿には一定のメリットが存在します。特に小規模事業者や特定の業種では、手書きならではの利点を活かしている点が特徴的です。
ここでは、手書きの出勤簿に関する、3つの主要なメリットを詳しく解説します。
導入コストをかけずに勤怠管理を始められる
手書きの出勤簿は、市販の様式を購入するか、インターネットで無料配布されているテンプレートを使用すれば、ほぼ費用をかけずに導入できます。勤怠管理システムの導入には初期費用で数十万円、月額利用料で数万円かかることも珍しくないため、資金に余裕のない企業にとっては大きな負担となります。
手書きの出勤簿なら、筆記用具と紙さえあれば即座に運用を開始でき、システムの保守費用や更新費用などのランニングコストも一切発生しません。特に従業員数が10名以下の小規模事業者や、設立間もないスタートアップ企業にとって、この低コストは魅力的な選択肢となるでしょう。
IT機器が苦手な従業員でも運用できる
手書きでの記入は誰もが慣れ親しんだ方法であり、パソコンやスマートフォンの操作が苦手な従業員でも、抵抗なく使うことができます。高齢の従業員が多い職場や、日常的にIT機器を使用しない建設現場、農業、介護施設などでは、この点が大きなメリットです。
複雑なシステムの操作研修や、パスワード管理、ログイントラブルなどの問題も発生せず、全従業員が即座に勤怠記録を開始できます。IT機器の故障やシステムダウンによって打刻ができないなどのトラブルもなく、安定した運用が可能です。
複雑な設定なしで、直感的に使用できる
手書きの出勤簿は、シフト制、フレックスタイム制、変形労働時間制など、どのような勤務形態でも特別な設定なしで対応できる柔軟性があります。急な残業や休日出勤、有給休暇の取得なども、その都度記載するだけで済み、事前のシステム設定や承認フローの構築は不要です。
勤怠管理システムでは、従業員ごとの所属部署、雇用形態、勤務パターンなどを事前に設定する必要があり、この作業だけで数日かかることもあります。システムの導入やメンテナンスを担当する情報システム部門がない中小企業でも、手書きなら、総務担当者だけで十分に管理できるのが利点です。
出勤簿を手書きで作成するデメリット
手書きの出勤簿には、導入が手軽にできる利点がある一方で、運用面では多くの課題を抱えています。これらのデメリットは、企業の成長とともに顕在化し、業務効率や法令遵守の観点から深刻な問題となる可能性があるので、注意が必要です。
ここでは、手書きの出勤簿に関する、4つの主要なデメリットを詳しく解説します。
集計や給与計算に多くの時間を要する
手書きの出勤簿を基に労働時間を集計し、給与を計算するには、すべてを人の手で行わなければならず、大きな時間と労力がかかります。
例えば、従業員が10名規模の企業でも、月末の勤怠集計に1日がかりになるケースは少なくありません。従業員数が増えるほど、その作業量は指数関数的に増加していきます。
時間外労働の割増率計算、深夜労働の判定、有給休暇の残日数管理など、複雑な計算を電卓で行うため、計算ミスのリスクも高くなります。給与計算の担当者は、本来なら他の重要業務に充てられる時間を、単純な集計作業に費やすことになり、生産性の低下は避けられません。
記入ミスや不正打刻のリスクを排除できない
手書きは誰でも簡単に修正や改ざんができるため、遅刻をごまかしたり、実際より多く残業時間を記載したりする、不正行為のリスクが常に存在します。同僚による代理記入も容易に行えるため、本人が出勤していないのに出勤したことにする「カラ出勤」も防ぎきれません。
字が汚くて判読できない、記入漏れ、日付の間違いなど、悪意のないミスも頻繁に発生し、正確な労働時間の把握を困難にします。これらの問題は、適正な賃金支払いを妨げるだけでなく、真面目に働いている従業員との間に不公平感を生み、職場のモラル低下につながりかねません。
リアルタイムでの労働時間を把握できない
手書きの出勤簿では、管理者が月末の締め日にならないと従業員の正確な労働時間を把握できず、日々の労務管理が後手に回ります。誰がどれくらい残業しているか、36協定の上限に近づいている従業員はいないかの重要な情報が、リアルタイムで確認できません。
また、長時間労働による健康被害のリスクが高まっている従業員を早期に発見し、業務量の調整や産業医面談につなげることが困難になります。月末になって初めて残業時間の超過が判明し、慌てて対策を講じる事態も起こりやすく、予防的な労務管理ができません。
法律で定められた保管や管理に手間がかかる
紙の出勤簿は、労働基準法で定められた5年間(当面は3年間)の保管義務があり、年々増加する書類の物理的な保管場所の確保が必要です。数百人規模の企業では、出勤簿だけで段ボール数十箱分になることもあり、専用の書庫や倉庫を借りるコストも発生します。
必要な書類を探し出す際も、年度別、部署別にファイリングされていても、該当する書類を見つけるまでに30分以上かかることは珍しくありません。火災や水害による消失リスク、経年劣化による文字の退色、虫食いなどの物理的な劣化も避けられない問題です。
手書きの出勤簿の課題を理解し、自社に最適な勤怠管理を実現しよう
手書きの出勤簿は、適切な運用を行えば法的に問題なく使用でき、労働者本人による毎日の記録と管理者の定期的な確認により、客観的な記録として認められます。
導入コストがかからず、ITが苦手な従業員でも使える手軽さは大きなメリットですが、集計の手間、不正リスク、リアルタイム管理の困難さなど、多くのデメリットも存在します。
正しい記載方法として、1分単位での時刻記録、休憩時間の明記、時間外労働の区別など、法令で定められた要件を満たすことが不可欠です。
管理面では、転記ミスの防止、統一された修正ルール、適切な保管体制の構築が、トラブル回避の鍵となります。
手書きの出勤簿は会社の規模によっては手軽に使えますが、さまざまな注意点もあるため、必要であればツールの導入も検討してみてください。

