【例文つき】日報の書き方|評価されるポイントを紹介
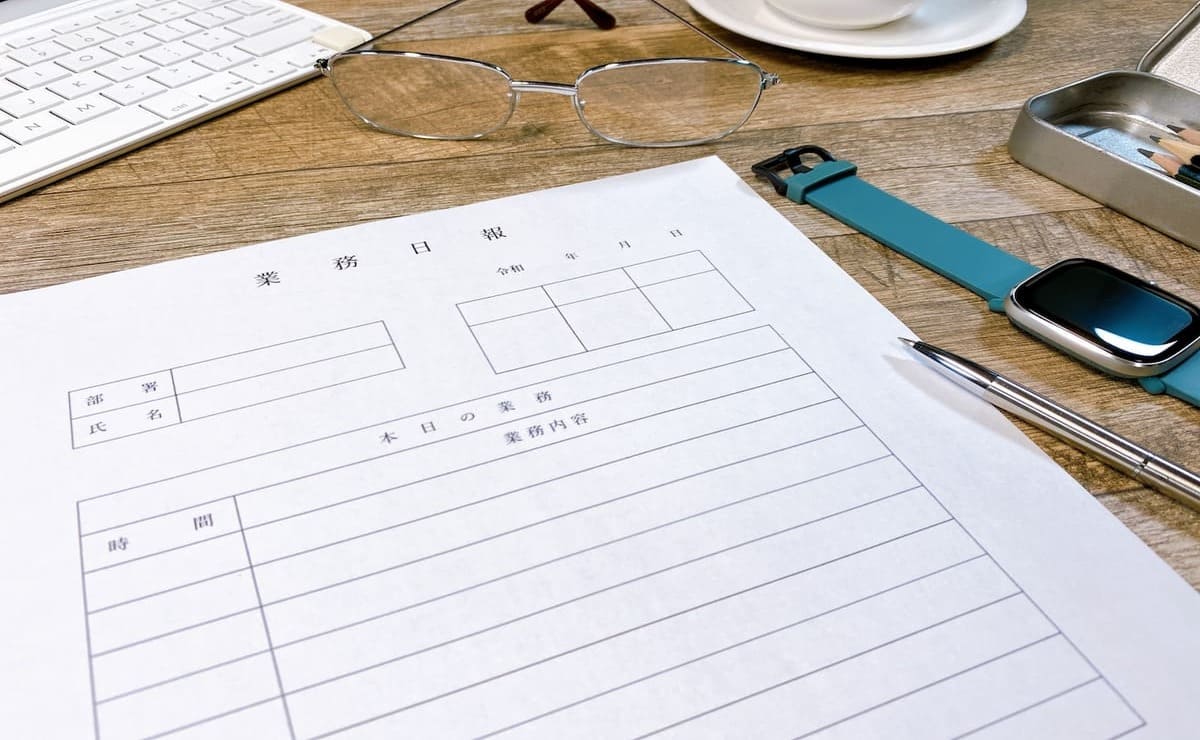
日報は単なる業務報告ではなく、自己成長と組織の生産性向上に欠かせないツールです。上司との認識のズレを防いだり、自身の課題を明確にしたりと、日々の小さな積み重ねが大きな成果につながります。しかし、何をどのように書けばよいか、悩む人も多いのではないでしょうか。
本記事では、基本的な日報の書き方から、新人・営業・テレワークなどの状況別の具体例までを詳しく解説します。明日からすぐに使える実践的な内容ですので、ぜひ参考にしてください。
【この記事のポイント】
- 日報は単なる業務報告ではなく、自己成長や組織の生産性向上に役立つ重要なツールである。
- 評価される日報を作成するには、客観的な事実と主観的な所感を明確に分けて書くことが重要である。
- 日報でネガティブな報告をする場合、その事実だけでなく、改善案や今後の対策もセットで伝えることが求められる。
基本的な日報の書き方
ここでは、日報作成の基本となる3つのポイントについて詳しく解説します。
- まずは、基本の構成要素を押さえる
- 5W1Hを意識して、業務内容を具体的に書く
- 所感・考察を加えて、自身の成長につなげる
読み手にとって分かりやすく、自分にとっても振り返りやすい日報を作成するための基礎を身につけましょう。
まずは、基本の構成要素を押さえる
日報の基本要素は「業務内容」「所感・考察」「明日の予定」です。
「業務内容」では、どのような作業を進めたのかといった、具体的な事実を記述します。「所感・考察」では、それに対する自分の考えや気づき、学びをまとめましょう。そして「明日の予定」には、翌日に予定しているタスクや対応すべき案件、目標などを明確に記載します。
大切なのは、提出先の上司やチームが今日の業務状況と成果を正確に把握できるよう、意識して書くことです。これにより、業務の進捗管理や課題の早期発見がしやすくなり、チーム全体のスムーズな連携につながります。
5W1Hを意識して、業務内容を具体的に書く
業務内容は、「いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように」の5W1Hを明確に記述します。
例えば「14時にA社を訪問し、新商品Bの件で山田部長と打ち合わせを行った」のように、状況が明確に伝わるように心がけましょう。報告が具体的であるほど、読み手は状況を正確に理解でき、的確なフィードバックをしやすくなります。
また、数値(件数・時間・金額など)や固有名詞(社名・担当者名・商品名など)を盛り込むことで、報告内容に信頼性と説得力が生まれます。業務報告をただの作業記録にせず、読み手にとって有益な情報として伝える意識を持つことが大切です。
所感・考察を加えて、自身の成長につなげる
「所感・考察」は、日報を自己成長の機会に変えるために欠かせない要素です。ここでは、業務を通じて得た学びや気づき、次に活かせる改善点を記述します。
「〇〇が成功した要因は△△だ」「次回は□□という方法を試したい」など、行動の結果とその理由をセットで書くことがポイントです。そうすることで、業務を客観的に振り返ることができ、次に活かせる実践的な学びにつながります。
日々の考えを言語化する習慣は、問題解決能力や論理的思考力を養う訓練にもなります。単に感想を述べるのではなく、原因分析の視点を持つことで、より深い学びが得られるでしょう。
【種類別】日報の具体的な書き方と例文
日報は職種や働き方によって、重視すべきポイントや記載内容が異なります。
新人、営業、テレワークという3つの代表的なケースについて、それぞれの特徴を踏まえた書き方を解説します。
具体的な例文もあわせて紹介しますので、日報作成に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
新人・研修期間の日報
新人日報では、教わった業務内容と、それに対する理解度や疑問点を正直に書くことが重要です。分からないことを明確にすることで、教育担当の上司や先輩が適切なフォローをしやすくなります。
「〇〇を学び、△△ができるようになった」など、日々の学びと成長を具体的に記述します。謙虚な姿勢を保ちながら、積極的に学ぶ意欲を示すことで、周囲からの信頼を得られるでしょう。
<例文>
【業務内容】
・9:00-12:00 営業部の基本業務フローについて山田先輩から説明を受けた
・13:00-15:00 顧客管理システムの操作方法を学び、テストデータで入力練習を実施
・15:00-17:00 電話応対マニュアルを読み込み、実際に3件の問い合わせ対応を行った
【所感・考察】
顧客管理システムの基本操作は理解できたものの、検索機能の使い方にまだ不安が残ります。
電話応対では、お客様の要望を正確に聞き取ることの難しさを特に実感しました。
明日は検索機能について再度確認し、電話応対時のメモの取り方を工夫したいと思います。
【明日の予定】
・顧客管理システムの応用機能の習得
・営業同行の準備(資料確認、質問事項の整理)
営業日報
営業日報では、訪問件数や商談内容、受注額といった活動実績を定量的な数値で示しましょう。
顧客の反応や課題、次回の具体的なアクションプランを記載し、案件の進捗状況を明確に共有します。受注や失注の要因を自分なりに分析し、記述することで、今後の営業戦略やスキルアップに役立てられます。
数値だけでなく、顧客の生の声や競合情報なども記載することで、チーム全体の営業力向上につながるでしょう。
<例文>
【業務内容】
・訪問件数:5件(新規2件、既存3件)
・A社(既存):追加発注の商談。予算30万円で来月導入予定。決裁者の承認待ち
・B社(新規):初回訪問。製品デモを実施し、2週間の無料トライアルを開始
・C社(既存):クレーム対応。システムの不具合について謝罪し、明日技術部が訪問予定
【所感・考察】
A社は競合他社も提案しているため、差別化ポイントを明確に伝える必要があります。
B社は導入意欲が高く、トライアル期間中のフォローが受注の鍵になると判断しました。
C社のクレームは初期設定のミスが原因だったため、今後は導入時のチェック体制を強化します。
【明日の予定】
・C社への技術部同行訪問
・B社へのフォローコール
・新規リスト20件への架電
在宅勤務(テレワーク)の際の日報
在宅勤務の日報では、業務の開始・終了時刻と具体的な作業内容を時系列で記載することが大切です。
オフィス勤務と異なり、仕事の様子が見えにくいため、進捗状況や成果をより詳しく報告することで、上司やチームメンバーの不安を取り除けます。
また、コミュニケーション上の課題や業務環境の問題点があれば、積極的に記述して改善を促します。状況を丁寧に伝えることで、相手との認識のズレを防ぎ、良好な関係づくりにつながるでしょう。
<例文>
【業務内容】
・8:30 業務開始、メールチェックとスケジュール確認
・9:00-10:30 企画書作成(新商品プロモーション案)、初稿完成
・10:30-11:00 オンライン会議(週次定例、参加者5名)
・13:00-15:00 データ分析作業(売上推移レポート作成)
・15:00-16:30 企画書の修正と最終版作成
・17:00 業務終了
【所感・考察】
自宅での作業は集中できる反面、チームメンバーとのカジュアルな情報交換が減っていると感じます。
オンライン会議では積極的に発言し、Slackでも細かく進捗を共有するよう心がけました。
明日は定期的な雑談タイムの提案をして、チームの一体感向上に貢献したいと思います。
【明日の予定】
・企画書のプレゼン準備
・月次レポートの作成開始
日報を書くメリット
ここでは、日報を書くことで得られる3つのメリットについて、詳しく解説します。
- 自身の成長を客観的に記録できる
- 上司やチームとの情報共有を円滑にする
- 業務の課題や改善点を発見しやすくなる
それぞれ見ていきましょう。
自身の成長を客観的に記録できる
日報は、日々の業務で得たスキルや直面した課題を記録し、自身の成長過程を可視化するツールです。取り組みの積み重ねや考え方の変化を記録することで、自分の成長を客観的に振り返ることができます。
また、日報には設定した目標に対する日々の進捗やアクションの記録も残るため、自己評価の精度が上がり、次の目標設定にも役立ちます。過去の日報を振り返ることで、以前の自分との違いを実感でき、成長を確信できるでしょう。
こうした気づきは、自信やモチベーションの向上にもつながり、日々の業務への前向きな姿勢を後押しします。
上司やチームとの情報共有を円滑にする
日報は、自分の業務内容や進捗状況を上司やチームに正確に伝えるためのツールです。口頭だけでは伝わりにくい細かな作業内容や気づきも文章に残すことで、報告漏れや認識のズレを防ぎ、関係者間で必要な情報が確実に共有される状態をつくります。
また、他のメンバーの日報を読むことで、チーム全体の動きを把握でき、より円滑な連携が可能です。誰がどの業務に取り組んでいるのかが見える化されることで、サポート体制の構築や業務の適切な分担にもつながります。
特にリモートワークが増えた現在、日報による情報共有の重要性はさらに高まっています。
業務の課題や改善点を発見しやすくなる
日々の業務を文章で振り返ることで、非効率な作業や潜在的な問題点に気づきやすくなります。「この作業に想定以上の時間がかかっている」といった気づきが、業務プロセスの見直しにつながるのです。
さらに、発見した課題を共有することで、上司や同僚から客観的なアドバイスをもらい、解決の糸口が見つかることもあります。チームとして改善策を検討・実行することで、組織全体の生産性向上にも寄与するでしょう。
日報は単なる報告ツールではなく、日々の業務をよりよくするための「気づきのきっかけ」としても有効なのです。
評価される日報を書くためのポイント
日報を単なる義務ではなく、自己成長とキャリアアップのツールとして活用するためには、いくつかのコツがあります。
以下では、実践的な3つのポイントについて詳しく解説します。
- テンプレートを活用して、作成時間を短縮する
- 事実と所感を分けて記述する
- ネガティブな報告は、改善案とセットで伝える
それぞれ見ていきましょう。
テンプレートを活用して、作成時間を短縮する
日報を毎回ゼロから作成するのは、思った以上に時間がかかるものです。あらかじめ記載項目を定めたテンプレートを活用することで、入力作業の手間を大幅に減らすことができ、日報作成を効率化できます。
会社指定のフォーマットがない場合でも、基本構成に沿って自分なりの雛形を作成しておくとよいでしょう。あらかじめ書くべき内容が整理されていることで、考えがまとまりやすくなり、スムーズに記述を進められます。
日報作成の時間を短縮した分、内容を吟味する時間を確保でき、より深い振り返りや考察に集中できるため、日報全体の価値を高めることにもつながります。
事実と所感を分けて記述する
「業務内容(事実)」と「所感(意見)」の項目を明確に分けることで、読み手に意図が伝わりやすくなります。
事実と意見が混在した文章は、何が起きたのか、書き手がどう考えているのかが分かりにくいです。そのため、「思ったより時間がかかったので、次回は手順を簡略化したい(所感)」というように、事実と意見を分けることで、読み手が状況を正確に把握しやすくなります。
このように、客観的な事実報告とそれに基づく主観的な考察を区別することが論理的な報告の基本です。この習慣は、ビジネス文書全般の作成スキル向上にもつながるでしょう。
ネガティブな報告は、改善案とセットで伝える
ミスやトラブルを報告する際は、単に事実を述べるだけでなく原因分析と再発防止策をセットで記述しましょう。失敗を隠すのではなく、正直に報告し、次につなげる姿勢を見せることで、責任感や主体性を評価されやすくなります。
また、報告の際には「次回はこうしたい」といった具体的な改善案を提示することで、問題解決能力を示し、上司やチームからの信頼を得られます。ネガティブな出来事は誰にでも起こりうるものですが、それをどう伝え、どう活かすかで印象は大きく変わるでしょう。
効果的な日報の書き方をマスターして、キャリアアップを目指そう!
日報は、基本構成の「業務内容」「所感・考察」「明日の予定」を押さえ、5W1Hを意識した記述を心がけることで、自身の成長や周囲との連携につながる報告書を作成できます。
新人は学びと成長を、営業は数値と分析を、テレワークは詳細な進捗を重視し、それぞれの立場に応じた日報を作成することが大切です。
さらに、テンプレートの活用で記入の手間を減らし、事実と意見を分けて書く、ネガティブな報告には改善案を添えるといった工夫を取り入れることで、報告書としての完成度が高まります。
このような日報を継続的に書くことで、業務を客観的に見直す習慣がつき、上司やチームとの信頼関係も深まるでしょう。今回紹介したポイントや項目を意識しながら、自身の成長につながる日報を書いてみてください。

