営業報告書の書き方完全ガイド|目的・項目・例文まで分かりやすく解説
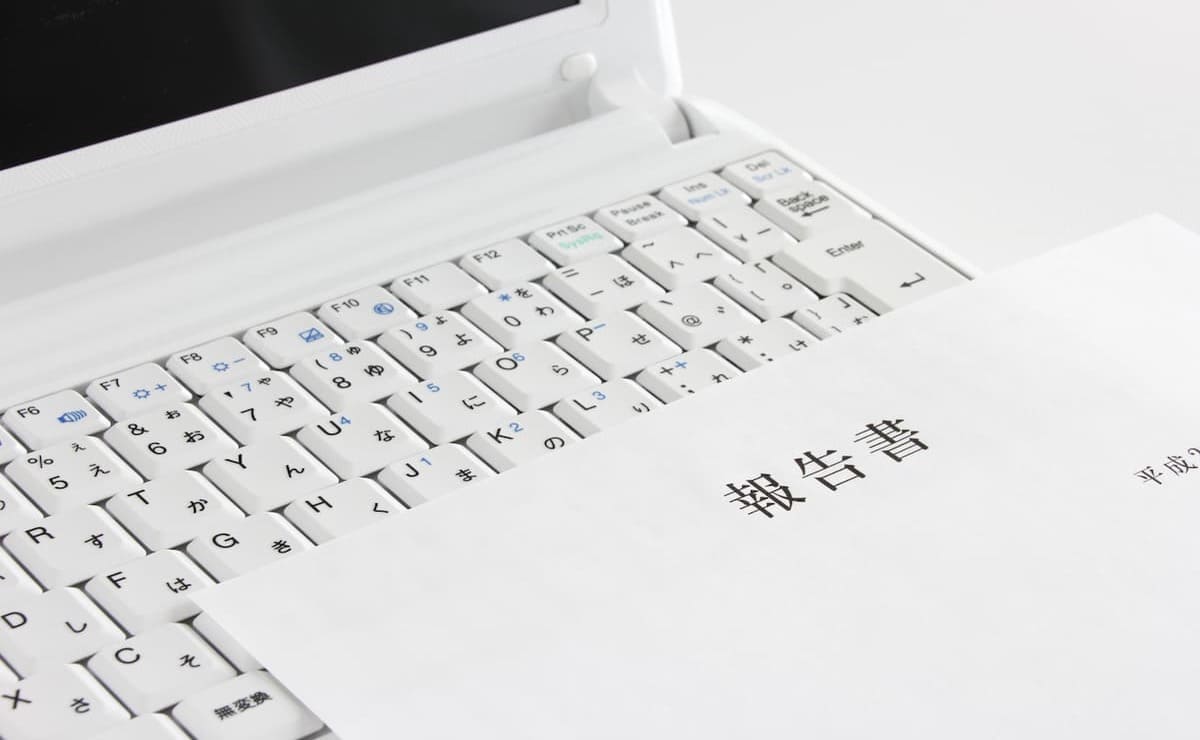
営業報告書は、担当者の活動内容や進捗を上司やチームに正確に伝えるためのツールです。成功事例や失敗の共有を通じて、課題の発見や改善策の検討につなげることができます。また、自身の活動を振り返ったり、他の社員の報告書を参考にしたりすることで、営業のヒントを得ることも可能です。
本記事では、営業報告書の書き方や上司やチームに評価されやすい営業報告書を書くポイントについて詳しく解説します。例文も紹介しますので、ぜひ参考にして、日々の報告業務に活かしてください。
【この記事のポイント】
- 営業報告書は活動進捗を上司やチームに共有し、成功や失敗の事例から課題発見や改善策の検討につなげる目的を持つ。
- 報告書は5W1Hを意識して具体的に記述し、活動内容や成果、課題、そして今後のアクションプランを記載する。
- 客観的な事実と主観的な所感を明確に区別したうえで、具体的な数値を用いて報告することが重要である。
【項目別】営業報告書の書き方
営業報告書を効果的に作成するには、必要な項目を漏れなく記載し、読み手に分かりやすく伝えることが重要です。
以下では、営業報告書に欠かせない5つの項目について、具体的な書き方と例文を交えながら詳しく解説します。
- 訪問日時・訪問先・担当者
- 訪問の目的
- 活動内容・商談内容
- 成果と課題
- 次のアクションプラン
訪問日時・訪問先・担当者
「いつ」「どこで」「誰と」会ったのかという基本情報は、誰が見ても分かるように正確に記録することが大切です。日時を正確に記載することで、後から活動履歴を時系列で簡単に振り返ることが可能になります。
また、企業名や部署名だけでなく担当者名も正確に記すことで、責任の所在とキーパーソンを明確にします。これらの基本情報は、後日のフォローアップや引き継ぎの際にも重要な参照データとなるでしょう。
- 訪問日時:2024年3月15日(金)14:00~15:30
訪問先:株式会社ABC商事 本社
担当者:営業部 山田太郎部長、購買課 鈴木花子課長 - 訪問日時:2024年3月16日(土)10:00~11:00
訪問先:DEF工業株式会社 横浜工場
担当者:生産管理部 田中一郎マネージャー - 訪問日時:2024年3月18日(月)16:00~17:30
訪問先:GHIシステムズ株式会社 大阪支店
担当者:IT推進室 佐藤次郎室長、情報システム部 高橋三郎主任
訪問の目的
訪問の目的を書く際は、その営業活動が「何を達成するため」のものだったのか、事前に設定したゴールを明確に記載します。目的を最初に書くことで、読み手はその後の活動内容や成果を意図と照らし合わせて理解できるのです。
また、活動の目的意識を明確にすることにより、行き当たりばったりの営業を防ぎ、戦略的な行動を促す効果があります。目的は具体的かつ測定可能な内容にすることで、成果の評価も容易になるでしょう。
- 新製品Xの導入提案および、現行システムの課題ヒアリング
- 前回提案した見積もりに対する回答確認と、導入スケジュールの調整
- 競合他社との比較検討状況の確認および、追加デモンストレーションの実施
活動内容・商談内容
顧客と「どのようなやり取りをしたのか」という商談の具体的なプロセスは、時系列に沿って具体的に記録しましょう。提案した内容、それに対する顧客の反応、ヒアリングで得られた情報などを客観的な事実として記述することが大切です。
重要な発言や質問、顧客が示した懸念点などを具体的に書くことで、商談の温度感を正確に伝えられます。議論の流れを再現できるような内容にすることで、次回の商談戦略を立てやすくなるでしょう。
- 14:00~14:30:新製品Xの機能説明とデモンストレーションを実施。山田部長は特に自動化機能に強い関心を示し、「現在の手作業を80%削減できる」という点を高く評価
- 14:30~15:00:現行システムの課題をヒアリング。「データ入力に時間がかかる」「レポート作成が煩雑」という2点が主な問題として挙げられた
- 15:00~15:30:導入費用と投資対効果について説明。初期費用300万円に対し、年間500万円のコスト削減が見込めることを数値で提示。鈴木課長から「費用対効果の詳細資料が欲しい」との要望あり
成果と課題
活動の結果として「何が得られたか(成果)」と「何が達成できなかったか(課題)」を明確に記録しましょう。成果には「アポイント獲得」や「見積もり依頼」など、次のステップにつながる具体的な事実を記載します。
一方、課題には、受注に至らなかった理由や顧客から指摘された問題点などを正直に書き、次に活かします。このように結果を整理することで、営業活動の振り返りがしやすくなり、次の戦略につなげられるのです。
失敗を恐れず課題を明確にすることで、組織全体の営業力向上に貢献できます。
- 成果:費用対効果の詳細資料提出の約束を取り付け、次回プレゼンテーションの日程を4月5日に確定
- 成果:決裁者である山田部長から前向きな評価を獲得し、社内検討会議での提案許可を取得
- 課題:競合A社の製品との機能比較で、カスタマイズ性の面で劣るという指摘を受けた。技術部門と連携し、カスタマイズオプションの検討が必要
次のアクションプラン
今回の活動結果を踏まえ、「次にいつまでに何をすべきか」という具体的な行動計画を示します。例えば、「〇月〇日までにAさんに再度連絡する」など、明確な期日と担当者、行動内容を具体的に記述します。
次にとるべき行動を宣言することで、上司からの承認を得やすくなり、PDCAサイクルを効率的に回すことが可能です。アクションプランは実現可能で測定可能な内容にすることで、進捗管理が容易になるでしょう。
- 3月22日まで:費用対効果の詳細資料を作成し、鈴木課長にメールで送付
- 3月25日:技術部門と打ち合わせを行い、カスタマイズオプションの可能性を検討
- 4月5日:山田部長、鈴木課長を含む社内検討会議でプレゼンテーションを実施。カスタマイズ対応を含めた最終提案を行う
評価される営業報告書の書き方のポイント
営業報告書の質を高めるには、単に事実を羅列するだけでなく、読み手にとって価値のある情報を分かりやすく伝える工夫が必要です。
以下では、評価される営業報告書を書くための4つのポイントについて解説します。
- 5W1Hを意識して具体的に書く
- 客観的な事実と主観的な所感を区別する
- 具体的な数値を用いて報告する
- 要点を絞ってまとめる
上司やチームメンバーが迅速に状況を把握し、適切な判断や支援ができるような報告書作成を心がけましょう。
5W1Hを意識して具体的に書く
「いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように」の5W1Hを明確にすることで、情報が具体的に伝わります。抽象的な表現を避け、実際の行動や発言を記述することで、読み手が状況を正確にイメージできるのです。
例えば、「お客様に提案を行った」と書くよりも、「8月5日、〇〇社のA様とオンラインで打ち合わせを行い、新サービスの導入提案をした」と書くことで、何があったのかが明確になります。
5W1Hのフレームワークは報告内容の抜け漏れを防ぎ、論理的な構成で報告書を作成するのに役立ちます。特に「なぜ」と「どのように」の部分を充実させることで、単なる活動報告から戦略的な報告書へと進化するでしょう。
客観的な事実と主観的な所感を区別する
実際に起きた「事実」と、それに対する自分の考えや感想である「所感」は明確に分けて記載しましょう。事実と所感を混同すると、報告の客観性が失われ、読み手に誤った情報を与えかねません。
例えば、事実は「〇〇社の担当者と15時に打ち合わせを行った」と記し、所感は「提案内容に改善の余地があると感じている」と書きます。このように、事実は過去形で、所感は現在形や未来形で書き分けることで、区別がより明確になるでしょう。
また、「所感」の欄では、事実から導き出される考察や改善提案を記述することで、自身の思考力をアピールできます。
具体的な数値を用いて報告する
「たくさん」や「少し」といった曖昧な表現ではなく、具体的な数値を用いて定量的に報告することで、進捗や成果を正確に把握できます。
例えば、「訪問件数3件」「提案資料の閲覧時間15分」など、数値を盛り込むと、読み手が状況をイメージしやすくなり、より説得力のある報告になるでしょう。
数値で報告する習慣をつけることで、目標に対する進捗管理が容易になり、データに基づいた分析が可能になります。パフォーマンスの変化や向上も一目で分かるようになるため、自身の成長を実感しやすくなり、モチベーションの維持にもつながるでしょう。
要点を絞ってまとめる
報告書は、忙しい上司が短時間で目を通せるように簡潔にまとめる必要があります。そのためには、伝えたい情報の「要点」を明確にし、簡潔にまとめることが大切です。
長文の報告は避け、結論から先に書く「PREP法(Point:結論 → Reason:理由 → Example:具体例 → Point:結論の再提示)」などを意識して、構成を組み立てることが望ましいでしょう。
また、専門用語や社内用語の多用は避け、誰が読んでも理解できる平易な言葉で表現することが求められます。複数の要素を並べて説明する場合や、具体的な成果・課題を整理する際は、箇条書きや段落分けの使用が効果的です。
営業報告書の作成を効率化する方法
営業報告書の作成は重要な業務ですが、時間がかかりすぎると本来の営業活動に支障をきたします。
以下では、営業報告書作成を効率化する3つの方法について詳しく解説します。
- 共有のテンプレート(雛形)を活用する
- SFA/CRMツールを導入し、入力を自動化する
- 音声入力機能を使って、移動中に下書きを作成する
それぞれ見ていきましょう。
共有のテンプレート(雛形)を活用する
報告書や日報を毎回ゼロから作成していると、時間や労力がかかるうえ、記載内容にばらつきが出てしまうこともあります。そこで、あらかじめ必須項目を網羅したテンプレートを用意しておくことが有効です。
組織で統一されたテンプレートを使えば、報告の質が標準化され、読む側も内容を把握しやすくなります。選択式の入力欄や記入例をあらかじめ設けておけば、作成のハードルも下がり、誰でもスムーズに報告書を作成できるでしょう。
テンプレートは一度作ったら終わりではなく、定期的に見直すことが重要です。現場の業務やニーズの変化に応じて、実際の利用者の声を反映しましょう。
SFA/CRMツールを導入し、入力を自動化する
SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理)を導入すると、顧客情報や商談履歴と連携し、報告書作成の一部を自動化できます。商談記録や進捗状況などがリアルタイムで共有されるため、手作業による入力ミスの防止も可能です。
また、こうしたツールはスマートフォンにも対応しており、外出先からでも簡単に入力できるため、報告のためだけに帰社する必要がなくなります。営業活動の合間に手軽に入力できることで、報告のタイミングも早まり、チーム内での情報共有がスムーズになるでしょう。
さらに、蓄積されたデータは自動で集計・分析されるため、報告書作成だけでなく営業戦略の立案にも役立ちます。
音声入力機能を使って、移動中に下書きを作成する
スマートフォンの音声入力機能を活用すれば、移動中などの隙間時間に報告書の下書きを作成できます。商談直後の記憶が新しいうちに要点を話してテキスト化しておくことで、後からの思い出し作業を減らせるのです。
テキスト化された下書きを、後でPCで清書するだけで済むため、デスクでの作業時間を大幅に短縮できます。近年は音声入力の精度も大きく向上しており、話し言葉の自然な変換はもちろん、業界特有の専門用語も正確に認識されるようになっています。
こうした技術をうまく取り入れることで、報告書作成の効率を高めながら、情報の鮮度と正確さも維持できるでしょう。
正しい営業報告書の書き方を実践して、営業成果を最大化しよう
営業報告書は、「訪問日時・訪問先・担当者」「訪問の目的」「活動内容・商談内容」」「成果と課題」「次のアクションプラン」という5つの基本項目を押さえることで、効果的な情報共有ツールとなります。
また、「5W1Hを意識して具体的に書く」「客観的な事実と主観的な所感を区別する」「具体的な数値を用いて報告する」「要点を絞ってまとめる」という4つのポイントを実践することで、上司やチームから高く評価される報告書が作成できるでしょう。
さらに、テンプレートの活用、SFA/CRMツールの導入、音声入力機能の活用により、報告書作成の効率化を図ることで、本来の営業活動により多くの時間を割くことができます。本記事を参考に営業報告書を作成し、営業成果の向上を目指しましょう。

