電子契約における法的に有効な保管方法と電子帳簿保存法ガイド
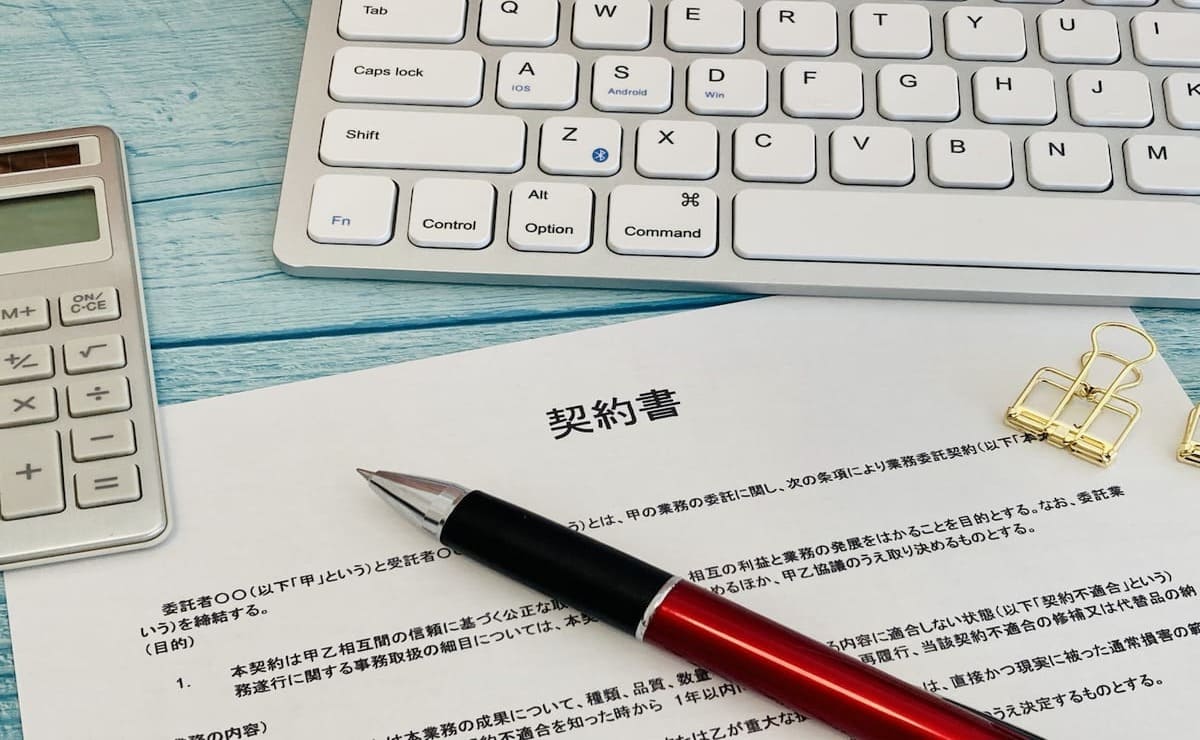
電子契約は、今まで紙で行ってきた契約業務をオンライン上で行うことができるため、業務効率化に大きく貢献します。しかし、メリットがある一方で、データを保管する際に適切な方法を守らないと法的リスクが生じる危険があり、取り扱いには注意しなければなりません。
本記事では、電子契約における法的有効な保管方法と電子帳簿保存法のポイントを解説します。自社のコンプライアンス確保と効率的な文書管理の両立を目指している方は、ぜひ参考にしてください。

【この記事のポイント】
- 電子契約は業務効率化に寄与するが、法的リスクを避けるため電子帳簿保存法が定める改ざん防止や検索機能の確保といった4つの要件を確実に満たす必要がある。
- 契約データの保存期間は原則7年間と定められているが、納税地から速やかに閲覧や検索、印刷ができる状態であれば、サーバーの物理的な保管場所は問われない。
- データの喪失や改ざんを防ぐため、定期的なバックアップや復元テストの実施に加え、複数箇所での分散保管など、あらゆるリスクを想定した対策が不可欠である。
電子契約の保管方法とは?
電子契約の保管は、2024年1月に完全義務化された電子帳簿保存法の要件に従わなければなりません。電子帳簿保存法は、国税関係書類の電子保存に関する法律で、電子契約の保管方法についても具体的な要件を規定しています。
電子契約は印紙税の節約や業務効率化などのメリットがありますが、保管方法を誤ると法的リスクが生じる恐れがあります。そのため、電子帳簿保存法の要件を確認し、正しい保管ルールの理解が不可欠です。
法的義務の概要
電子契約は電子帳簿保存法における「電子取引」に該当するため、同法の定める保管要件を満たさないと法律違反となります。電子取引の定義は「取引情報の授受を電磁的方式により行う取引」であり、電子契約サービスを使った契約締結はこれに該当するため、保管には注意が必要です。
法に違反した場合、税務調査時の否認リスクや、最悪の場合は重加算税などのペナルティが課せられる可能性があります。法違反を起こさないためにも、電子帳簿保存法の要件を正しく理解し、確実に対応することが大切です。
保存年数と保管場所
電子契約データは、原則7年間保存しなければなりません。欠損金の繰越控除をする法人の場合は、最長10年間の保存が必要となることがあります。
また、国税庁の見解では「納税地から閲覧・検索・印刷できる状態であれば、サーバーの物理的所在地は問わない」とされています。そのため、納税地からアクセスできれば、クラウドや海外サーバーでも電子契約データの保管が可能です。
電子契約データ保管の法的要件
電子契約データの保管には以下の4つの法的要件があり、すべての要件を満たす必要があります。
- データ改ざんを防止する
- 効率的な検索システムを実装する
- 契約データへのアクセス環境を整備する
- システム操作手順を文書化する
ここでは、それぞれの要件を詳しく見ていきましょう。
データ改ざんを防止する
電子契約データの信頼性を確保するためには、タイムスタンプの付与や改ざん防止システムの導入が不可欠です。
従来はすべてのファイルに認定タイムスタンプの付与が求められていましたが、現在は以下の4つの方法のいずれかを選択できます。
- タイムスタンプが付与された後に、取引情報を授受する
- 取引情報授受後、速やかにタイムスタンプを付与する
- 「データを訂正・削除した記録が残るシステム」または「訂正・削除ができないシステム」を利用する
- 訂正・削除防止に関する事務処理規程を整備する
自社の業務フローに合わせた、改ざん防止策の導入を行いましょう。
効率的な検索システムを実装する
税務調査などでの迅速な対応のため、日付・金額・取引先での検索や条件組み合わせ検索が必須です。具体的には、以下のような検索機能がなくてはなりません。
- 取引年月日・取引金額・取引先を検索条件として設定できる
- 日付や金額は範囲指定での検索ができる
ただし、税務職員のダウンロードの要求に応じられる場合は、範囲指定や条件組み合わせ検索の要件は緩和されます。
契約データへのアクセス環境を整備する
電子契約データをディスプレイ表示や印刷出力で明瞭に確認できる、環境の整備が欠かせません。具体的には、契約データを閲覧するためのパソコンやディスプレイ、プリンターなどの環境を用意しておきましょう。
データはディスプレイの画面または書面で整え、明瞭な状態で速やかに表示できる必要があり、データ形式の互換性確保も重要です。
システム操作手順を文書化する
電子契約システムの操作マニュアルや責任者体制を文書化し、誰でも適切に利用できる状態を維持してください。自社開発システムの場合はシステム概要書なども必要ですが、市販ソフトの場合は操作マニュアルのみで対応可能です。
マニュアルは紙でもオンラインヘルプでも問題ありませんが、必要時に参照できる状態を確保する必要があります。
電子契約のデータを適切に保管する際のポイント
電子契約データを適切に保管するポイントは、以下の4つです。
- 保管データの法的証明力を確保する
- 2024年以降の特例措置を活用する
- 保管方法の選択基準を理解する
- バックアップと災害対策を講じる
ここでは、それぞれのポイントを詳しく解説します。
保管データの法的証明力を確保する
訴訟などでの証拠能力を確保するためには、電子署名の適切な実施とデータの完全性証明がポイントとなります。電子署名法に準拠した電子署名を付与し、その検証可能性を維持することが契約の真正性担保に不可欠です。
また、アクセスログの保存やタイムスタンプの有効性確認など、データの完全性を証明するための補助的な証拠も大切です。法的証明力の確保は、電子契約データの適切な保管に欠かせない視点と言えるでしょう。
2024年以降の特例措置を活用する
2024年以降も、相当の理由がある場合は紙での保存も例外的に認められます。
特例措置が適用される条件は、以下の2点です。
- 要件に従って電子取引データを保存できなかったことについて、所轄税務署⻑が相当の理由があると認める
- 税務調査などの際に、「電子取引データのダウンロード要求」と「電子取引データの出力書面の提示・提出」への対応をする
ただし、相当の理由の判断基準は明確ではないため、安易に特例措置に依存するとリスクを伴います。例外的に認められると言っても、将来的な電子化体制の構築は計画すべきです。
保管方法の選択基準を理解する
電子契約データの保管は、クラウド保管のセキュリティ性や社内保管の自由度など、それぞれの特性を考慮して選択しなければなりません。
クラウド保管は初期投資が少なく、専門的な機能が利用できますが、長期的なコストや特定のベンダーへの依存に注意が必要です。一方、社内保管は自社のポリシーに合わせた管理が可能ですが、システム構築・運用の技術的負担や、セキュリティ対策の責任が大きくなります。
バックアップと災害対策を講じる
電子契約データの喪失リスクを回避するために、定期的なバックアップや複数場所での保管など、二重三重の対策をしましょう。自然災害やサイバー攻撃、人為的ミスなど、さまざまなリスクを想定したバックアップ体制の構築が不可欠です。
また、定期的な復元テストを実施し、バックアップデータの実効性を確認することも忘れてはなりません。
電子契約データの保管を効率化する方法
電子契約データの保管を効率化するには、主に以下の2つの方法があります。
- 電子契約専用サービスを活用する
- 保管業務を体系化する
ここでは、それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。
電子契約専用サービスを活用する
電子帳簿保存法対応の電子契約サービスは、自動タイムスタンプ付与や検索機能などの法的要件をすでに満たしており、データ保管の負担軽減につながります。サービス選定時には、電子帳簿保存法への対応を明記しているか、API連携などの拡張性があるか、データエクスポート機能があるかなどを確認しましょう。
長期契約前にトライアル利用やユーザーレビューの確認を行い、自社業務との相性を検証することも大切です。
保管業務を体系化する
電子契約の保管業務を標準化し、担当者の役割や監査体制を明確にすることで、確実な法的対応と業務効率化が両立できます。具体的には保管業務の手順書作成や、責任者と実務担当者の明確化、定期的な監査体制の構築などが効果的です。
新たな電子契約サービス導入時には、関連部署との連携強化や従業員教育も行うことで、効率的な導入・運用が可能です。
効率的で安全な電子契約データの保管を始めよう
電子帳簿保存法の要件を理解し、自社に最適な保管方法を選択することで、コンプライアンスを確保しながら文書管理の効率化を実現できます。電子契約データの保管は単なる法的義務ではなく、業務効率化とリスク管理の両面から企業経営に貢献する取り組みなのです。
本記事を参考に、自社の状況に合わせた効率的で安全な電子契約データの保管体制を構築してください。電子契約の適切な運用とデータ保管により、自社のビジネス変革を加速させましょう。

