借用書を電子契約で作成できる? 作成のステップや法的効力などを解説
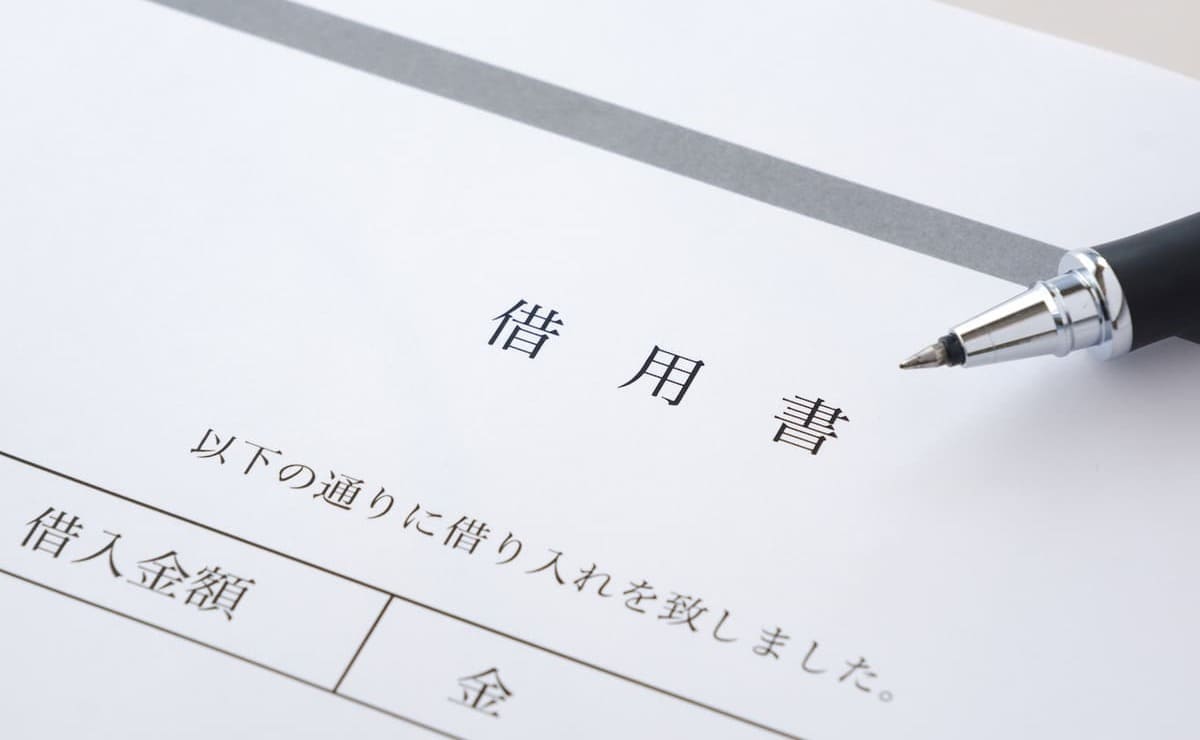
借用書の電子化が進むなか、電子契約で借用書の作成が可能になり、自社での導入を考えている企業も多いかもしれません。しかし、今まで借用書の作成は紙で行っていたため、どのように電子契約で借用書を作成すればいいのか分からない担当者も多いのではないでしょうか。
本記事では、借用書の電子契約が法的に有効である理由や、電子契約での借用書の作成方法、紙の借用書との違いとメリットについて解説します。借用書作成を効率化し、コスト削減を図りたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

【この記事のポイント】
- 電子契約で作成された借用書は、電子署名法に基づき適切に作成されれば、従来の紙の契約書と全く同等の法的効力を持つ、正式な文書として認められている。
- 電子契約で借用書を作成する最大のメリットは、印紙税法上の課税文書に該当しないため、契約金額の大小に関わらず、収入印紙代を全額削減できる点である。
- 電子借用書を作成する際は、法的効力を担保するために電子署名やタイムスタンプを付与し、改正電子帳簿保存法の要件に従って適切に保存する必要がある。
借用書は電子契約で作成可能?
借用書は電子契約で作成でき、その利便性から、近年借用書の電子化が急速に進んでいます。ここでは、借用書を電子契約で作成することの法的有効性や、電子借用書が活用されている主な場面、法的効力について見ていきましょう。
電子契約の借用書が法的に有効な理由
電子契約で作成された借用書は法的に有効であり、電子署名法に基づいて適切に作成されれば、紙の借用書と同等の法的効力を持ちます。
さらに、2020年の改正電子帳簿保存法により、電子取引の取引情報は電子データでの保存が義務付けられ(2024年1月に完全義務化)、借用書の電子化がより一般的になりました。電子借用書は印紙税法上も課税文書として扱われないため、収入印紙の貼付が不要となり、コスト削減効果もあります。
電子契約書式での借用書が活用されている主な場面
電子借用書は、個人間の少額での金銭消費貸借から企業間の大型融資まで、幅広い場面で活用が進んでいます。リモートワークの一般化によって対面での書類手続きが困難になったことが、電子契約による借用書の需要急増の要因です。
金融機関やフィンテック企業による個人向け融資サービスでは、顧客の利便性向上のため、電子契約形式での借用書が標準的に採用されています。また、不動産賃貸借における敷金の差し入れに関する書類など、日常的な取引でも電子契約形式の借用書の利用が広がっています。
電子形式の借用書と紙の借用書の効力は同等
民法上、金銭消費貸借は要式契約ではないため、電子形式の借用書と紙の借用書には法的効力の差はありません。また、電子署名法に基づいて認証された電子署名が付与された電子形式の借用書は、本人の意思に基づいて作成されたものと推定され、紙の借用書と同等以上の証明力を持つ場合もあります。
さらに、電子形式の借用書は改ざんの痕跡が残りやすく、作成日時の証明も容易であるため、紙の借用書よりも証拠としての信頼性が高いと評価されることもあります。
借用書を電子契約で作成する方法とステップ
電子契約で借用書を作成する際は、以下のステップに沿って進めていきましょう。
- 最適な電子契約プラットフォームを選定する
- 電子契約形式の借用書の基本要素を含める
- 電子契約形式の借用書を作成する
ここでは、それぞれの作成工程について詳しく解説します。
最適な電子契約プラットフォームを選定する
電子契約プラットフォームは、複数のサービスから費用・機能・使いやすさを基準に選定することが大切です。
各プラットフォームには独自の特徴があるため、自社に合ったシステムを選択してください。月額費用や1契約あたりの料金体系、同時に締結できる契約数など、自社の取引量に合わせた選定基準を設けることで、コストパフォーマンスの高いサービスを選びましょう。
電子借用書の基本要素を含める
次に、自社の電子契約形式の借用書に必要な基本要素を確認しましょう。電子契約形式の借用書には、取引内容や当事者情報、返済条件などの基本要素に加え、電子署名やタイムスタンプなどの電子契約特有の要素を含めなければなりません。
紙の借用書と異なり、電子契約形式の借用書では本人確認の方法として、メールアドレスや電話番号による認証プロセスを組み込むことが一般的です。
また、電子署名の種類が電子認証局発行の電子証明書を使用する「認証局型」と、手書きサインをデジタル化する「サインパネル型」のどちらであるかにより、契約が有効であることの証明力が異なりうることを理解しておきましょう。
電子契約形式の借用書を作成する
電子契約形式の借用書の作成は、テンプレートの選択から始まり、必要情報の入力、相手方への署名依頼送信、双方の署名完了までの一連のプロセスで行われます。
多くの電子契約サービスでは、過去の契約書を複製して再利用できる機能があり、同様の貸借契約を繰り返し行う場合に、作業効率を大幅に向上させることが可能です。
また、相手方への送信時にSMSやメールで通知を行い、未署名の場合は自動でリマインドを送信する機能を活用することで、契約締結までの時間の短縮を促すことができます。
電子契約による借用書の法的効力と証明力
電子契約で作成された借用書の法的効力と証明力(証拠としてどの程度有力であるか)は、電子署名法の観点や裁判事例から評価されます。ここでは、電子署名法の要件や裁判所の判断傾向、電子借用書の証明力を強化する方法について見ていきましょう。
電子署名法の観点から
電子署名及び認証業務に関する法律では、一定の要件を満たした電子契約形式の借用書は、紙の借用書と同等の法的効力を持つと規定されています。
特に、以下の3つの要件を満たすことが、法的な推定効を得るポイントです。
- 本人による電子署名
- 改変が検出できる技術的措置
- 本人が作成したことを示すための措置
また、2020年の法改正により、クラウド型電子署名(リモート署名)も法的に認められるようになり、さらに借用書の電子契約化が進みやすくなりました。
裁判事例から
裁判所は電子契約形式の借用書について、適切な認証プロセスと完全性の証明(契約書などの電子データが作成された後に、改ざんされていないのを証明すること)があれば、有効な証拠として認める傾向にあり、実際の裁判例でもその有効性が認められています。
過去の裁判例では、電子署名の信頼性やタイムスタンプの存在、アクセスログの保存状況などが証明力を判断する重要な要素として評価されています。一方で、簡易な電子サインのみで本人確認が不十分な場合や、データの保存状態に問題がある場合は証明力が否定される事例もあるため、適切な運用が必須です。
電子契約形式の借用書の証明力を強化するには
電子契約形式の借用書の証明力は、第三者によるタイムスタンプ認証、本人確認の厳格性、電子署名の技術レベルによって大きく強化されます。
特に、時刻認証業務認定事業者が発行するタイムスタンプの付与により、その時点でのデータの存在と内容の非改ざん性を客観的に証明することが可能です。
また、IPアドレスやデバイス情報、操作履歴など、電子契約の全プロセスのログを保存しておくことで、万が一の紛争時に契約の成立過程を詳細に証明できます。
紙の借用書と電子借用書の違いとメリット
電子契約形式の借用書は、以下のような紙の借用書とは異なる特性とメリットを持っています。
- 返済条件を電子的に明確化する
- 電子環境で当事者情報を適切に記録する
- 電子契約形式の借用書の実用的なメリットを活用する
ここでは、紙の借用書と電子借用書の違いやメリットについて、それぞれ見ていきましょう。
返済条件を電子的に明確化する
電子契約形式の借用書では、返済スケジュールや遅延利息の条件を構造化データとして記録し、自動リマインド機能と連携させることで返済管理の効率化が図れます。
返済日が近づくと自動的に通知が送られる機能を活用すれば、借主に返済期日を意識させることができ、未払いリスクの軽減に効果的です。また、返済履歴も自動的に記録されるため、返済状況の可視化が容易になり、管理の手間を減らすことができます。
遅延が発生した場合には、遅延損害金の金利計算を自動化できるため、手計算による誤りを防ぎ、正確な金額の算出が可能になります。
電子環境で当事者情報を適切に記録する
電子契約形式の借用書では、従来の署名・押印に代わり、メールアドレスや電話番号による本人確認と電子署名を組み合わせて当事者の特定と合意を証明します。
法人間の契約では、GビズID(gBizID)といった企業ごとに発行されるビジネスIDや、法人認証基盤を活用することで、より信頼性の高い本人確認が可能です。
また、契約当事者の住所や連絡先などの基本情報に変更があった場合も、電子的に一括更新できるため、最新の連絡先情報を維持しやすくなるでしょう。
電子契約形式の借用書の実用的なメリットを活用する
電子契約形式の借用書は全文検索機能、自動期限通知、場所を問わない締結手続きなど、紙の借用書にはない実用的な利点を多く提供します。これにより、契約管理の効率化だけでなく、コスト削減や業務の柔軟性向上も実現できます。
借入金額や返済日などの条件から、データベース検索が可能です。紙の借用書の場合、過去の契約書を探すには膨大な時間と手間がかかりますが、電子環境では必要な契約書を瞬時に検索できるため、業務の迅速化と正確性の向上が図れます。
また、ファイリング用品や保管スペース、管理人件費など、紙の契約書の保管コストが不要になり、特に大量の契約を扱う企業では大幅なコスト削減につながるでしょう。
安全な電子借用書のためのセキュリティと管理のポイント
電子契約形式の借用書を安全に運用するには、以下のようなセキュリティ対策と管理体制が欠かせません。
- 効果的なデータ保全戦略を構築する
- 本人確認の厳格化で「なりすまし」を防止する
- トラブル発生時の対応体制を整備する
ここでは、それぞれのポイントについて解説します。
効果的なデータ保全戦略を構築する
電子契約形式の借用書のデータ保全には、クラウドストレージと物理メディアの併用、定期的なフォーマット変換によるデータ劣化対策が効果的です。
長期保存が必要な電子契約形式の借用書は、技術の陳腐化に備えてPDF/A形式(※)など、長期保存に適した標準フォーマットで保存することが推奨されます。
※PDF/A形式:電子文書の長期保存用に定められた、PDFベースのファイル形式の1つ
また、重要度の高い借用書については、正本・副本の考え方を適用し、異なるストレージサービスに分散保存することで、災害やシステム障害時のリスク分散を図れます。
クラウドストレージ利用時には信頼性の高いサービスを選定し、データの暗号化、アクセス制御、バックアップの自動化など、セキュリティ対策も徹底しましょう。
本人確認の厳格化で「なりすまし」を防止する
電子契約形式の借用書でのなりすまし防止には、パスワードとSMS認証の組み合わせや、顔認証などの生体認証を活用した多要素認証が有効です。
特に高額な借用取引では、ビデオ通話による顔確認と身分証明書の提示を組み合わせるなど、より厳格な本人確認プロセスを設けることで安全性を高めてください。
また、契約締結権限の確認も重要であり、法人の場合は、登記簿情報や社内の決裁権限フローと連携した承認プロセスを構築することが望ましいです。
トラブル発生時の対応体制を整備する
電子契約形式の借用書におけるトラブル対応は、作成時のログデータ保存、署名プロセス全体の記録保持、第三者機関による証明書の取得が重要な解決策となります。
契約の有効性が争われた場合に備え、本人確認手段、契約内容の確認画面のスクリーンショット、同意クリックの記録など、契約プロセスの証拠を体系的に保存しておきましょう。
また、システム障害による契約プロセスの中断に備え、一時保存機能や再開手順をあらかじめ設定しておくことで、契約プロセスの信頼性を保てます。
電子契約で借用書の作成・管理を効率化しよう
電子契約による借用書の作成・管理は、これからの時代に欠かせない手段です。
電子契約形式の借用書は、契約作成時間の短縮や保管コストの削減、返済管理の自動化など、多くのメリットが得られる利点から、今後のデジタル時代の貸借関係の標準になると考えられます。
本記事で紹介した、法的効力や証明力、セキュリティ面での課題を十分に理解し、適切な対策を講じることで、電子借用書のメリットを最大限に活かすことが可能です。
貸借取引のデジタル化を推進し、自社の業務効率化やコスト削減、リスク管理の強化を実現しましょう。

