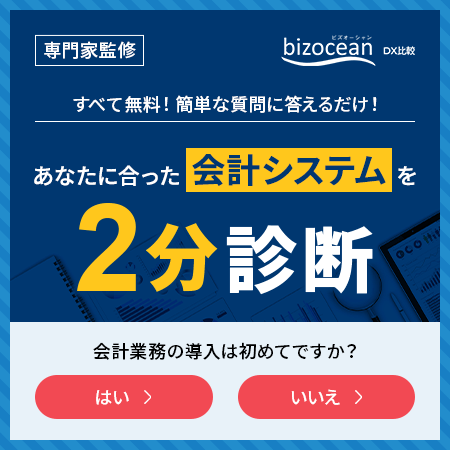Q&Aで学ぶ民法(債権法)改正 第4回「錯誤規制の見直し①」


Q:ダイビングを趣味とするAは、防水性の高い腕時計を買おうと思い、防水性のある時計を取り扱っている専門時計店Bで見つけた腕時計を購入しました。ところが後で説明書を読むと、日常生活を送る上で求められるレベルの防水機能はあるもののダイビングに使えるほど防水性は高くありませんでした。この場合に、Aは、勘違いしたことを理由としてBに腕時計を返品して返金を求めることができるでしょうか。
A:改正民法によって、設例Qでは、Aが購入の動機を述べていた場合には、Aは錯誤による取消を主張できる可能性があります。
1.改正のポイント
令和2(2020)年4月1日から債権法を改正する改正民法が施行されました。前回の「中間利息控除の見直し」に引き続き、本稿では錯誤規制の見直しについて取り上げます。
改正のポイントは
(1)錯誤の要件を明確に
(2)法律行為の効果が無効から取消へ
2.改正点の解説
それでは改正点を簡単に解説しましょう。
(1)錯誤の要件を明確に
改正により、保護の対象となる錯誤について、①意思表示に対応する意思を欠く錯誤(表示錯誤)と②表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(動機の錯誤)と要件を明確にしています。②については、「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り」取消を主張できるとします。
これまで「要素の錯誤」というわかりにくかった用語を、「その錯誤が法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なもの」と書き改めています。
まとめると、意思表示は、上記①・②に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができます(民法95条1項)。
(2)法律行為の効果が無効から取消へ
錯誤による法律行為の効果について、改正前民法では「無効」としていました。錯誤に陥ったまま意思表示をしてしまった表意者を保護するためです。もっとも、法律上「無効」というのは誰でも主張できるはずですが、表意者(A)が無効を主張していない場合にまで、あえて相手方(B)や第三者(例えばAの知人のC)からの無効の主張を認める必要性はありません。そのため表意者のみが主張できるべきであり、それならば「取消」と同様であると考えられました。そこで、改正民法では無効から「取消」へと錯誤の効果を変更することとしました。
また、取引の相手方の保護のために、改正民法は、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、錯誤による意思表示の取消をすることができないと規定しますが、次の2つの例外を設けます。
(1)相手方が表意者に錯誤があることを知り、または重大な過失によって知らなかったとき
(2)相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
3.錯誤とは?改正の理由は?
それでは、改正された錯誤とは何でしょうか。またなぜ改正されたのでしょうか。
(1)錯誤とは
錯誤(さくご)とは、表意者が自分でした意思表示がその真意に合致していないことを表意者が意識していない場合をいいます。簡単にいえば、勘違い(思い違い)の場合をいうといってもいいでしょう。100ユーロのつもりで100米ドルと記してしまったというのが典型例です(表示錯誤)。
これに対して、受胎している良馬であると勘違いして「この馬を買う」と申込みをしたところ、実際は駄馬で受胎もしていなかったというケースも考えられます。「馬を購入するつもりでこの馬を買った」ということからは、申込み(意思を表示する行為)と購入行為に錯誤はないともいえそうですが、「受胎している良馬」を購入するつもりだったとすれば、そういう考え(内心の意思)からは勘違いが生じています。このように、意思表示をする「動機」に勘違いがある場合(動機の錯誤)も問題となります。
(2)改正の理由
改正前民法95条本文は、意思表示は、「法律行為の要素に錯誤があったとき」(つまり、その契約に関する意思表示の重要な部分について錯誤があったとき)は、無効とすると規定していました。ここでいう重要な部分かどうかは、もしその部分に錯誤がなければ通常人はそのような意思表示をしないと思われるか否かという判断基準で決められます。また、例えば、腕時計をなくしたと思って新しい腕時計を買いましたが、実は鞄の中にあったという場合にまで錯誤の主張を認めることも錯誤の対象範囲が広くなりすぎます。
さらに、表意者(A)に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない(改正前民法95条但書)という制限を置いていました。勘違いは、表意者が著しく注意を欠いた結果であるときは、本人の責任(帰責性)が大きいためです。無効となる場合には法律行為の効果が発生しないことになります(民法119条)。
もっとも、規定が簡潔なため、解釈の余地が広く、より詳細な規定を設けるとともに、判例で認められた法理についても立法で明確にすべきであると考えられていました。そこで、前述2のような改正が行われたのです。
4.錯誤があった場合の法律効果と改正
設例Qのとおり、時計の売買契約が成立し、当事者が契約に拘束されるには、①当事者(A)が「真の納得」ができた状態で購入の意思表示をしたことが必要です。しかし他方で、②時計を購入すると伝えられた相手方(B)の信頼を保護する必要もでてきます。どのように考えるべきでしょうか。これが錯誤の問題です。
前記3の改正前民法の規定は簡潔な規定であったため、設例Qの場合に錯誤を主張できるかははっきりしませんでした。しかし、「ダイビングで使うための防水性の高い時計を購入したい」とAが述べていた等、動機が契約内容に取り込まれていた場合には、錯誤無効の対象となるとするのが判例法理でした。このような判例法理を明文化し、わかりやすい用語に書き改めて錯誤についてのルールを明確化したのが改正民法です。
設例Qでは、Aは防水性の高い腕時計と勘違いをしてそうではない時計を購入したのですから、「真の納得」がなく契約をしたといえそうです。しかし、勘違いによる意思表示は何でも無効であるとしますと、Bの「信頼」が保護されず、取引の安全が害されることになり妥当ではありません。
もっとも、改正前民法95条本文は、意思表示は、「法律行為の要素に錯誤があったとき」(その契約に関する意思表示の重要な部分について錯誤があったとき)は、無効とすると規定していました。ここでいう重要な部分かどうかは、もしその部分に錯誤がなければ通常人はそのような意思表示をしないと思われるか否かという判断基準で決められます。また、例えば、腕時計をなくしたと思って新しい腕時計を買いましたが、実は鞄の中にあったという場合にまで錯誤の主張を認めることも錯誤の対象範囲が広くなりすぎます。
さらに、表意者(A)に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない(改正前民法95条但書)という制限もあります。勘違いは、表意者が著しく注意を欠いた結果であるときは、本人の責任(帰責性)が大きいためです。無効となる場合には法律行為の効果が発生しないことになります(民法119条)。
このように、錯誤の規定内容を明確にすることで国民にわかりやすい規定になったということができます。
執筆の参考にしたサイト