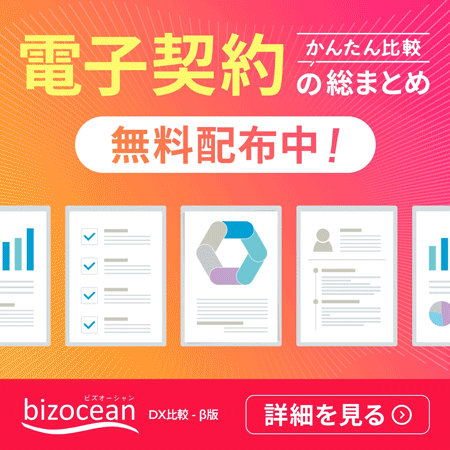ERPシステムとは? 基幹システムとの違いや導入のメリットを解説
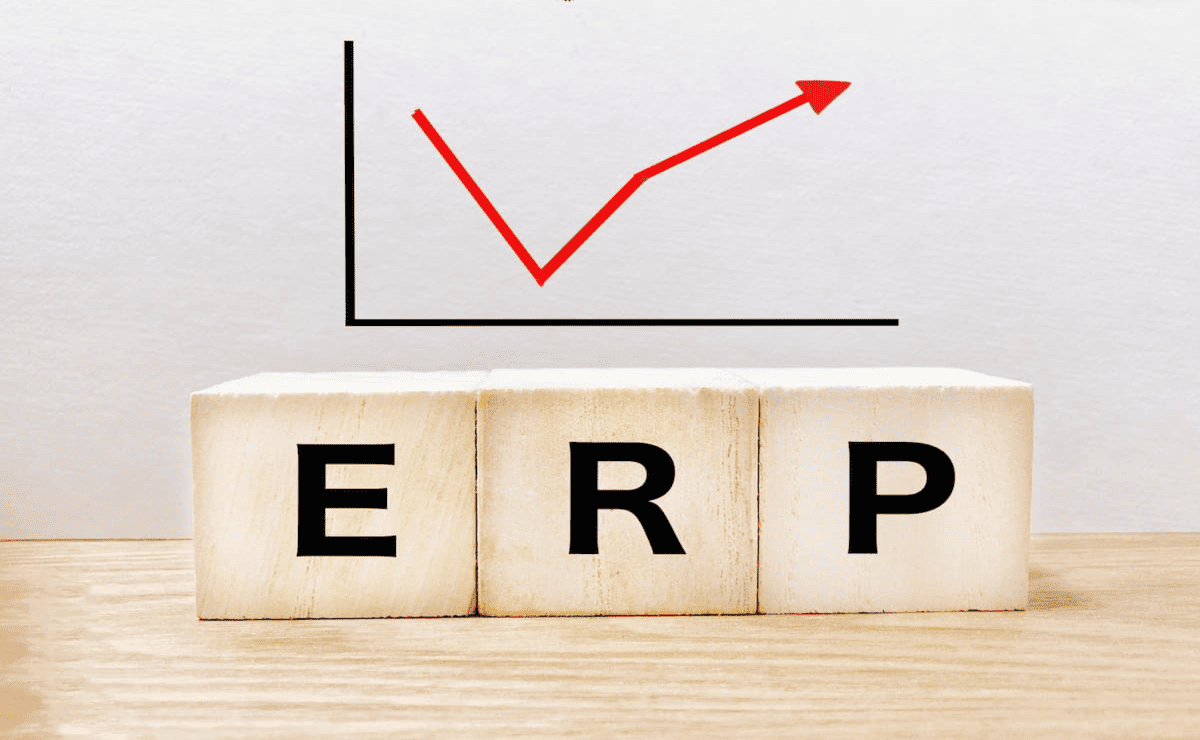
ERPシステムは企業の業務や情報を一元管理して業務効率をアップさせてくれるツールです。各業務に特化した基幹ツールよりも、連携が得意なツールとして注目が集められています。
本記事では、そのようなERPシステムの特徴から、主な機能や種類、導入メリットまで紹介していきます。
基幹システムとの違いについても解説しているので、企業の基幹業務をより統合的に管理したい担当者の方は、比較の際の判断材料として参考にしてください。
ERPシステムとは
ERPシステムは、企業の基幹業務をより効率化し、経営判断を迅速化させるためのツールです。そのようなERPシステムとは、どんなものなのかについて、まずは深く理解しておきましょう。
ここでは、以下の3つに分けて、ERPシステムについて紹介していきます。
- ERPシステムの定義と由来
- ERPシステムの特徴
- ERPシステムと基幹システムの違い
ERPシステムの定義と由来
ERPとは「Enterprise Resources Planning」の略称で、日本語では「企業資源計画」と訳されます。
ERPは、もともと生産管理の手法であるMRP(Materials Requirements Planning)から発展しました。この概念をもとに、ERPシステムは企業が保有する人材、設備、資金、情報などの経営資源を統合的に管理し、より効率的な経営を実現しようと生まれたシステムです。
従来部門ごとにバラバラに管理されていた情報資源を一元化して、情報の速さや正確さを向上させて経営の効率化を図る仕組みになっています。
ERPシステムの特徴
ERPシステムは、企業内のさまざまな情報を一元管理することを目的としたシステムです。
従来、部門ごとに管理されていた情報を統合し、リアルタイムでデータを共有・活用することで、業務効率の向上や意思決定の迅速化を実現します。
経営層は統合されたリアルタイムのデータをもとに、タイムリーな経営判断を下すことが可能になるでしょう。
ERPシステムと基幹システムの違い
基幹システムとは、企業の基幹業務を個別に管理するシステムの総称です。会計システム、人事システム、販売管理システムなどのそれぞれの業務に特化した機能を提供します。
一方でERPシステムは、これらの基幹システムを統合し、企業全体の経営資源を最適化するためのシステムです。部門や部署に関わらずデータを一元管理・活用することで、より効率的な経営を実現します。
基幹システムが部門ごとの業務効率化を目的とするのに対し、ERPシステムは企業全体での最適化を目指す点が大きな違いといえます。
|
|
最適化の範囲 |
目的 |
|
ERP |
企業全体 |
|
|
基幹システム |
各部門 |
|
ERPシステムに備わっている主な機能
ERPシステムには、幅広い業務機能が備わっています。ここではERPシステムに搭載されている、以下の主な機能について紹介していきます。
- 人事・労務管理機能
- 財務会計管理機能
- 販売・在庫管理機能
- 購買管理機能
- 生産管理機能
これらの機能を一元管理することで部門間の情報連携がよりスムーズになり、業務プロセスの最適化が可能になります。
人事・労務管理機能
ERPシステムには従業員の個人情報や勤怠データを管理し、給与計算や人事評価をサポートする人事・労務管理機能が備わっています。
採用や目標管理、教育、研修管理など人材に関わる業務を包括的に管理することが可能です。
個人情報に対するセキュリティには警戒する必要があるため、現在マイナンバー管理に特化した機能が搭載されたERPが多く登場しています。
財務会計管理機能
ERPシステムは総勘定元帳や債権・債務管理、支払処理などの会計業務を一元的に処理する財務会計管理機能もあります。
財務諸表の作成や予算管理、原価管理などを統合的に行えるため、経理関連業務の負担を大幅に減少させてくれる役割です。
また自社の経営状況をグラフや表で視覚化できるため、経営状況のリアルタイムな把握が可能になります。
販売・在庫管理機能
受注処理や出荷管理、請求・回収管理を行う販売管理機能と、在庫の入出荷や在庫評価を行う在庫管理機能を統合的に管理できる機能もERPシステムの特長です。
販売実績と在庫状況をリアルタイムに連携させることで、適切な在庫管理と販売計画の立案ができます。
購買管理機能
ERPシステムには発注処理や納期管理、検収処理などの購買業務をより効率化する購買管理機能も搭載されています。
この機能と在庫管理機能を連携すると、適切な発注量や発注タイミングを判断することが可能です。
生産管理機能
ERPシステムの製造工程の進捗管理や品質管理、原価管理を行う生産管理機能も非常に有効です。
この機能は、設備の保全管理や需要予測に基づく生産計画の立案なども含まれ、効率的な生産活動をサポートしてくれます。
ERPシステム導入のメリット
ERPシステムを導入することで、業務効率の向上から経営判断の迅速化まで、さまざまなメリットを得ることができます。
ここでは、以下のERPシステム導入による主なメリットについて紹介していきます。
- 業務効率が向上する
- 経営判断のスピードが上がる
- 内部統制を強化する
- 成功企業のノウハウを活用できる
業務効率が向上する
ERPシステムは情報の一元管理により、入力作業の効率化や部門間での連携を円滑にして業務効率を大幅に向上させます。
このシステムによってデータの重複入力や不整合を防いで、業務プロセスを自動化できるため、作業時間の短縮や人的ミスの削減が可能になるのです。
また標準化された業務プロセスが担当者による作業のばらつきを抑制し、業務効率だけでなく業務品質の向上にも貢献してくれます。
経営判断のスピードが上がる
ERPシステムによりリアルタイムな情報を把握できるため、経営層のスピーディーな意思決定につなげられます。
例えば、販売動向や在庫状況、財務データなどを即時に理解できるため、市場の変化に素早く対応した経営判断が可能です。
また統合されたデータを活用した高度な分析もできて、より精度の高い経営判断を実現できるでしょう。
内部統制を強化する
ERPシステムの持つデータの整合性と一貫性、不正アクセスやデータ漏洩の防止力によって内部統制を強化できます。
アクセス権限の設定や監査証跡の保存などのセキュリティ面での管理機能も充実しているため、コンプライアンス対策にも役立ちます。
成功企業のノウハウを活用できる
ERPシステムには、多くの企業での導入実績から得られたノウハウが組み込まれています。このような先進企業の優れた業務プロセスを自社に取り入れることで、業務改善の効果を最大化することが可能です。
また、実績から得られた知見をもとに業種や業態に応じた標準的な業務フローを提供し、スムーズな導入と運用を実現できます。
ERPシステム導入時の課題
ERPシステム導入には多くのメリットがありますが、一方でいくつかの課題も存在します。
ここでは、ERPシステム導入時における以下の課題点について紹介していきます。
- 自社にマッチしたシステム選定の必要性
- 導入後の浸透・定着率向上の必要性
- 導入コストに見合うメリットの見極め
自社にマッチしたシステム選定の必要性
ERPシステム導入では、自社の業務に適したシステムを選定することが重要です。業種や規模、業務の特性などを踏まえ、必要な機能を備えたシステムを見極める必要があります。
自社に不要な機能を持つERPシステムを導入してしまうと、かえって業務が煩雑になる可能性があるからです。自社の課題やニーズを明確にし、それに合ったシステムを選びましょう。
導入後の浸透・定着率向上の必要性
ERPシステム導入後は、従業員への教育と浸透のための施策が欠かせません。
システムを使いこなすための操作研修や、業務プロセスの変更に伴う意識改革など継続的な取り組みを行っていきましょう。
導入すれば自動的に効果が出るものではないので、現場の従業員にシステムを十分に活用してもらい業務に定着させるステップを大切にしましょう。
導入コストに見合うメリットの見極め
ERPシステムの導入コストに見合うだけのメリットがあるかを慎重に検討することも必要です。初期投資や運用コストを考慮し、中長期的な視点で費用対効果を分析することが求められます。
初期コストだけでなく、維持・運用コスト、カスタマイズや機能追加にかかる追加コストについても考慮してください。投資に見合った効果が得られるか、十分に見極めてから導入に至りましょう。
ERPシステムの種類
ERPシステムには、いくつかの種類があり、導入形態や機能性、対応範囲によって分けることができます。
ここからは、ERPシステムの各分類について詳しく解説していきます。さまざまな分類における種類について知っておくことで、ERPシステムについて理解を深めていきましょう。
導入形態による分類(オンプレミス型・クラウド型)
ERPシステムは、導入形態では、オンプレミス型(自社で管理)とクラウド型(クラウド上で利用)に分類されます。それぞれの特徴については、以下のとおりです。
|
オンプレミス型 |
|
|
クラウド型 |
|
クラウド型ERPシステムはインターネット環境さえあれば、いつでもどこでもシステムにアクセスできるため、テレワークのような柔軟な働き方にも対応可能です。
セキュリティ面での不安もありますが、クラウドベンダーのセキュリティ対策は年々強化されています。
機能性による分類(パッケージ型・フルスクラッチ型)
ERPシステムは、機能性では、パッケージ型(標準的な機能の組み合わせ)とフルスクラッチ型(一からオーダーメイド)に分類されます。
それぞれの特徴を表で確認しましょう。
|
パッケージ型 |
|
|
フルスクラッチ型 |
|
コストと開発期間を十分に見積もる必要がありますが、自社の業務に特殊な要件がある場合は、フルスクラッチ型の選択も検討してください。
パッケージ型でもある程度のカスタマイズは可能なので、自社に合った柔軟な設定を探ってみるのも一案です。
対応範囲による分類(統合型・コンポーネント型)
ERPシステムは対応範囲において、以下のような統合型(すべての業務を一元管理)とコンポーネント型(必要な機能のみ利用)に分類されます。
|
統合型 |
|
|
コンポーネント型 |
|
統合型は、企業全体の業務を一元的に管理できるメリットがある一方、導入コストが高くなる傾向にあります。
コンポーネント型は、自社に必要な機能だけを選んで導入できるため、コストを抑えられますが、統合し最適化するという視点が弱くなりやすい点に注意が必要です。
ERPシステムの選び方
ここまでは、ERPシステムについての理解を深めてきましたが、自社に適したERPシステムを選ぶことで、それらの効果を最大限発揮できます。
以下では、ERPシステムを選ぶときのポイントについて詳しく解説します。
- 費用対効果を見極める
- 自社に必要な機能を確認する
- セキュリティ対策を評価する
- 自社と近い業種・規模での導入実績を参考にする
- サポート体制の充実度をチェックする
費用対効果を見極める
ERPシステムの選定では、導入・運用コストと得られるメリットを比較検討することが重要です。
業務の効率化や意思決定の迅速化による定量的・定性的な効果を見積もり、投資対効果を慎重に判断していく必要があります。
コスト面では初期導入費用だけでなく、ランニングコストも考慮することが重要です。ライセンス費用や保守費用、システム更新費用など、中長期的な視点でトータルコストを見積もることが求められます。
自社に必要な機能を確認する
ERPシステムの選定では、自社の業務内容や課題に適した機能を備えているかを確認しておく必要があります。
そのためには、現状の業務フローを分析し、改善すべきポイントを具体的に洗い出した上で、システムに求める要件を明確化していきましょう。
このときは必須の機能と、なくてもいい機能を分けて整理します。もし自社に不要な機能まで導入してしまうと、業務が複雑化する可能性があるからです。
セキュリティ対策を評価する
ERPシステムの選定では、アクセス権の管理やデータ暗号化などのセキュリティレベルを吟味し評価することが重要です。
ERPでは企業の経営資源のすべてを管理するため、情報漏洩や不正アクセスなどのリスクを最小限に抑えてください。
クラウド型のERPシステムを選ぶ際は、クラウドベンダーのセキュリティ対策を確認することが不可欠です。
自社と近い業種・規模での導入実績を参考にする
ERPシステムの選定では、自社と類似した企業での成功事例を参考にすることが有効です。
同業他社の導入事例を調査し、システム導入によってどのような効果が得られたかを分析しておくことで、自社で効果的に活用できます。特に自社と同規模の企業での導入実績を参考にしてください。
規模が近いということは、業務の複雑さや課題の傾向が似ていることが多いため、実際の導入事例から学んで自社に合ったシステム選定につなげましょう。
サポート体制の充実度をチェックする
ERPシステムの選定では導入支援や問い合わせ対応など、長期的なサポート体制の充実度を確認することが重要です。
システムの安定稼働と継続的な改善を実現するには、ベンダーの手厚いサポートが欠かせません。
具体的には、以下のようなサポート支援があるか確認します。
- 導入時の教育やマニュアル提供
- 運用開始後の問い合わせ対応
- バージョンアップ時のサポート
ベンダーとの長期的なパートナーシップを築ける体制があるかどうかは、ERPシステム選定時の重要なポイントになります。
ERPシステム導入の流れ
それでは、最後に、実際にERPシステムを導入する時にはどのような流れで進めていくのかについて説明します。
ERPシステムは、以下のようなステップで段階的に導入していきます。
- 導入目的を明確にする
- 導入プロジェクトを立ち上げる
- 業務フローを棚卸する
- 新たな業務フローを策定する
- 試験導入を行う
- 本導入を実施する
1.導入目的を明確にする
まずは、ERPシステム導入によって実現したいことを明確化することです。
例えば、業務の効率化や業績の向上など具体的な目的を設定し、その達成に向けた計画を立案しましょう。
導入目的を明確にしておくことで、システムに求める要件も明らかになり、適切なシステム選びにつながります。
2.導入プロジェクトを立ち上げる
ERPシステム導入では、社内の担当者を決めてプロジェクトチームを結成しましょう。経営層や現場の従業員を巻き込むことで、同意を得た上で綿密な導入計画を策定することができます。
プロジェクトチームには、現場の管理に関与している人をできる限り選んでください。実際の現場での知識や課題を持ち寄ることで、より実現可能な視点でシステム要件を定義できます。
3.業務フローを棚卸する
ERPシステム導入前に、現在の業務フローや管理方法を洗い出してください。現行業務の課題や非効率な部分を特定し、改善の余地を探りましょう。
業務フローの棚卸は、現場の担当者へのヒアリングや、業務マニュアルの分析などから行います。
現状の業務を可視化することで、システム化によって解決すべき課題や優先順位を明らかにすることが重要です。
4.新たな業務フローを策定する
ERPシステム導入では、システムを活用した新しい業務フローを検討・策定する必要があります。
ここでは現場の意見を積極的に取り入れながら、自社にとって最適な業務プロセスをデザインしていきましょう。
新たな業務フローの策定では、現行業務の課題解決だけでなく、業務の標準化や効率化も視野に入れることが大切です。
5.試験導入を行う
ERPシステムの本格導入前に試験的に運用し、問題点を洗い出すことが望ましいです。データ移行や操作性など、実際の運用を想定したテストを実施し、必要な改善を施しましょう。
試験導入では、一部の部門や業務に限定して行うのが一般的です。
課題や改善に向けて重点的に取り組める環境で、段階的に範囲を広げつつ、システムの安定稼働と業務への適合性を確認していくことが求められます。
6.本導入を実施する
ERPシステムの本導入では、従業員への教育やマニュアル整備を行いながら本格運用を開始します。本導入では、トラブルへの迅速な対応と、システム活用の定着化が重要なポイントです。
まずはユーザー部門とIT部門が連携し、課題の早期発見と解決に努めましょう。そして安定稼働に向けた支援体制を整え、システム定着率の向上と継続的な改善活動を行うことが大切です。
ERPシステムで企業の経営基盤を強化しよう
ERPシステムは企業の基幹業務を統合的に管理することで、業務の効率化と経営判断の迅速化を実現します。
そのためERPシステムの導入は、単なるIT投資ではなく、業務プロセスの改革と、経営基盤の強化につながる戦略的な取り組みです。
ただし導入と運用には、コストや労力がかかることも忘れてはいけません。
自社の経営課題に向き合い、中長期的な視点でERPシステムを効果的に活用することで、企業の競争力強化と持続的な成長を実現していきましょう。