配当性向とは? 計算方法や目安をわかりやすく解説!
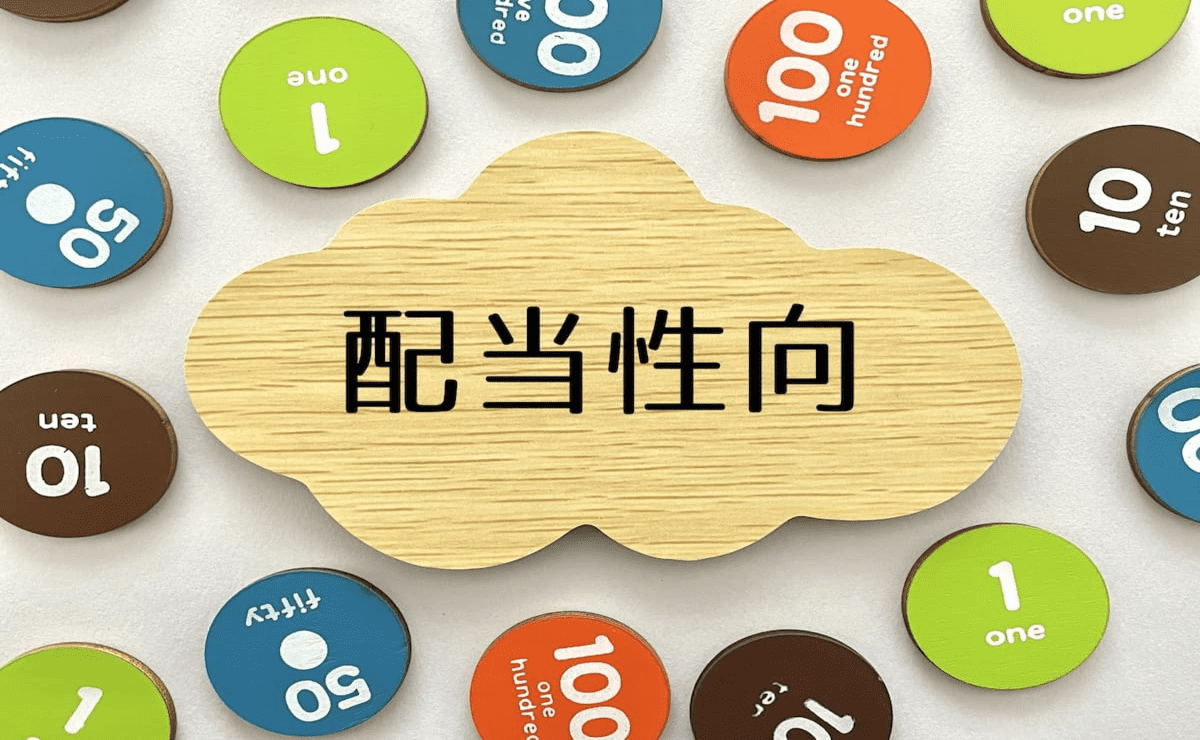
配当性向(はいとうせいこう)とは、会社の利益がどのくらい株主に還元されているかを見るための指標です。配当性向値が高ければ、株主への利益還元率が高い企業と言えます。
最近注目されている高配当株への投資を考えている投資家にとって、配当性向は銘柄を選ぶうえで重要な数値です。また、企業の利益配分に対する考え方を知る手がかりにもなります。
この記事では、配当性向の意味や計算方法、目安について徹底解説します。

配当性向とは
まずは、配当性向の意味や数値からわかることを解説します。
投資で重視される「利回り」が投資金額に対する収益を知る目安になるのに対して、配当性向は投資家(株主)に対する企業の姿勢を知る手がかりになります。
配当性向の意味
配当性向とは、企業の純利益から配当金をどれくらい支払っているか割合を示した数値で、株式投資をする際に参考とする指数の一つです。
配当性向の数値が高ければ、株主への利益還元率が高い企業と言えます。配当性向は、高配当株への投資を考えている投資家にとって、銘柄を選ぶ際に参考となる数値です。
配当性向の数値からわかること
配当性向の指数の高低からわかることは、企業の株主に対する利益配分の考え方です。
配当性向の数値が高ければ、より多くの配当金が受け取れるというわけではありません。あくまでも「企業の利益の中からどれだけ株主へ還元するか」という、企業姿勢を知ることができる数値です。
たとえば、配当性向が低くても、大きな利益を生み出している企業の株主は、多くの配当金を受け取ることができます。
逆に、配当性向が高い企業でも、少ない利益しか出せない場合は配当金が少額になるという仕組みです。
また、成長期にある企業は、利益をさらなる成長のための投資に多く配分する傾向にあり、配当性向が低くなっている可能性もあります。
その場合は、投資によって企業が成長し、より多くの利益を出すことができれば、将来の増配につながるかもしれません。
配当性向の求め方|2つの計算式
配当性向を求める計算式は2つあります。いずれのケースでも当期純利益がベースの数字となり、どちらの式を用いても結果は変わりません。
当期純利益を用いた計算式
配当性向は、企業の当期純利益の総額と配当金総額を用いて計算します。
配当金の総額を、その時期の企業の純利益総額で割り返すことで算出された割合が、配当性向です。配当金がゼロの場合は配当性向もゼロとなります。
配当性向の計算式は次のとおりです。
配当性向(%)=配当金支払総額÷当期純利益×100
例:当期純利益が1,000億円の企業が、配当金を総額300億支払った場合
配当性向=300億÷1,000億×100=30%
1株あたりの利益を用いた計算式
1株あたりの純利益と1株あたりの配当金を用いて、配当性向を計算する方法もあります。1株あたり配当額を1株あたり当期純利益で割ることで、配当性向の数値を求めます。
計算式は次のとおりです。
1株あたり配当額÷1株あたり当期純利益×100(%)
例:1株あたりの当期純利益が100円の企業が、1株あたり年間の配当額を30円支払った場合
配当性向=(30円÷100円×100)=30%
東京証券取引所が提示する決算短信の作成要領では、この1株あたりの利益を用いた計算式となっています。
なお、配当金支払総額と当期純利益を、発行済株式総数で割ると、それぞれ1株あたり配当金と1株あたり利益となるため、前述の式と計算結果は同じです。
配当性向の目安の数値
ここでは、配当性向の数値の目安を解説します。
配当性向は100%以上になることもあり、その場合に考えられる理由や懸念事項なども併せて紹介します。
配当性向の適正な目安数値は30%前後
企業の成熟度合いで株主の配当に回せる割合は異なりますが、企業の利益を株主・社員・企業自身の3者間で分け合うと考えるなら、30%以上が一つの目安です。
実際、社団法人生命保険協会「平成29年度生命保険調査」による日本企業の配当性向の推移によると、TOPIX構成企業の配当性向は、おおむね30%前後で推移しています。
会計期間の会社の売上から経費を引いた「当期純利益」は、配当金として株主に還元するほか、企業の財務を安定させるためのキャッシュとして内部留保となります。
儲けのすべてを株主に配分せずに、翌年以降の投資資金や赤字になってしまった時の補充用資金として、企業の内部に残しておきましょう。
配当性向が100%以上になる理由
配当性向が100%以上、つまり、当期純利益以上に配当金を出している状態は、利益が減ったにも関わらず、配当金の引き下げをしなかった場合などに起こります。
たとえば、これまで1株あたりの当期純利益が100円だった企業が、一時的な要因で20円になったとします。
1株あたりの年間配当金が30円で、減益後も配当金30円を維持した場合、配当性向は150%(30円÷20円×100)となり、100%を超えます。
企業は、「安定的に配当金を出し続けることで株主に長期に保有してもらいたい」と考えます。株価は長期保有によって安定するからです。
配当金の維持は、配当金目的の株主が株を売却してしまうことを防ぎ、株価の下落を防止する目的があります。
また、株価が下落すると企業買収のリスクが高まるため、配当を据え置くという理由もあります。
【配当性向が100%以上で安全なケース】
配当性向が100%を超える状態は健全な状態とはいいにくいですが、その状況が一時的なものであり、早期に業績の回復が見込まれる場合には心配ないと考えられます。
前述のように株価下落防止策として目的を持って実施している場合や、企業の財務状況が健全で、これまで内部留保をしっかり蓄積してきた、キャッシュリッチな企業であれば問題ないでしょう。
【配当性向が100%以上でリスクが高いケース】
配当性向100%以上の状態が続いている企業には注意が必要です。今後も同じように利益が上げられない状態が続けば、突然減配もしくは配当金0円となる恐れがあります。
また、資金が潤沢にない場合、継続して配当金を出し続けること自体不可能です。企業業績のみならず、財務状況も確認が必要です。
配当性向がマイナスの場合
配当性向がマイナスになっているという状況は、当期純利益がマイナスになっているにも関わらず、配当金を出している状態ということです。当期純利益がないため、配当金として支払う原資はこれまでの内部留保となります。
配当金が減る、もしくは0円となる恐れがあるうえに、赤字の状態が続けば株価の値下がりリスクがあり、最悪の場合は企業の存続にも関わります。
赤字の理由が短期的な理由であれば、そこまで心配する必要はありませんが、継続するようなら、投資対象から外すことを検討したほうが賢明です。
配当性向値が高い企業へ投資の目安
配当性向に注目して株式投資を行う場合、次のようなポイントが挙げられます。
- 企業の収益が増えているか
- 株主への利益還元にどれだけ積極的か
また、上記に着目する際に留意すべき点などについても、併せてご紹介します。
企業の収益が増えているか
配当性向は、企業の配当性向を一定とした場合、当期純利益の金額が大きければ支払われる配当金額も大きくなります。
当期純利益の金額は、売上高から費用や税金等を差し引いた額で、1年間の企業活動の結果、株主にもたらされた最終的な利益の額です。
増収つまり、売上高が増えている状態が続いている企業であれば、純収益の額(配当可能な金額)も大きくなっている可能性があると言えるでしょう。
ただし、収入が増えても企業の収益が減る場合があります。たとえば、円安による輸入原材料費の高騰などで原価が増えたり、賃金の高騰などで人件費が増えたりするなど、費用がかさむ場合です。
また、営業外で特別な損失が出たなど、状況によっては、増収減益となる可能性もあります。そのため、売上高の伸びだけでなく、企業の財務状態や収益モデルを分析することが重要です。
株主への利益還元にどれだけ積極的か
配当性向とは、株主に対する利益還元の企業姿勢(積極性)を示します。利益の規模が同程度の会社を比較する場合、配当性向が高い要因もしっかりと分析してみるとよいでしょう。
一般的に成長期にある企業は、株主に利益を還元するよりも、利益を再投資へ回すほうを優先するため、配当性向が低くなる傾向があります。
一方で、成熟企業は、株主への利益還元を重視し、配当性向が高くなる傾向が強いです。
そのため、現時点で配当性向が高いかだけでなく、企業の将来性も加味して投資先を決める必要があります。
また、配当性向が高い企業は、再投資に回す利益が少ないことや、内部留保が少ないため、不測の事態に陥った時に、借入金に頼る可能性があります。
配当性向が高い企業への投資には、その企業の財務状況や市場環境を分析・評価することが重要です。
配当性向についてのまとめ
配当性向の意味や計算方法、目安について解説しました。配当性向は30%を一つの目安にしましょう。
数値がマイナスの場合は、配当金の原資が内部留保からとなっているため、赤字の理由が短期的な要因であるかを確認することが大切です。
配当性向の数値は、高ければよいというものでもありません。極端に数値が高い場合は、その状態がどのくらい続いているかを確認することが大切です。
一時的に数値が高くなっている場合は問題ないケースが多いですが、利益が上げられない状態が続けば、突然減配もしくは配当金0円となる恐れもあります。
企業の現状をしっかりと見極めて、投資先を検討しましょう。

