折衝(せっしょう)とは? ビジネスでの使い方や「折衝力」についても詳しく解説!
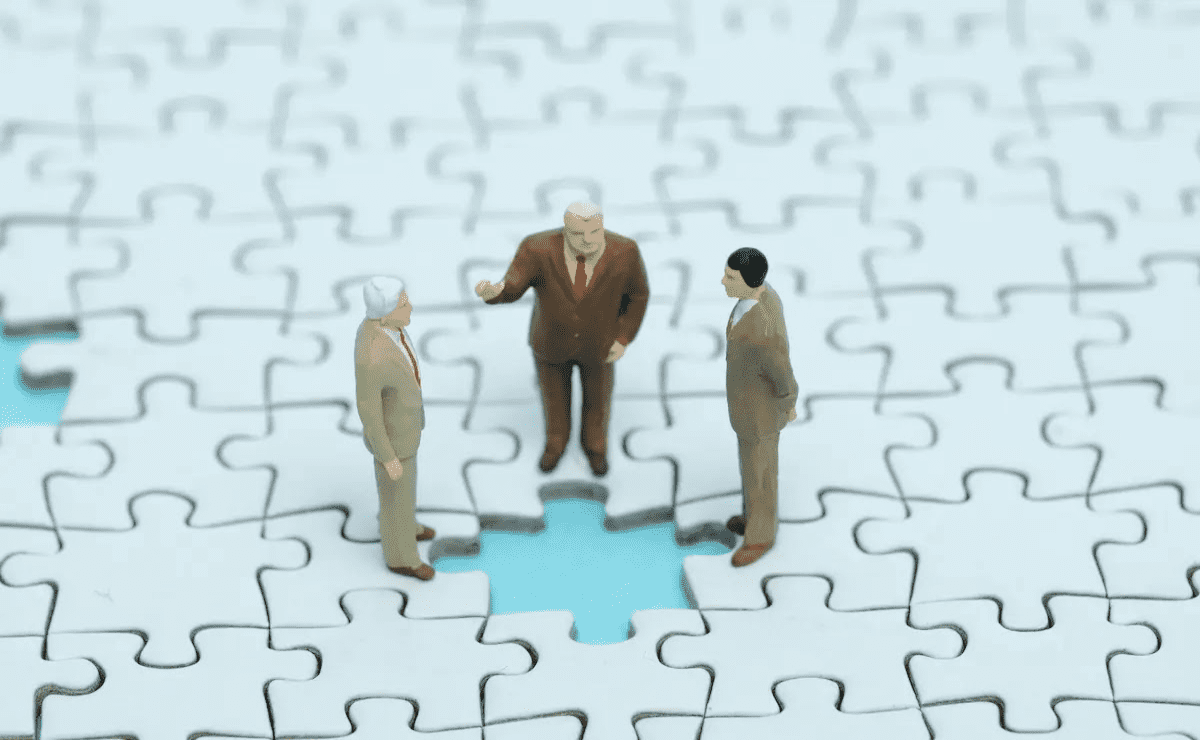
折衝(せっしょう)とは、利害が一致しない相手と話し合い、双方が納得できる解決策(落とし所)を導き出すことです。
単なる「交渉」とは異なり、お互いの利益を考慮しながら折り合いをつける高度な駆け引きを指します。
「交渉と何が違う?」「どうすれば折衝力を鍛えられる?」と悩む方も多いはず。
本記事では折衝の意味や使い方、能力を高める習慣を詳しく解説します。読めば、上司や顧客から信頼される「調整のプロ」への一歩が踏み出せます。
【この記事のポイント】
- 折衝とは、利害が一致しない相手と問題解決や要求の擦り合わせを行い、双方が納得できる結果を目指す駆け引きであり、ビジネスや外交など幅広く用いられる。
- ビジネスにおける折衝力は、自社の利益を確保しつつ相手も納得できる着地点を見極め、取引や関係構築を円滑に進めるために重要な能力である。
- 折衝力を高めるには、話の構成を意識し、代替案をいくつか事前に準備し、相手の主張をよく聴き、上司からのフィードバックを受ける習慣が有効である。
【関連記事はこちら】
折衝とは?
ここでは折衝の意味や似た言葉との違いについて紹介します。
折衝の意味
折衝は(せっしょう)と読みます。折衝は、主に利害が一致しない相手を対象に、問題解決やお互いの要求の擦り合わせを話し合いなどで行うという意味があります。
双方の要求を踏まえてお互いが納得できる結果を目指すための駆け引きなどを指し、ビジネスだけでなく外交においても使用される言葉です。
折衝と似た言葉との違い
折衝には似た言葉がいくつかありますが、それぞれの単語との違いを紹介します。
「交渉」と「折衝」の違い
「交渉」と「折衝」は意味が似ていますが明確な違いがあります。
「交渉」は利害関係に関係なく使用する言葉です。それに対して折衝は利害が一致しない際に使われる言葉なので、利害関係によって選ぶ単語が変わります。
また、一般的には正式な協議の場では折衝が用いられ、個人間の話し合いなどには「交渉」が用いられます。
「談判」と「折衝」の違い
「談判」は、事件やもめごとなどのトラブルに決着をつけるために話し合うという意味があります。
「折衝」と似た意味合いに見えますが、「談判」はトラブルの決着をつける話し合いで、利害を一致させる駆け引きではありません。
「談判」と「折衝」には、目的や使われるシーンに違いがあります。
「渉外」と「折衝」の違い
「渉外」は外部と連絡をとり交渉や折衝を行うという意味があります。外部との連絡という点がポイントで、社外や外国の相手との交渉にのみ使う言葉です。
外国の会社と取引の多い業種などでは、渉外担当が存在します。
ビジネスでの折衝の使い方と例文
ビジネスシーンにおいての折衝は、企業間に生じた問題を解決するための協議をあらわすことが多いです。対象になるのは、主に社内の関係者や取引先、顧客などがあげられます。
企業間で利害が一致しない際や問題が生じた際に解決を目指し、「折衝する」「折衝が行われる」と表現するケースが多いです。
実際にビジネスシーンでよく使われる例文は次のとおりです。
- 「先日発生した問題について、〇〇社と折衝が行われるみたいだ」
- 「顧客と折衝を繰り返したおかげで問題が解決した」
- 「〇〇の商品について、先方と折衝を行う予定だ」
折衝を使った言葉
ここでは、折衝を使った言葉を3つ紹介します。
対人折衝
「対人折衝」とは、物事を有利に進めるための人間関係における駆け引きを指します。
ビジネスに限らずさまざまなシーンで使われる言葉です。
折衝業務
「折衝業務」は、折衝を仕事で行うという意味です。
顧客と折衝を行う人を顧客折衝という役割で呼ぶケースもあり、「これから顧客との折衝業務がある」などと表現できます。
折衝業務では双方の利益を考慮して話を進める必要があるため、うまくまとまらずに長引くケースも多いです。
折衝力
「折衝力」とは、その名のとおり折衝を行う能力のことで、最終的にどこに落とし所を持っていくか、どのように折り合いをつけるかなどの意味を持ちます。
自社や自分が有利になる提案をしつつ、双方が納得できる提案をする能力が必要です。
ビジネスに必要な折衝力とは?
折衝力はビジネスにおける対人スキルの1つとして身につけておきたいところです。
ここでは、なぜ折衝力が必要なのか、どのような職業で求められるかなどを紹介します。
折衝力がビジネスで必要な理由
ビジネスでは、お互いがWinWinの結果になるように話し合いを行うことが重要です。双方が納得できるラインを見極めることで、クレームやトラブルなどの回避にもつながります。
折衝力があると自社の利益を確保しつつ、お互いが納得できる着地点を見つけられるので、取引において重要な能力です。
折衝力の高い人の特徴
折衝力の高い人には、次のような特徴があります。それぞれの特徴をみていきましょう。
自分の要求を分かりやすく伝えることができる
折衝力が高い人は、自分の要求を分かりやすく伝える力があります。お互いの要求が分かりやすいと、問題解決のための話し合いがスムーズになり、最終的な落とし所を探りやすくなります。
自分の要求や状況を分かりやすく伝える能力は、折衝に欠かせません。
客観的な視点で物事を見ることができる
客観的な視点で物事を見ることができるのは、折衝力が高い人の特徴です。
折衝ではお互いが利益を確保するために駆け引きを行います。
駆け引きの場において、客観的な視点で冷静に物事を考える力は重要です。相手の立場になって状況を客観的に見ることで、適切な提案や妥協点を導き出せます。
状況に合わせた代替案を提案することができる
状況に合わせた代替案を提案できるのも、折衝力がある人の特徴です。
話し合いの妥協点が見つからず折り合いがつかない際に、他の代替案を具体的に提案できると、問題が解決する可能性があります。
特に、相手の反応などをみながら具体的な案を提案できると、折衝がスムーズに進むでしょう。
折衝力を活かせる業種
折衝力はビジネスシーンにおいて非常に役立つ能力です。ここでは、その中でも特に折衝力を活かせる業種を紹介します。
営業職
営業職は折衝力を活かせる職業の1つです。相手の要求を理解して飲み込みつつも、自社の利益も考える必要があるため、双方の妥協点を提案する駆け引き能力に折衝力が役立ちます。
顧客に納得してもらいながらも、どちらにとっても利益があるラインを見極めるためには折衝力が欠かせません。
接客業
折衝力が活かせる職業として接客業があげられます。
接客業において折衝力が高いと、他のスタッフと差別化ができるだけでなく、自社の利益にも貢献できます。
特にクレーム対応などにも効果的で、顧客の意見を聞きつつ解決策を提案できる折衝力があると、トラブルの予防が可能です。
システムエンジニア
システムエンジニアは、コミュニケーション能力が求められる業種の1つで、折衝力が重要な職業と言えるでしょう。
システムエンジニアは、作業内容や必要な費用などを、専門用語を使わずに顧客のニーズを踏まえて提案する必要があります。
顧客から一方的な予算や期間を要求された際などに、折衝力がなければ適切な提案ができずトラブルに発展するケースもあるでしょう。
折衝力を身につけるための習慣
さまざまなシーンで重要な折衝力ですが、どのように身につければよいか疑問に思う人もいると思います。ここでは、折衝力を身につけるための習慣を4つ紹介します。
日頃から話の構成を意識する
日頃から話の構成を意識すると、折衝力を鍛えられます。
話の構成とは、どのような順序で物事を伝えたら相手がわかりやすいかなど、会話の組み立てを指します。
普段の会話から、自分の話したい内容を端的にわかりやすく伝える意識を持つのが重要です。話の構成を考えるときは、結論から伝えるPREP法を活用してみましょう。
会議やミーティングの場面では、議事録をつけると話の構成を考えやすくなるので試してみてください。
代替案をいくつか事前に準備しておく
折衝や交渉など話し合いの機会がある際に、あらかじめ代替案を準備する習慣もおすすめです。
複数案用意しておくことで、相手が妥協できるラインが探りやすくなります。
また、日頃から複数案を考えていると、とっさのタイミングで代替案の提案をすることも可能です。常に代替案を事前に準備する習慣を身につけましょう。
相手の主張をよく聴く
相手の主張をよく聴くことは、折衝力の向上につながります。
折衝では、相手の主張をよく理解して、双方が納得できる着地点を探すのがポイントです。
そのため、相手の主張を聴けなければ適切な提案を行えません。日頃から相手の主張を聴く習慣があると、折衝がスムーズに進むでしょう。
まずは相手の話に相槌をうち、適度に質問をする意識を持って話を聞いてみてください。
上司からフィードバックをもらう
折衝力を高めるには、上司からフィードバックをもらう習慣が効果的です。
フィードバックは相手の気持ちや要望を理解できるため、相手が求めている内容を把握できます。
自分に足りない能力を客観的に理解できるというメリットもあるため、積極的にフィードバックをもらいましょう。
まとめ
折衝は利害が一致しない場合に、双方が納得する形で最終的に落とし所を見つける駆け引きです。
ビジネスシーンにおいて顧客や取引先などとの話し合いなど、さまざまなシーンで折衝力が求められます。
折衝力が高いと取引をスムーズに進められ、自社の利益を確保しつつ顧客満足度の向上が期待できるなど、会社にとって重要な人材になれます。
日頃の習慣を意識して折衝力を高めましょう。
【関連記事はこちら】


