協調性はなぜ大事? 意味と必要性、高め方についても解説!
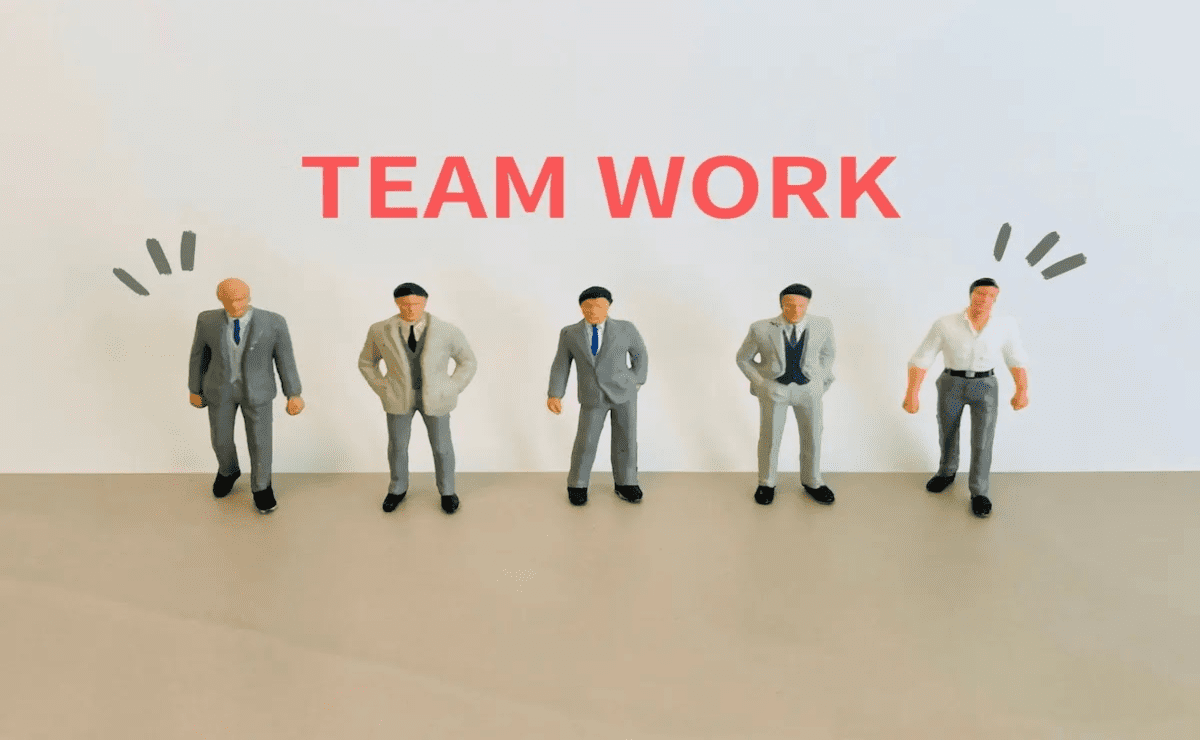
ビジネスパーソンなら「協調性が大事」と一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
でも、協調性がなぜ大事か、「協調性がある人」とはどのような特徴があるのかを具体的に説明できるかと言われたら難しいのではないでしょうか。
この記事では、協調性の意味やビジネスシーンで協調性が必要な理由、協調性がある人の特徴などについて解説します。
企業が従業員の協調性を高める方法についてもあわせて紹介するので、「協調性はなぜ大事か言語化できない」「協調性の高め方を知りたい」という方は、ぜひお読みください。
協調性とは?
協調性とは「立場や意見が自分と異なる人たちと協力して、共通の目標を達成するために行動する力」を意味します。
ビジネスシーンでもプライベートでも、多様な人たちの中で生活する以上、意見や立場の違いは避けられません。スムーズにコミュニケーションをとるためには協調性が必須です。
協調性と似た言葉に「イエスマン」がありますが、協調性とは意味が全く異なります。
イエスマンは自分の考えを押し殺してでも多数派に合わせる人を指す一方、協調性は自分と他人の考えをすり合わせて行動する力を指します。
ビジネスシーンで協調性が必要な理由
ビジネスシーンでは協調性が求められます。その理由は以下の5点です。
- 風通しの良い職場づくりのため
- 円滑なコミュニケーションのため
- 適切な役割分担のため
- 企業の理念が浸透しやすくなる
- 仕事が進みやすくなる
一つずつ詳しく解説します。
風通しの良い職場づくりのため
ビジネスシーンで協調性が必要な理由は、風通しの良い職場づくりのためです。
協調性がある人は、他人の意見を聞いて行動するため、周りの人が意見を出しやすい雰囲気になります。
役職を持つ人や新入社員など年次や立場にかかわらず、会議や打ち合わせで意見を出しやすくなると、新しいアイデアの創出や社員のモチベーション向上につながります。
円滑なコミュニケーションのため
円滑なコミュニケーションのためにも、ビジネスシーンで協調性が必要です。
社員に協調性があると、普段から上司や同僚と対話しているため「話を聞いてもらえる」という安心感が生まれます。
取引先でのトラブルや顧客からのクレームなど、報告しにくいことが発生した場面でもスムーズに報告でき、早急な対応が可能です。
また、円滑なコミュニケーションを図れると、良い人間関係を構築できます。
良好な人間関係は、社員のモチベーション向上やスムーズな業務遂行につながり、企業にとってメリットが大きいといえます。
適切な役割分担のため
協調性は、適切な役割分担のためにも必要です。協調性がない会社では、他人と分担して協力する空気が生まれず、業務の重複や無駄が増えて生産性が下がってしまいます。
社員に協調性があると、役割分担を決めるためのコミュニケーションがスムーズに行えるため、適切な役割分担で業務を行うことが可能です。
役割分担をした後も周囲の動きに目を向け、役割分担の修正やサポートが必要な場合にも対応できます。
企業の理念が浸透しやすくなる
企業の理念が浸透しやすくなることも、ビジネスシーンで協調性が必要となる理由です。
企業が目標を達成するためには、「何を目的に事業を行っているか」という理念やビジョンを従業員全員で共有する必要があります。
協調性がある人は、理解力や共感力が高いため、企業の理念やビジョンへの理解も早い傾向にあります。
協調性のある人が理念やビジョンに沿って業務を行うことで、企業の理念が社内に浸透しやすくなるでしょう。
仕事が進みやすくなる
ビジネスシーンで協調性が必要な理由として、仕事が進みやすくなることが挙げられます。
仕事を進めるためには、部内や他部署とのコミュニケーションが必須です。
意見の対立が起きた場合、協調性がない会社ではそれぞれが意見を出し合うだけになり、仕事が前に進みません。
社員に協調性があると、相手と対話を重ねて妥協点を見いだすなどスムーズなやり取りができるため、仕事が進めやすくなります。
ビジネスシーンで求められる協調性とは?
ビジネスシーンで求められる協調性はどのような力なのでしょうか。
企業が求める協調性と従業員の考える協調性には、ギャップがある場合があります。
例えば、採用面接で応募者が「私は協調性があります」とアピールするとき、企業と応募者が同じ協調性をイメージしているとは限りません。
ここでは、企業が求める協調性と従業員の考える協調性を説明します。
企業が求める協調性
企業が求める協調性は、当然「企業が利益を上げるために他人と協力して行動できる力」です。
従業員が和気あいあいと働くだけではなれ合いになり、企業に利益をもたらすことはできません。
多様な人が集まった企業という組織の中で、社員が企業にとってプラスになるよう行動できる力が求められます。
具体的には、企業が求める協調性は以下の2つの力です。
- 周囲のサポートをする力
- 組織のために行動する力
周囲のサポートをする力
企業は協調性として周囲のサポートをする力を求めています。企業には性格や得手不得手が異なる社員が集まっており、すべての社員がスムーズに業務を行えるとは限りません。
新入社員や異動してきたばかりの社員など、サポートが必要な社員を放置すると、業務が滞るだけでなく社員のモチベーションが下がってしまいます。
協調性のある社員が増えて周りをサポートすると、業務がスムーズに進み、企業全体の生産性を上げることが可能です。
組織のために行動する力
企業は、組織のために行動する力を協調性として求めています。
企業が掲げる理念やビジョン、目標の達成には、すべての社員が協力して行動することが不可欠です。企業に所属する以上、一人で完結する業務はほとんどありません。
ときには組織のために、自分と違う意見を受け入れなければならない場面もあります。個人の利益ではなく、組織の利益を優先して行動できる力を企業は求めています。
従業員の考える協調性
従業員の考える協調性として、周囲と円滑にコミュニケーションできる力をイメージする人が多いでしょう。
業務をスムーズに進めるためには、円滑なコミュニケーションが重要です。日頃からスムーズなコミュニケーションができていると、目標や仕事の進捗の共有、役割分担の明確化など、企業にとっても多くのメリットがあります。
ただし「人に合わせるのがうまい」「他人と仲良くなるのが早い」などは、従業員として協調性があるとはいえません。他人に迎合するだけでは、組織の士気を下げる可能性もあります。
協調性がある人の特徴
ビジネスシーンで協調性がある人を増やすためには、協調性がある人の特徴を理解することが重要です。
「協調性がある人」をなんとなくイメージできても、具体的に説明するのは難しい人が多いでしょう。
協調性がある人の特徴は、主に以下の4点です。
- 洞察力が優れている
- 傾聴できる
- 相手の立場に立って考えることができる
- ポジティブな考え方ができる
一つずつ具体的に解説します。
洞察力が優れている
協調性がある人は、洞察力が優れています。他者とスムーズなコミュニケーションを図るために周囲を観察する必要があるためです。
「相手がどのような役割を担っているのか」「相手が求めているのは何か」などを瞬時に判断して、その場に必要なコミュニケーションを図ります。
洞察力に優れているため、初めて参加する会議や打ち合わせでも、決定権を持つ人を瞬時に判断して議論を進めることもできます。
傾聴できる
協調性がある人は、傾聴できる人です。傾聴とは、相手の話をしっかり「聴き」、相手への共感や信頼を示すことを意味します。
協調性がある人は、自分の意見がありながらも、それを主張しすぎることなく、相手の意見にしっかりと耳を傾けます。
最後まで相手の話を否定せずに聞くため、周りからの信頼も厚く、取引先や顧客から好印象を持たれることも多いでしょう。
取引先や顧客と良い関係を築けるため、企業や個人としての成果も期待できます。
相手の立場に立って考えることができる
協調性がある人は、相手の立場に立って考えることができます。
例えば、相手が自分と違う意見を持っているとき、協調性がある人が考えるのは「相手がこの意見を持つのはなぜなのか」です。
相手が置かれた立場や担っている役割、状況を考えた上で、対応しようと考えます。そのため、意見がぶつかってもうまく着地点を見いだし、スムーズに物事を進めることが可能です。
ポジティブな考え方ができる
ポジティブな考え方ができるのも、協調性がある人の特徴です。
相手の話を否定せずに聞くため、相手の話をふまえてポジティブに物事を変換できます。
また、普段から他者とコミュニケーションをとって物事を進める経験が豊富なため、笑顔が多く、周囲に自然と人が集まる太陽のような存在ともいえます。
ポジティブに考える人が多い組織では意見を出しやすいため、イノベーションも生まれやすいでしょう。
協調性がない人の特徴
協調性がない人の特徴が協調性のある人と逆だとすると、「周りを観察しない」「相手の話を聞かない」「自分のことしか考えない」「ネガティブに考える」となります。
これをさらに深掘りして、協調性がない人の特徴を以下の4つの視点から解説します。
- プライドが高い
- 融通が効かない
- 自分の意見を無理に押し通す
- 個人プレーが多い
プライドが高い
協調性がない人はプライドが高いといえます。プライドとは保身です。
トラブルやミスが起きたときに、「なぜこのトラブルが起きたのか」「どうすれば防げたか」を周りと話し合うことなく「自分は悪くない」と考えます。
また「自分が正しい」という考えが強いため、他人の意見を聞かずに物事を進める傾向もあります。
チームで業務を進める場合には、保身に走る人がいるとチームワークを乱すため、組織の士気も下がってしまうでしょう。
融通が効かない
協調性がない人は、融通が効かないことも特徴です。
「自分が正しい」という考えが強いため、固定概念にとらわれやすく柔軟な考え方ができません。
自分の考えで行動した結果トラブルやミスが起きた場合でも、周りの意見を聞いて考え方を変えたり、修正したりすることも苦手です。
自分を変える柔軟さがないため、周囲の変化や成長に取り残されてしまい、組織やチームの成長も阻んでしまいます。
自分の意見を無理に押し通す
自分の意見を無理に押し通す点も、協調性がない人の特徴です。自分の意見に自信を持っており、他人の意見には耳を傾けずに自分の考えだけで行動します。
自分の意見の欠点や他者の意見の利点を考えようとせず、無理にでも押し通す傾向にあります。
チームの他のメンバーは「何を言っても無駄だ」と感じ、コミュニケーションを図るのを止めてしまうため、協調性がない人はチーム内で孤立してしまうでしょう。
個人プレーが多い
協調性がない人は個人プレーが多い点も特徴です。
個人でできる業務には限界があり、多くの人の視点が入ることで業務が進めやすくなることもあります。
協調性がない人は根本的に「自分の意見が正しい」と考えているため、周囲のサポートを必要としません。チームで動くときには、他者との意見のすり合わせが必要になります。
協調性がない人は意見のすり合わせを「面倒」「必要ない」と考えるため、個人プレーが多くなる傾向にあります。
従業員の協調性を高めるには?
企業が従業員の協調性を高めると、以下のようなメリットがあります。
- 業務がスムーズに進む
- 組織の雰囲気が良くなる
- 社員のモチベーションが上がる
- 会社へのエンゲージメントが高まる
これらのメリットが企業にもたらすのは、生産性の向上です。企業が従業員の協調性を高めるためには、以下の3つの方法があります。
- チームビルディング研修を実施する
- チームワークを高めるためのゲームを行う
- 協調性を人事評価に取り入れる
一つずつ詳しく解説します。
チームビルディング研修を実施する
従業員の協調性を高めるには、チームビルディング研修を実施するのが効果的です。
チームビルディング研修とは、ゲームやスポーツを通じて、チームで目標のために協力し合う体験ができる研修です。
屋内や屋外、合宿形式など、実施方法はさまざまで、自社に合った研修を選べます。オンライン形式で実施することも可能で、テレワーク中心の企業でも実施できます。
働き方や価値観が多様化している中、社員の協調性を高めることが難しくなったとの声も聞かれるため、チームビルディング研修を活用すると良いでしょう。
チームワークを高めるためのゲームを行う
チームワークを高めるためのゲームを行うことも、従業員の協調性を高める方法の一つです。
チームビルディング研修で行うゲームやスポーツもその一種ですが、他にも以下のようなゲームがあります。
|
ペーパータワー |
新聞紙やクラフト紙を使って、チームでタワーを作る |
|
ジェスチャーゲーム |
出されたお題をジェスチャーだけでチームに伝える |
|
しっぽ取りゲーム |
自分のしっぽ(ビニールテープなど)を取られないように相手のしっぽを取る |
簡単なゲームですが、勝つための戦略を立てたり、うまくいかないときに声を掛け合ったりなどのチームワークが求められます。
チームで動くときに必要な考え方や視点が分かり、協調性を高めることに役立つでしょう。
協調性を人事評価に取り入れる
従業員の協調性を高めるためには、協調性を人事評価に取り入れることも効果的です。
企業から従業員への「協調性を評価する」というメッセージになり、従業員に協調性の価値を認識してもらえます。
人事評価においては、評価項目や評価基準をあらかじめ従業員に明示することが重要です。
協調性の評価ではコンピテンシー(行動特性)評価を導入し、協調性がある従業員のどのような行動が成果につながったかを基に、評価項目を設定すると良いでしょう。
面接時に協調性を見抜く方法
採用面接で協調性を見抜けると、入社後に協調性を高める労力を減らせます。
また、協調性がある社員はチームで動くことが多い業務に配属できるなど、企業と従業員の双方にとってメリットがあります。
面接時に協調性を見抜く方法は、以下の3つです。
- グループ面接を取り入れる
- 過去のチーム体験についての質問をする
- 他者と意見が異なったときの対処法を質問する
一つずつ詳しく解説します。
グループ面接を取り入れる
グループ面接を取り入れると、協調性を見抜けます。
グループ面接には同じ場に他の応募者がおり、「採用されるためには他人より自分を良く見せなければいけない」と考える場面です。「自分の意見が優れているとアピールする」「話す内容や長さを周囲に合わせる」など、集団にいるときの態度や立ち振る舞いから、協調性を図ることができます。
協調性を見抜くうえでは、グループディスカッションも効果的です。決められた時間の中で自分をアピールしつつ、意見のすり合わせも行う必要があるため、協調性がある人を見抜きやすいといえます。
過去のチーム体験についての質問をする
面接時に協調性を見抜くには、過去のチーム体験についての質問をすると良いでしょう。
過去のチーム体験とは、学生時代の部活動やサークル活動、アルバイトなどが該当します。例えば、面接で以下の質問をしたとします。
学生時代の部活動で対立や課題があった場合、どのように対応してきましたか?
質問への回答によって「対立や課題があったときにどのように行動するのか」「周囲にどのような働きかけをしたのか」「チーム内でどのような役割を担っていたのか」などが明確になります。
うまくいかないときに周囲と協力して乗り越えた経験のある人は、協調性があると判断できるでしょう。
他者と意見が異なったときの対処法を質問する
他者と意見が異なったときの対処法を質問すると、協調性を見抜けます。
ビジネスシーンでは、他者と意見が異なることが頻繁に起こります。例えば、面接では以下のような質問をしてみましょう。
職場で対立したときは、どのように対応しますか?
応募者はこれまでの経験をもとに回答するため、「意見が違う場合にどのように乗り越えてきたか」「意見が対立したときに周囲と協力して対応できるか」を測ることができます。
入社後の困難な状況をイメージして回答してもらうことで、応募者が入社後に社内でどのように行動するかを具体的にイメージできるのも、協調性を測る上で効果的です。
協調性の必要性を知り、社員の協調性を高めよう
協調性とは「立場や意見が自分と異なる人たちと協力して、共通の目標を達成するために行動する力」です。
従業員の協調性が高まると、円滑なコミュニケーションによって風通しが良くなり、適切な役割分担ができて仕事が進みやすくなるなど、企業にとって多くのメリットがあります。企業として従業員の協調性を高める試みを行うことが重要です。
従業員が協調性を高められるよう、協調性の価値を認識する環境づくりや従業員への働きかけを行いましょう。


