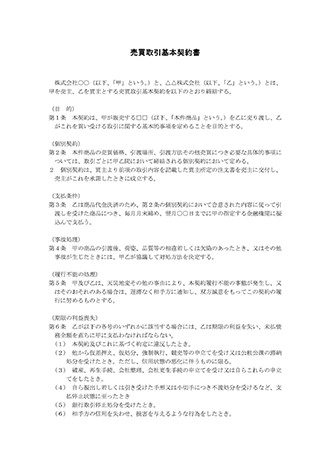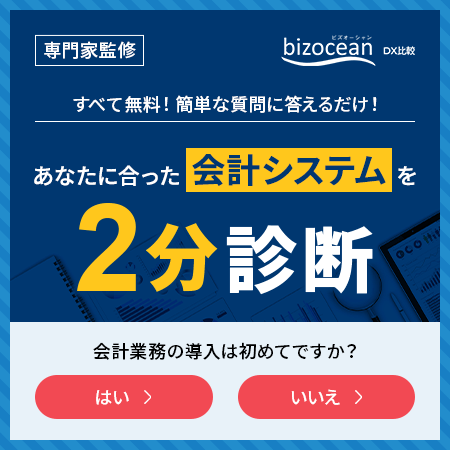[契約書の書き方] 第1回:取引基本契約書①
![[契約書の書き方] 第1回:取引基本契約書①](https://journal.bizocean.jp/assets_c/2021/11/_kigyo-houmu-photo04-thumb-660x426-1096.jpeg)
当事者間で反復継続して行われる商取引に共通して適用される事項を定めて締結したものを、総称して「取引基本契約書」と言います。
当事者間の合意内容を契約書として明文化しておくことで、将来の紛争を予防したり、紛争が生じたときに問題解決の根拠にしたりできます。
そのため、契約書作成時には、当事者間で合意しながらも、自社に不利益がないように、各条項を検討する必要があります。
本文では、具体的な例文を用いて、契約書に必要な記載事項を解説します。さらに、契約書発行にかかる印紙税をどうすべきかの判断基準についても言及します。

はじめに
本コラムでは、「契約書の書き方」と題して、主に企業間の取引で利用される種々の契約について、どのような条項を設ける必要があるか、また、どのような点に注意して各条項を規定すべきか等について、会社内で法務を専門にされていない方々にも役に立つよう、できる限りわかりやすく解説していきたいと思います。
第1回の今回は、商取引が反復継続して行われる場合に作成される取引基本契約書について、主に総論的な部分を解説していきます。
取引基本契約書とは何か
当事者間(主に会社間が想定されますが、双方又は一方が個人事業主の場合もあります。)で商取引が反復継続して行われる場合に、取引開始以前の段階で、当該取引に共通して適用される事項を定めておくために締結される契約を取引基本契約といいます。また、その契約内容を定めた書面を、取引基本契約書といいます。
ただし、契約書の表題が「取引基本契約書」とされていなくても、上記のとおり反復継続して行われる商取引に共通して適用される事項を定めたものであれば、例えば「売買契約書」という表題の契約書であっても、ここでいう取引基本契約書に当たります。
筆者が弁護士業務において相談を受ける顧客の中には、相手方企業との間で取引上の問題や疑問点が生じたとき、「うちの会社には取引基本契約がなく、受発注書だけでやっています。」とか、「なぜこの支払期日にお金を支払うことになっているのか分からない。」などとおっしゃる方が時々おられます。しかし、稀に、本当に取引基本契約書に相当するものが存在しない場合はあるものの、たいていの場合、その担当者が見たことがなかっただけで、会社のどこかに、相手方との間で交わした契約書(代金の支払条件等を規定した契約書)が存在するものです。場合によっては、今まで見たことがなかった、あるいは、日々のルーティンワークの中であまり意識していなかった取引基本契約書の条項を確認するだけで、ほとんど解決に至るような問題もあります。契約書は、当事者間の合意内容を明確にし、将来の紛争を予防するとともに、現実に紛争が生じたときに問題解決の拠り所となるものです。そのため、契約書作成にあたっては、当事者間で円滑な商取引を行うことができるよう配慮する一方、紛争発生時にできる限り自社に不利益が生じないよう、各条項を慎重に検討して規定する必要があるのです。
≫取引基本契約書(民法改正対応)
≫関連書式:民法改正対応済の売買契約書(無料)
契約書に貼付すべき収入印紙
筆者が顧客から質問を受ける事項で多いものの一つが、印紙税の金額です。取引基本契約書は、多くの場合、印紙税法の別表第1のうち第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」として、1通4,000円の印紙税がかかります。ただし、契約期間が3か月以内であり、かつ、更新の定めのないものは除かれます。
印紙税のかかる課税文書に当たるか否か、また、当たるとしてもどの課税文書に当たるかについては、契約書の形式的な表題によってではなく、内容によって決まります。いくらの収入印紙を貼るべきか疑義がある場合には、弁護士等の専門家に相談するか、国税局電話相談センターを利用するなどして判断することをおすすめします。
前文
ここからは、取引基本契約書の具体的内容について解説します(上記の「取引基本契約書(民法改正対応)」の書式と本コラムで紹介する規定例とは、必ずしも一致しませんので、ご了承ください)。本コラムでは、売主(甲)が買主(乙)に対し、甲が取り扱う製品を販売することを想定して、契約書の内容を検討していくこととします。このような取引基本契約書には、売主側(メーカー等)から買主側に対して提示されるものと、買主側(商社等)から売主側に対して提示されるものとがありますが、できる限り、いずれの立場からも想定される規定例を挙げて解説していきます。
まずは前文ですが、例えば次のように規定します。
株式会社○○(以下「甲」という。)と、△△株式会社(以下「乙」という。)とは、甲を売主、乙を買主として、甲乙間の継続的取引に関する基本事項について、以下のとおり契約を締結した。
ここで重要なことは、第一に、契約当事者を特定することです。第二に、比較的大規模な会社が当事者となる場合等においては、どの部署等が取り扱うどの製品が当該契約の対象となるのかを明確にしておくことです。上記の例では、第二の点は特に規定せず、単に「甲乙間の継続的取引」とし、対象商品は、後に説明する第1条で特定することを想定しています。
会社の誰が契約締結を行うか
契約当事者の特定という点に関しては、契約書の末尾に通常設けられる契約当事者欄に、会社の誰が記名押印するかという問題があります。
株式会社の場合、(代表)取締役に代表権がありますので(会社法349条、362条3項参照)、代表取締役名を記名し、代表者印を押印するのが原則です。
しかし、比較的大規模な会社の場合等では、商取引に関しては平取締役や事業部長などが記名押印することもあります。会社法上、事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人も、当該事項に関しては一切の裁判外の行為をする権限を持っており(会社法14条1項)、会社がその代理権に制限を加えても、その制限について善意(「善意」というのは、法律用語で「知らない」という意味です。)の第三者には対抗することができません(同条2項)。したがって、例えば、営業部長がその事業上の取引について契約を締結する場合には、仮にその事業について会社から売買契約締結の代理権を与えられていなかったとしても、会社法14条1項の使用人に該当し、上記売買契約について、会社は善意の相手方に対して責任を負うことになります(参考:最高裁平成2年2月22日判決・最高裁判所裁判集民事159号169頁)。
一方、課長や係長といった肩書きの場合も会社法14条1項の使用人に該当するかどうかは、ケースバイケースであると思われます。代表者以外の者との間で契約を締結する場合には、契約締結後に代理権の有無についてトラブルが生じることのないよう、契約締結段階において、記名押印欄の前に記載する後文に、次のように表記することも検討すべきと考えます。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲より本契約締結の権限を授与された下記の者及び乙代表者が記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
目的物の特定、契約の目的
第1条(目的)
甲は、乙に対し、□□(以下「商品」という。)を売り渡し、乙は、乙が製造し販売する××の部品とすることを目的として商品を買い受ける。
ここからは、取引基本契約書の具体的条項について検討していきます。
取引基本契約書では、まず対象となる商品(目的物)を特定することが重要です。これによって、当該契約の拘束力が及ぶ対象商品の範囲が決まることになります。対象商品が多岐にわたる場合には、別紙を作成し、「取引基本契約書第1条に定める商品は、以下に掲げるとおりとする。」などと記載して、対象商品を列挙することが考えられます。
また、上記の規定例では、乙が商品を自社が製造・販売する製品(××)の部品として買い受けることを契約の目的としています。契約の目的は、例えば、債務不履行による損害賠償請求が認められるか否かの判断の際、「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由」(民法415条1項ただし書)の存否を判断する重要な要素の一つとなります。令和2年4月1日より施行された改正民法では、415条1項において、履行不能とそれ以外の債務不履行を区別することなく、債務者に帰責事由がない場合には債務不履行に基づく損害賠償責任を負わないことを定めた上、同項ただし書において、「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」と、帰責事由の有無の判断枠組みが明確化されました(筒井健夫=村松秀樹編著『一問一答 民法(債権関係)改正』〔商事法務、2018〕74頁)。契約の目的は、上記の「契約その他の債務の発生原因」の重要な一要素と考えられますので、契約書に記載する場合には、後に疑義が生じないよう、明確に規定する必要があります。
次回からは、基本契約と個別契約の関係(第2条)と、それ以降の具体的条項について解説します。
≫取引基本契約書(民法改正対応)
≫関連書式:民法改正対応済の売買契約書(無料)
(第1回・以上)