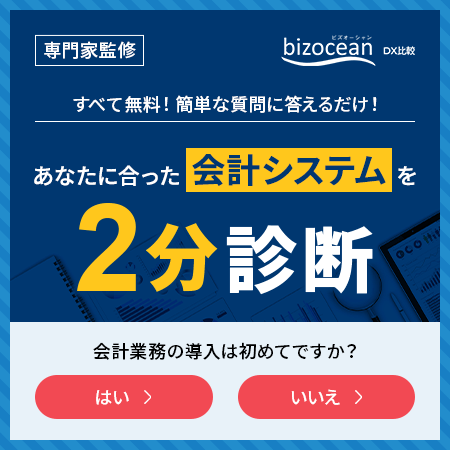法人格否認による役員に対する責任追及(1)
~法人格否認の法理についてわかりやすく解説します~


1 はじめに
スタートアップ企業などに代表される零細企業の経営者の中には、会社の法人格を活用して様々なメリットを享受している人も多いと思います。ただ、会社の法人格を活用することと濫用することはまったく別の話です。
たとえば、実態は経営者個人の債務に過ぎないのに、会社の法人格を隠れ蓑にして法的責任を回避するような行為は許されません。そのような場合、法人格否認の法理というルールによって、経営者個人に対して直接責任が追及されることがあります。
今回は、役員個人に対する責任追及方法としての法人格否認の法理の説明と、どのような場合に同法理によって経営者個人の責任が認められ、どのような効果が発生するのかについて説明します。
2 会社法人格の活用方法
経営者は、個人事業主としてではなく、法人である会社を活用することによって様々なメリットを享受することができます。簡単にまとめると概ね以下の4つを挙げることができます。
① 対内的・対外的法律関係の簡便化
会社に代表される法人には法人格が付与されています(会社法3条)。
そのため、法人は法人名義で法律行為を行うことが可能となります。法人内部の構成員ではなく法人自身が法律行為を行えるので、法人は対外的法律関係を簡便に処理することができます。また、対内的法律関係についても、構成員が多数に上る場合であっても法人格を有する法人自身が財産を所有することができるため、構成員全員の合意を取りつけるといった煩瑣な手続を回避することができます。
この点、同じ団体である組合には法人格がないため組合名義で法律行為を行うことはできません。また、組合は財産権を有することができないので、出資金その他の組合財産は組合の所有ではなく、組合員全員の共有に属することとなります(民法668条)。
さらに、組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員が執行することとなっています(同法670条1項)。
② 社会的信用の獲得
会社に代表される法人は、ヒト・モノ・カネを集めた団体に法人格を付与することで出来上がります。つまり、法人であるということは、個人事業主よりも相対的に人的・物的基盤が備わっていることを意味します。
また、会社の基本情報は登記によって公示されているので、当該会社と取引を行おうとする者は登記情報を確認することで取引をするか否かを決めることができます。法人の金融機関からの信用度も個人事業主と比べて相対的に高いといえるので、個人事業主よりも法人の方が融資を受けやすくなる可能性はあります。
③ 節税効果
法人を活用した節税スキームは様々存在します。たとえば、会社の利益を役員報酬として役員個人に支払うことで、給与所得控除額分の法人所得を減少させることができ、節税することができます。
また、個人事業主に対する所得税の税率は、累進課税となっていて最高45%ですが、法人税は最高約23%となっており、事業の利益が一定ラインを超えた場合は法人を活用したほうが税負担は少なくなります。
④ 経費圧縮効果
③と連動している部分もありますが、法人を活用することで様々な出費が経費として認められることとなります。
例えば、本人や家族に対して役員報酬を支払った場合、法人の人件費であるとして経費となります。そのほか、賃貸で借りている自宅を社宅であるとすれば、家賃相当額の半額程度を経費とすることができます。
3 法人格否認の法理とは
このように、法人と経営者が別人格であることを奇貨として、経営者は様々なメリットを享受することができます。しかし、零細企業、とりわけスタートアップ企業のような小規模閉鎖会社においては、実態として法人=経営者である企業も多く存在します。
そのような企業において、経営者が法人を私物化することで不当な利益を得たり、法の適用を免れようとしたりする事例が散見されます。これは見方を変えると、法人と経営者の法人格が形式的に独立していることを重視することで、かえってバランスを失する・衡平性を欠く解決となってしまうことを意味します。
そこで、当該事案に限って、法人と経営者などの関係者をあえて同一視して当事者の利害を調整するため、法人の法人格を否認するルールが存在します。それが、法人格否認の法理です。
同法理の適用が認められると会社の法人格が否認されるという劇的な効果を発生させるわけですから、あくまでその運用は例外的、かつ当該事案に限って行われることとなります。実務では、小規模閉鎖会社が倒産した際などに、その実質的オーナーである個人を責任追及するために活用されています。
法人格否認の法理が適用されるのは、最高裁判決によると、法人格が形骸化している場合(最判昭和44年2月27日・民集23巻2号511頁)と、法人格が法律の適用の回避や債務免脱等の目的で濫用されている場合(最判平成17年7月15日・民集59巻6号1742頁)の2つです。
以下、株式会社の事例を取り上げて説明します。
①形骸化事例
法人格の形骸化は、法人とは名ばかりであって、会社が実質的には経営者個人の営業と同一、または、子会社が親会社の営業の一部門に過ぎない状態をいいます。
例えば、株主総会・取締役会の不開催、株券の違法な不発行等、業務の混同、財産の混同といった、法人形式を無視するような要素が積み重なって初めて、法人格が形骸化しているとされます。
②濫用事例
法人格の濫用は、法人格が経営者により意のままに道具として支配されていること(支配の要件)に加え、会社の支配者に違法または不当の目的(目的の要件)がある場合をいいます。
例えば、倒産危機に瀕している会社が、強制執行を免脱するため、あるいは財産を隠匿するため新会社を設立する場合に、法人格が濫用されているとして2つの会社の法人格の異別性が否定され、倒産危機に瀕している会社の債権者に、新会社への支払請求を認めるとされます。
4 法人格否認の法理が認められた場合の効果
法人格否認の法理の適用が認められた(会社債権者が勝訴した)場合、実体法上の効果として、会社の金銭債務を株主や経営者といった者へ拡張(有限責任を排除)すること、株主・経営者・旧会社の金銭債務を新会社へ拡張(強制執行の免脱を防止)すること、会社倒産手続における株主や経営者の会社に対する債権が劣後的に取り扱われること、などが発生します。
一方、手続法上の効果として、会社債権者が取得した勝訴判決の既判力・執行力の範囲が、株主や経営者などへ拡張されるか否かについては見解の対立があります。
判例(最判昭和53年9月14日・判時906号88頁)は、訴訟手続・強制執行手続の明確・安定の確保を理由に、これを否定しています。
ただ、法人格が否認される実質的理由は様々なので、法人格を否認することが実体法上可能なケースであっても、訴訟法上も既判力・執行力等の拡張を認めてよいか否かについて、様々な状況が想起されます。
そのため、手続法上は法人格否認の法理の適用はあり得ない、と一律に解するのは適当ではないという見解も有力です(江頭憲治郎『株式会社法(第8版)』(有斐閣、2021年)48頁)。
5 おわりに
ここまで、法人格否認の法理の概要を説明してきました。
とりわけ小規模閉鎖会社においては、経営者などによって法人の法人格を活用してメリットを享受する状況が散見されるところではありますが、上述したとおり、条件が揃うと法人格否認の法理が適用され、直接経営者個人に対して責任追及がなされる可能性があるため注意が必要です。