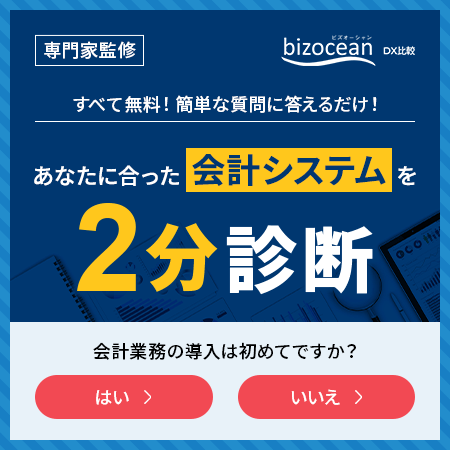解雇予告手当の雇用形態別の計算方法! 未払いの罰則や有給の扱いはどうなる?

突然の解雇から労働者の生活を守るため、労働基準法では「解雇予告手当」を設けています。
この記事では手当の概要や対象者、期限といった基本知識を得た上で、具体的な手当額を計算できるように、基本的な算出方法を詳細にご紹介します。しっかり理解し適切に対応することで、未払いによるペナルティのリスクを防ぎましょう。

労働基準法第20条に定められている「解雇予告手当」
従業員を解雇することは、その従業員の生活設計に大きな影響を与えます。その影響を少しでも減らすために「解雇予告手当」が設けられているのです。ここでは、解雇予告手当とはどのようなものなのかについて、ご紹介しましょう。
解雇予告手当とは
会社と雇用契約を結び働いているときに、突然何の予告もなく解雇されると、今後の生活がままならず困窮に陥ってしまいます。
そのようなリスクを回避するため、解雇する前の手続きとして用意されているのが「解雇予告義務」及び「解雇予告手当支払義務」であり、労働基準法第20条第1項本文で以下のように明確に定められています(以下では、当該規定の内容を「解雇予告制度」といいます。)。
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
つまり、
- 少なくとも解雇日より30日前には予告する
- 解雇予告をしない場合は、解雇と同時に30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う
という2点がポイントです。
ちなみに、解雇には、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇等がありますが、前述した解雇予告制度」は、原則として、いかなる解雇の場合であっても、適用があることに注意が必要です。
解雇予告手当の対象者
解雇予告手当を受け取れる対象者は、正規雇用されている労働者だけではありません。派遣社員や契約社員、パートタイマーやアルバイト等の非正規雇用とされる労働者も対象に含まれます。
解雇予告手当の支払が必要ないケース
解雇予告手当は労働者にとって重要な制度ですが、一方で適用除外、つまり会社が解雇予告手当を支払わなくてもよいとされるケースもあり、労働基準法第20条第1項ただし書きで、以下のように明記されています。
但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
この場合、使用者は解雇予告制度に関して所轄の労働基準監督署長による「除外認定」が受けなければならないとされています(労働基準法第20条第3項)。
また、後者の「労働者の責に帰すべき事由」に該当するケースついては、条文上明確ではありませんが、該当すると考えられるケースの例示として、
- 会社の商品を何点も窃取したことを理由に解雇された場合
- 同僚に対して侮辱的な暴言を吐き、暴行を加えて傷害を与えた場合
- 正当な理由がなく数週間無断欠勤し、出勤を督促しても応じない場合
- 賭博や風紀を乱す行為により、他の労働者や取引関係に悪影響を及ぼした場合
などが挙げられます。このように、解雇予告制度の適用が除外されることは、決してハードルが低くないといえるでしょう。
なお、上記の事由はあくまで解雇予告制度の除外認定に関するものであり、上記事由があったからといって必ずしも解雇が有効になるとは限りません。
さらに、労働基準法第21条では、以下のとおり解雇予告手当を支払う必要のない労働者を定めています。
ただし、括弧内に記載の場合には、解雇予告制度が適用されるので、留意が必要です。
- 試用期間中の者(試用期間が14日を超える場合)
- 4か月以内の季節労働者(4か月を超えて継続して使用される場合)
- 2か月以内の有期契約労働者(2か月を超えて継続して使用される場合)
- 日雇労働者(1か月を超えて継続して使用される場合)
解雇予告手当を支払うタイミング
会社は、労働者に対し、解雇予告手当をどのようなタイミングで支払うべきなのでしょうか。
法律上明確になっていませんが、即日解雇の場合は、解雇と同時に支払うべきとされています。また、解雇日から起算して30日前を切った段階で予告をした際にも、予告日数30日分に対して不足する日数分の解雇予告手当を支払う必要があります。この場合は、解雇の申し渡しと同時、又は遅くとも解雇日までの間に支払うべきとされます。
なお、実際の運用においては、最終の給与支払いと併せて支払う事例が多いようです。もっともこの場合には、解雇の効力発生日が争いになった際には、当該給与支払日が解雇日と見られる可能性がありますのでご注意ください。
基本的な解雇予告手当の計算方法と計算の流れ
解雇予告手当を支払う場合、基本的には以下のように計算します。
「平均賃金1日分」×「解雇日までの期間が30日に足りなかった日数」
万が一自分が解雇予告手当の支払を求める立場になった場合、どのようなステップを踏んで計算されているのかをあらかじめ理解しておくことはとても重要です。では次からそのステップごとに計算方法や計算の流れを解説していきましょう。
1. 平均賃金を計算する
まず、上記の計算式のうち、平均賃金を求める必要があります。1日の平均賃金は、以下の式で求められます。
「直前3か月の賃金の合計÷直前3か月の暦日数」
ただし、時給や日給といった給与制の場合は労働日数に配慮した「(直前3か月の賃金の合計÷直前3か月の労働日数)×0.6」という式と比較し、いずれか高い方とします。
「直前3か月」とは、解雇を予告した日からみて直前の給与締め日を起点とします。例えば、締め日が月末で、6月15日に解雇を通知された場合、起点は直前の締め日である5月31日になるため、3ヶ月間は3月1日から5月31日まで、となります。
1-1. 直前3か月分の暦日数を求める
次に、上記期間中の暦日数について考えます。
直前3ヶ月分の暦日数は3月の「31日」、4月の「30日」、5月の「31日」を合計して「92日」となります。
なお、労働基準法第12条第3項では、この暦日数に含まない日として以下の事項を定めています。
- 試用期間
- 産前産後休暇期間
- 育児介護休暇期間
- 業務上の怪我・疾病による療養休業期間
- 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
1-2. 直前3か月の賃金合計を求める
次に、直前3か月の賃金合計を考えていきます。賃金については発行された給与明細で確認ができます。なお、この賃金は手取り収入ではなく、社会保険料や所得税などが引かれる前の額面の金額なので注意しましょう。
また、賃金に含まれるもの、含まれないものも以下のようにあるため、正確に計算をしていきます。
<賃金として含むもの>
- 基本給
- 役職手当
- 残業手当
- 昇給が確定している場合には、その昇給額
- 皆勤手当
- 通勤手当 など
<賃金として含まれないもの>
- 3か月を超える期間で支払われる賃金(賞与等)
- 臨時で支払われる賃金(退職金、私傷病手当等)
- 労働協約等で定められていない現物給与 など
1-3. 平均賃金の計算式に当てはめる
ここまで要素をまとめたら、1−1と1−2で出てきた数値を使って、前述した以下の式により、1日の平均賃金を求められます。
「直前3か月の賃金の合計÷直前3か月の暦日数」
例えば、3月は「29万円」、4月は「28万円」、5月は「31万円」だったとすると、3ヶ月間の賃金合計は88万円。暦日数は92日間なので、88万円÷92日=9,565円です。なお、1円未満の端数の処理については、通常、四捨五入します。
2. 解雇日までの期間が30日に足りなかった日数を計算する
解雇予告が30日以上前に行われず、30日を切ってから通知された場合は、30日に足りない日数を計算します。それは以下の計算式で求められます。
「30-解雇までの日数」
たとえば、10日後に解雇をすると告げられた場合には、30-10=20日となります。
3. 解雇予告手当を計算する
では、本題の解雇予告手当について計算していきましょう。解雇予告手当は、
「平均賃金1日分」×「解雇日までの期間が30日に足りなかった日数」
で求められると説明しました。
そのため、この計算式に数値を当てはめると、
9,565(円)× 20(日)=191,300(円)
が、実際に支払われる解雇予告手当額です。
4. 最低保障額を下回っていないか確認する
実は、平均賃金の計算においては、労働者の権利や生活を守るための最低保障額が設けられています。最低保障額は、以下の計算によって求めることができ、前述の「1-3. 平均賃金の計算式に当てはめる」で出した1日の平均賃金、つまり「直前3ヶ月の賃金の合計÷直前3ヶ月の暦日数」と比較します。
<最低保障額の計算式>
(直前3か月分の賃金の合計額)÷(直前3か月間の労働日数)×0.6
※なお、月給の場合と、時給や日給の場合が併給されている場合には、月給の場合には暦日数を用いて計算し、時給等の場合には労働日数を用いて計算し、それぞれの額を合算した額が最低保障額となります(労働基準法第12条第1項第2号)
もし、「直前3か月の賃金の合計÷直前3か月の暦日数」で計算した金額が、最低保障額を下回っている場合は、最低保障額を平均賃金として解雇予告手当を算出する必要があります。
たとえば先の例で暦日数92日に対して実労働日数が85日だった場合は、
88万円÷ 85(日)×0.6=6,211(円)
が最低保障額(1日の平均賃金)です。
この場合は最低保障額よりも「直前3ヶ月の賃金の合計÷直前3ヶ月の暦日数」で算出した9,565円の方が上回っているため、9,565円を平均賃金として解雇予告手当を算出することになります。
雇用形態別の解雇予告手当の計算方法
ここまで、基本的な解雇予告手当の算出する方法を説明しました。ただし、雇用形態によって若干の違いがあるため、それぞれの注意すべきポイントについて解説しましょう。
パート・アルバイトの解雇予告手当
パートタイマーやアルバイトの場合も、基本的な解雇予告手当の計算方法は正規雇用の場合と同様です。ただし、毎日決まった時間働くというよりも、自分のライフスタイルや都合に合わせてスポットで勤務することも多い勤務形態のため、暦日数で平均賃金を求めると、解雇予告手当が少なくなる可能性があります。
そのため、パートタイマーやアルバイトの場合は、最低保障額を平均賃金として、解雇予告手当を算出しなければならないことが多くなるといえます。
契約社員の解雇予告手当
パートタイマーやアルバイトと同様に、契約社員も前述した算出方法で解雇予告手当を受け取ることができます。また、最低保障額についても同様の計算方法となります。
ただし、会社が解雇予告手当を支払う必要がないケースも存在することに注意が必要です。具体的には、「解雇予告手当が必要ないケース」でもご紹介しましたが、
- 4ヶ月以内の季節労働者
- 2ヶ月以内の有期契約労働者
の場合は、解雇予告手当を支払う必要がないとされます。ただし、前述のとおり契約期間を超えて雇用された場合は解雇予告制度の適用を受けます。
日雇労働者の解雇予告手当
同じく「解雇予告手当の支払が必要ないケース」で解説した通り、日雇労働者の場合、労働契約は基本的に1日単位のため、会社側は解雇予告手当を支払う必要がありません。
ただし、1ヶ月を超えて継続して雇用されている日雇労働者の場合は、例外となります。この場合は、労働者が生活を支える手段として賃金を受けとることを期待していると考えられることから、突然の解雇による困窮を防ぐために解雇予告手当の対象となるのです。なお、解雇予告手当の計算方法は前述と同様の方法で算出されます。
試用期間中の解雇予告手当
雇用されてから間もない試用期間中も、会社は解雇予告手当を支払う義務がありません。ただし、試用期間が14日を超える場合は、解雇予告制度の適用があります。なお、計算方法も前述と同様です。
解雇予告手当に関する4つの注意点
では最後に、会社側が自社の労働者に解雇予告手当を支払うにあたり、重要かつ注意すべきポイントについて4点解説しましょう。
解雇予告手当には所得税の源泉徴収が必要
解雇予告手当は退職したことに起因して支払われる「退職所得」と考えられるため、所得税の源泉徴収が必要になります。なお、従業員が、会社に対し、「退職所得の受給に関する申告書」を提出したかどうかで税額が変わります。
詳細は割愛しますが、申告書を提出した場合は、退職所得控除が適用された源泉徴収額(「(課税退職所得金額×所得税率-控除額)×102.1%」)となります。
一方、提出しなかった場合は、解雇予告手当の20.42%の税率で税額を計算できます。
解雇予告手当の未払いは罰則の対象となる
労働基準法第119条では、解雇予告手当の未払に関する罰則として、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が定められています。
企業イメージや取引先や顧客からの信用を失わないためにも、このようなリスクをしっかりと理解し、必要な場面では正確に計算の上、期限までに支払うことが重要です。
有給を消化しても解雇予告手当は発生する
突然解雇を言い渡された場合、解雇日までに、まだ年次有給休暇が残っている場合も十分考えられます。
そして、年次有給休暇と解雇予告手当は双方に影響を与えるものではありません。そのため、労働者は年次有給休暇を取得することが可能であり、この場合でも会社は解雇予告手当を通常どおり支払う必要があります。
ただし、解雇予告手当を30日分支払ったうえでの即日解雇の場合には、下記のとおり、年次有給休暇を取得することができないため、ご注意ください。
即日解雇の場合は有給消化や買い取りの必要はない
即日解雇をされた労働者から、会社に対し、未消化の年次有給休暇を取得したい、または買い取ってほしいと言われた場合はどう対応すれば良いでしょうか。
そもそも年次有給休暇は性質上、あくまで雇用期間中に取得できるものであるため、即日解雇がされた後は雇用期間とはいえず取得できません。
また、そもそも会社は有給休暇の買い取りに応じる義務はないため、この場合でも買い取りについても応じる必要はありません。