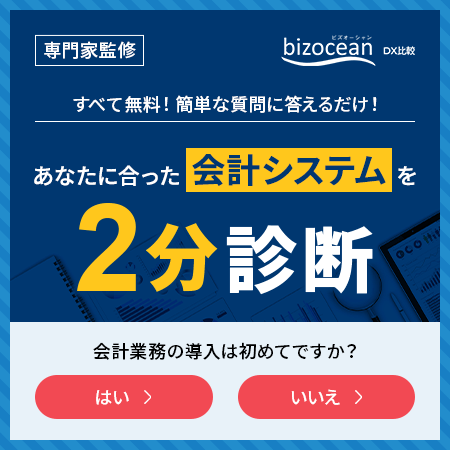Q&Aで学ぶ民法(債権法)改正 第7回「意思能力に関する規定の新設」


Q:高齢のAはアルツハイマー型認知症が進み、日常生活において正確な判断をすることができない状態になり、主治医から高度の認知機能の低下があるという診断を受けていました。Aは自宅で生活しています。そのAの日常生活上の財産管理については長女Bが行っていました。ところで、Aの長男Cには多額の借金があり、その返済期限が迫っていました。CはBが不在の時にA宅を訪れ、Aに100万円を贈与して欲しいと話しました。Aが頷いたので、用意してきた贈与契約書に判子をつかせ、金庫のお金を持ち去りました。法律上Aの保護は図られるでしょうか。
A:改正民法によって、意思能力を欠く者の保護規定が設けられましたので、設問Qでは、贈与契約を無効とすることでAを保護することができるでしょう。
1.改正のポイント
令和2(2020)年4月1日から債権法を改正する改正民法が施行されました。前回の「隔地者間における契約の成立時期の見直し」 に引き続き、本稿では、意思能力に関する規定の新設について取り上げます。
改正のポイントは
「意思能力を欠く者の保護規定を新設」するというものです。
2.改正点の解説
改正民法の意思能力を欠く者の保護制度の活用が考えられます。改正民法は、「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする」と規定します(民法3条の2)。このように、新たに意思能力を欠く者の保護規定が設けられています。
3.意思能力に関するこれまでの解釈は? 改正の理由は?
(1)意思能力・権利能力
契約を締結しようとする場合、法律上契約を締結できる者(権利主体)であるかどうかが問題となります。私法上権利を有し、義務を負うことのできる資格を「権利能力」といいますが、民法3条1項は「私権の享有は、出生に始まる」と規定し、人間(自然人)が権利主体となることを明確にしています(これに対し、例えば飼い犬等は人間によって所有される権利の客体にすぎません)。
しかし、権利能力があっても、その者が自ら売買契約を結ぶといった行為をすることができるか否かは別の問題です。例えば、生まれたばかりの赤ちゃんでも権利能力をもちますので、死亡した親の財産を相続することは認められますが、その財産を自ら処分する判断力をもつことは期待できません。そこで、意思能力という概念を考える必要があります。「意思能力」とは、一般に、自己の行為の意味やその結果について判断することのできる精神的な能力のことをいいます。例えば、3歳児のような極めて幼い幼児には意思能力がないといえ、7歳から10歳位で次第に獲得されてゆくものと考えられています。
もっとも、個人差もあり、法律行為の性質によっても異なります。したがって、だいたい10歳未満の子供や、これ以下の精神的な能力しかない精神障害者、泥酔者等には意思能力がないと考えられています。
意思能力のない者の行為の効力について、改正前民法では規定を置いていませんでした。しかし、民法は、個人は社会生活において、自己の意思に基づいて自由に契約を締結し、私的な法律関係を形成できるのであって、国家がこれに干渉するべきではないという私的自治の原則に基づいており、個人の意思を基本に法律関係が形成されることになっています。そのため、意思能力を有しない者の行為は無効になると判例・学説ともに認めてきました。こうした状況を受けて、これに関する明文の規定を置いたのが改正民法です。
(2)改正の理由
意思能力について規定を置いたのは、国民にわかりやすい法律にするためです。
この改正により、民法の規定は次のようになりました。
まず、自然人の法律上の能力は、出生により権利能力をもちます(民法3条)。自然人は意思能力(民法3条の2)を7歳~10歳位でもつこととなり、成年(満20歳。なお令和4(2022)年4月1日より満18歳)になれば行為能力(法律行為を単独で有効に行なうことのできる資格)を獲得する(民法4条以下)ことが明らかになります。したがって、意思能力のない者の行為は無効となり、また行為能力が備わっていない未成年者の行為については法定代理人の同意がなければ取り消すことができる(民法5条1項、2項)ので、これらの判断力が未発達な者については法律上の保護が与えられています。
4.設問Qの検討
設問QではAが頷いたとされています。しかし、贈与時点で認知症により、日常生活において正確な判断をすることはできない状態にあり、その旨の医師の診断書があったとされています。前述のとおり改正民法3条の2は、意思能力の有無の判断基準を、法律行為の当事者Aが「意思表示をした時」としています。そうであればAの贈与の意思表示時点では判断能力がないのですから、贈与を無効とすることができるでしょう。
この場合、誰が無効を主張することができるかが問題となります。一般に無効は誰からでも主張できるのが原則ですが、表意者を保護する趣旨の無効は、表意者の側からのみ主張できるものと考えられています。この点「表意者の側」の範囲については表意者Aのほか、どこまでが含まれるかは解釈に委ねられていますが、設問QではBがAの日常生活上の財産管理をしていたのですから、Aの財産保全のためにBが無効を主張することも認められるのではないでしょうか。
5.設問Qに関するその他の制度
高齢化社会の進展に伴い、判断能力が減退した高齢者の財産管理が問題となっています。設問Qのような場合も出てくるでしょう。その場合に、Aの財産の保護を図る方法はあるのでしょうか。まず考えられるのは、Aが成年後見開始の審判を受ける場合です。
Aのように精神上の障害により事理を弁識する能力を常に欠いた状態、つまり自分自身で自己の行為とその結果を合理的に判断する能力がまったくない精神状態の者については、本人、配偶者、4親等内の親族等一定の者からの申立てによって、家庭裁判所に、成年後見開始の審判を申し立てることができます(民法7条)。審判を受けた者は成年被後見人(精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者で家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者)とされます。成年被後見人には成年後見人が付けられ(民法8条、843条1項)、後見が開始されます(民法838条)。成年後見人は成年被後見人の財産を管理し、またその財産に関する法律行為を代理します(民法859条1項)。
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができます(民法9条)。仮に一時的に成年被後見人の意思能力が回復し、その間になされた行為であっても、画一的に代理人が取り消すことができるとして成年被後見人の保護を図っています。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、成年被後見人は単独で行うことができます。
設問Qで、Aが成年被後見人であった場合、成年後見人がBであれば、BがA=C間の贈与契約を取り消すことができます。
この申立てがなされていればAの保護を図ることができます。もっとも、判断能力の減退した高齢者のすべてにこの制度の利用を求めることは現実には難しいでしょう。そこで前記のとおり改正民法の意思能力を欠く者の保護制度が整備されたのです。
執筆の参考にしたサイト