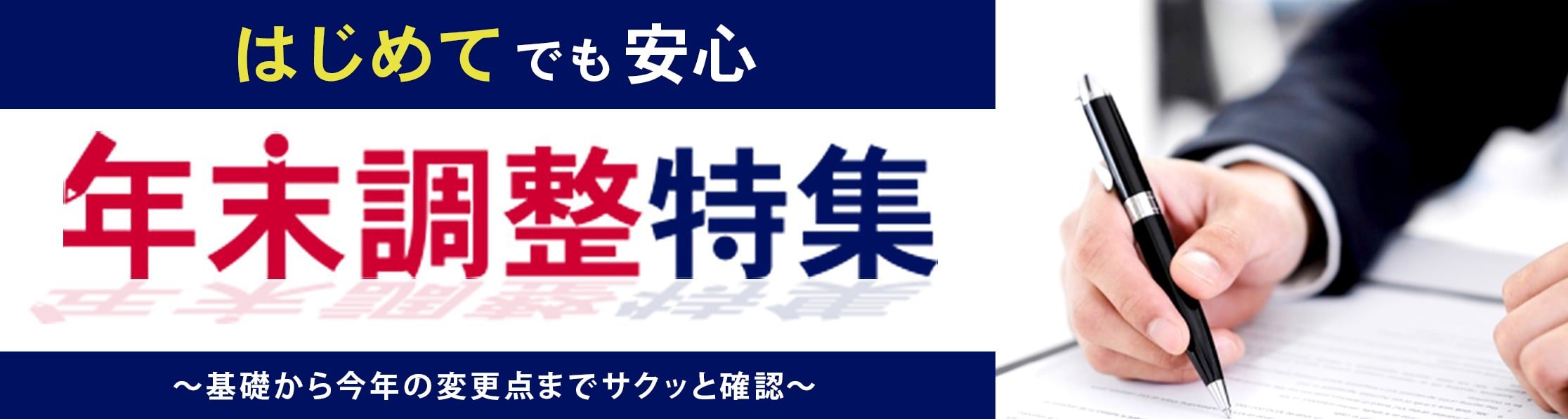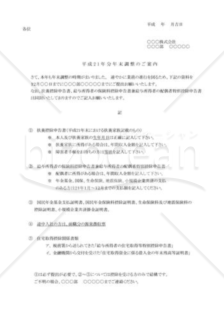分かりやすい年末調整の書き方、やり方

年末調整とは、従業員の年間の給与から徴収される所得税額を雇用主が計算し、源泉徴収した額との過不足を調整する手続きのことです。年末調整の書き方について解説します。
年末調整とは
税金を納税するにあたり、雇用主は従業員の年間給与から税金を計算して、所得税を天引きしています。しかし、天引きされた所得税額はほとんどの場合、本来納税すべき所得税額とは一致しないのです。なぜかというと、例えば年の途中で扶養家族に増減があったとしても遡って修正はされず、各種保険料の控除額も考慮されていないからです。そのため、年末に計算をし直し、精算しなければなりません。この調整のことを年末調整といいます。
年末調整の対象となる人
年末調整の対象となるのは、1年を通じて雇用されている人や、年の途中から雇用され年末まで勤務をしている人です。ただし、1年間に支払うべきことが確定し、その給与の総額が2,000万円を超える人、災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収について、徴収猶予や還付を受けた人は除かれるとされています。
年末調整の時期と期限
年末調整はその年に支払われる最後の給与、つまり12月の給与・賞与支給時に行われます。最終期限は1月31日ですが、これは訂正などが発生することが想定された期限ですので、11月末~12月初旬に、書類提出を呼びかける企業がほとんどです。
年末調整と確定申告の違い
年末調整は、雇用主が給与から税金を計算してくれ、必要書類さえ提出すれば年末調整をもって納税が完了します。しかし、企業に所属していない自営業やフリーランスの人は、自分で納税をしなければなりません。収入、経費、所得、税金の計算を自分でして、納税することを確定申告といいます。
源泉徴収と源泉徴収票
源泉徴収とは、雇用主が社員の給与から所得税を天引きして、国に払った金額のことをいいます。給与明細に記載されている『所得税』の欄に書かれているものが『源泉徴収』となります。ここに記載される金額はあくまでも概算となり、年末調整で精算されるまでの仮払額と考えると分かりやすいのではないでしょうか。そして年末調整後に渡される源泉徴収票とは、当該年の年収と、支払った所得税、公的年金、退職所得などが記載された書類のことをいいます。
年末調整で控除できる項目とは
年末調整で控除可能な項目は下記のとおりです。
給与所得控除
給与所得者が受けられる控除で、控除額は給与に応じて変化します。控除額は最低65万円とされています。
配偶者控除
所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられます。ただし、配偶者の所得が年間38万円未満である条件があります。
扶養控除
所得税法上の、控除対象扶養親族がいる場合に受けられます。
基礎控除
一定の要件に該当する場合に受けられます。
障害者控除
納税者自身または配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に受けられます。
寡婦(寡夫)控除
納税者が寡婦(寡夫)の場合に受けられます。
勤労学生控除
納税者が所得税法上の勤労学生である場合に受けられます。
配偶者特別控除
配偶者に38万円以上76万円未満の場合など、定められた要件を満たしているときに受けられます。
社会保険料控除
納税者自身または生計を一にする配偶者や、その他親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、または給与から控除される場合に受けられます。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金、および心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けられます。
生命保険料控除
一定の生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合に受けられます。
地震保険料控除
特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や、掛金を支払った場合に受けられます。
住宅借入金等特別控除
住宅ローン等を利用しマイホームを新築、増改築等(取得等)をし、一定の要件を満たす場合に受けられます。
年末調整のやり方
色々と複雑に感じる年末調整ですが、下記の手順で行います。
社員の所得控除の確認
1.所得控除
- ①扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認
- ②配偶者特別控除申告書の受理と内容の確認
- ③保険料控除申告書の受理と内容の確認
2.税額控除
- ④(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の受理と内容の確認
3.集計
- ⑤給与と徴収税額の集計
- ⑥給与所得控除後の給与等における金額の計算
- ⑦課税給与所得金額の計算
- ⑧年調年税額の計算
4.精算
- ⑨過不足額の精算
- ⑩過納付額の還付
- ⑪不足額の徴収、納付
年末調整の案内文の書き方
毎年10月以降を目処に年末調整用の書類が入手できるようになります。余裕を持って年末調整の手続きができるように、社員には早めに案内を出すと良いでしょう。提出漏れが出ないように、年末調整をするにあたって必要な書類をあらかじめ案内文に明記しておきます。人数が大きい企業ではシステム化され、PC上でデータ生成ができるようになっているところも多くあります。システム化されていなくても、チェックリスト形式の案内文であれば、社員は自分がどの書類が必要なのかが分かり便利です。
扶養控除等(異動)申告書の書き方
マイナンバーも配布され、平成28年分からは扶養控除等(異動)申告書の様式も一部変更となっています。書き方をパート別に見ていきましょう。
1.本人の情報
一番上に記載欄があるのが本人の情報欄です。下記情報を記載します。
- 氏名
- 生年月日
- 住所
- マイナンバー
- 勤務先名
- 家族構成
- 世帯主氏名/続柄
2.扶養親族の情報
扶養親族がいない場合は1.のみの記載で終了です。もし扶養している配偶者や親族がいれば、この欄を記載します。
- 【A欄】
-
- 扶養対象配偶者氏名
- 生年月日
- 住所
- 配偶者のマイナンバー
- 翌年の所得見積額(予測年収から給与所得控除額を引いた金額)
- 【B欄】
-
- 扶養親族氏名
- 生年月日
- 住所
- 扶養親族のマイナンバー
- 特定扶養親族であれば当該欄に○を記載(19歳~23歳未満)
- 同居老親族であれば当該欄に○を記載(70歳以上)
- 非居住者であれば当該欄に○を記載(日本国内に住所を有していない人)
- 翌年の所得見積額(予測年収から給与所得控除額を引いた金額)
- 【16歳未満の扶養親族の欄】
- 16歳未満の扶養親族は所得税の控除対象にはなりませんが、住民税に関係しますので必ず記載しましょう。
-
- 扶養親族氏名
- 生年月日
- 住所
- 扶養親族のマイナンバー
保険料控除申告書・配偶者特別控除申告書の書き方
毎年11月になると加入している保険会社から加入者へ『生命保険料控除証明書』が送られてきます。新制度、旧制度の2種類がありますので、どちらに該当するか証明書を確認しておきましょう。手元に申告書を用意して必要項目を転記します。
- 保険会社等の名称
- 保険等の種類
- 契約期間
- 契約者名
- 保険金等の受取人/続柄
- 新旧の区分
- 本年中に支払った保険料の金額
- 保険料の控除額
年末調整とマイナンバー
年末調整に必要な書類は4種類あります。マイナンバーが導入されてから、そのうちの3種類にマイナンバーの記載が必要になりました。扶養親族がいる場合は、申告者本人のマイナンバーだけでなく、扶養親族のマイナンバーも必要になります。マイナンバーは大切なものですから、管理には注意しましょう。
<年末調整に必要な書類>
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ⇒ マイナンバーの記載が必要
- 配偶者特別控除申告書 ⇒ マイナンバーの記載が必要
- 保険料控除申告書 ⇒ マイナンバーの記載が必要
- 住宅借入金等特別控除申告書 ⇒ マイナンバーの記載は不要
注意すべきこと
マイナンバー導入後の年末調整で気をつけたい注意点は4つあります。
1.本人確認について
従業員からマイナンバーを取得するには必ず本人確認が必要になります。運転免許証などと照らし合わせて確認をします。また扶養親族の本人確認は、扶養者の従業員が行うこととされています。
2.事業者と従業員の関係
マイナンバー関連の手続きを業者に委託する場合、事業者は委託先が適切にマイナンバーを取り扱っているか監督しなければなりません。同様に従業員が自身の扶養親族からマイナンバーを取得し記載することは、マイナンバー関連事務を事業者が従業員に委託したと考えられます。しかし、マイナンバー制度上、この場合の事業者と従業員の関係は委託にはならず、監督義務も生じないものとされています。そのため、マイナンバーが漏えいしたとしても、責任は事業者にあることにはなりません。
3.利用目的
マイナンバーを利用するには本人に利用目的を明示しなければなりません。明示した利用目的の範囲を超えないように対策をとる必要があります。年末調整の書類でも、配偶者特別控除申告書に必要なマイナンバーを『年末調整のために利用する』と明示していたら、それを従業員の承諾なく社会保険の手続きに利用することはできません。その場合は複数の利用目的をあらかじめ明示しておきましょう。
4.マイナンバーの管理
事業者には従業員のマイナンバーの適切な管理が義務づけられています。万一漏えいさせたり、紛失したり、欠損させてしまうと、特定情報保護委員会から指導や勧告を受けることがあります。適切なシステム作りをすると同時に、担当者への教育も必要になるでしょう。会社の信用にも関わることですから、コンプライアンスの観点からも管理を徹底する必要があります。
まとめ
毎年年末になると手続きをしなければならない年末調整。書類をそろえて記載しなければならず面倒に感じるのではないでしょうか。しかし、適切に納税をするために必要な手続きです。漏れや間違いがあると控除が受けられず損をしてしまうこともあります。スムーズに申告ができるよう、余裕を持って準備をしておきましょう。