「僭越ながら」の意味と適切な使い方は? シーン別の例文付きで徹底解説
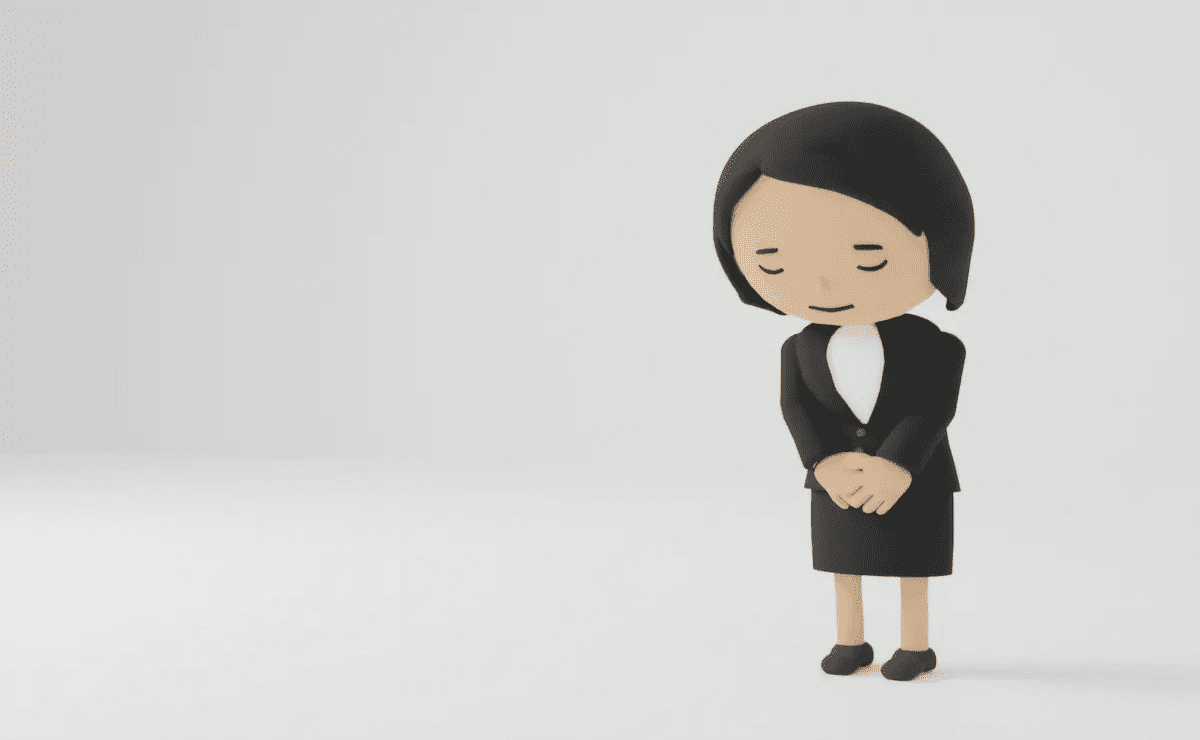
「僭越ながら」は、上司や先輩に意見を述べるときなどに使用されることが多い言葉です。
よく耳にするこの言葉ですが、使い方を誤ると相手に不快な印象を与えかねません。特に新入社員や若手社員の方は、正しい使い方を身につけることが重要です。
本記事では「僭越ながら」の意味や、ビジネスシーンでの正しい使い方を例文付きでわかりやすく解説します。また、知っておきたい他の言い換え表現も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
「僭越ながら」の意味
「僭越ながら」の「僭越(せんえつ)」とは、「自分の地位や身分、立場を超えて、出過ぎたことをする様」を意味します。少し崩した表現でいうと「出しゃばり」のことです。
「僭越ながら」の「ながら」は、「にも関わらず」、「けれども」などを意味する、逆接の接続詞になります。また、「そのまま」の意味も含みます。
つまり、「僭越ながら」は、「自分の身分や立場からすると、出しゃばったことではありますが」を意味する、フォーマルな用語です。
ビジネスで「僭越ながら」を使うシーンと例文
「僭越ながら」は、状況に応じて適切に前置きや、クッション言葉として用いることで、その後の対応や本題への導入をスムーズにさせます。
ビジネスで「僭越ながら」を使うシーンは様々あります。特に、新入社員や若手社員の人は使用する機会が多いでしょう。「僭越ながら」を活用することで、上司や先輩など目上の人と関わる状況で、丁寧で誠実な印象を与えることができます。
以下では、「僭越ながら」の使い方と例文を、シーン別に紹介するので、ぜひ参考にしてください。
上司の代役を務めるとき
「僭越ながら」という言葉は、上司が休暇や出張などで、会社や打ち合わせなどに不在の際、自分が代わりに対応する時に使うケースが多いです。
この場合は「本来対応すべき役職ではなく、部下である自分が代役を務めます」の意味で、「僭越ながら」を前置きで使うとよいでしょう。
例文
- 課長の佐藤が不在のため、僭越ながら本日は私が担当させていただきます。
- 誠に僭越ながら、課長の佐藤の代わりに本日は私が担当させていただきます。
- 僭越ではございますが、今回の会議の進行は私が代わりに務めさせていただきます。
上司の前で意見するとき
ビジネスシーンでは、新人でも上司や先輩など、目上の人に自分の意見を伝えないといけない場面は多々あります。丁寧さや謙虚さを表す「僭越ながら」をクッションにして、相手に失礼がないように意見を述べましょう。
例文
- 誠に僭越ながら、私はA案よりB案のほうがよいと考えます。
- 誠に僭越ではございますが、2点ほど質問させていただいてもよろしいでしょうか。
- 誠に僭越ながら、この予算案には賛成しかねます。
忘年会などで乾杯の音頭を取るとき
忘年会や新年会などの行事で、上司の代役として、急遽乾杯の音頭を任せられることもあるでしょう。その際には、焦らずに「僭越ながら」の言葉を用いて、下記の例文のように話すことがポイントです。
例文
- ただいまご紹介に預かりました佐藤です。僭越ながら、乾杯の音頭を取らせていただきます。
- ご指名賜りました営業課の佐藤でございます。誠に僭越ながら、代表してご挨拶させていただきます。
同僚の結婚式でスピーチをするとき
ビジネス以外でも、冠婚葬祭のような社交の場においては、フォーマルな対応は欠かせません。
同僚の結婚式でスピーチを任された時は、新郎新婦のご両親や会社の上司など、目上の人たちも多く出席している場合があります。その際は、丁寧で誠実な印象を与える意味で、「僭越ながら」を下記のように使用しましょう。
例文
- 新郎の山田君と同期の佐藤と申します。甚だ僭越ながら、友人代表のスピーチをさせていただきます。
- 誠に僭越ではございますが、新婦の友人を代表してお祝いの言葉を述べさせていただきます。
ビジネスメールを送るとき
「僭越ながら」は対面での話し言葉だけでなく、ビジネスメールでの書き言葉でも活用できます。取引先への確認やお断りの連絡など、少し言いづらい内容を相手に伝える際の前置きとして効果的です。
例文
- 僭越ながら、2点ほど確認させていただきたい件がございます。
- 誠に僭越ではございますが、今回のご依頼はお断りさせていただきます。
「僭越ながら」を使う際の注意点
「僭越ながら」は、身分や立場が上の人に対して使用する謙譲の表現です。部下や同僚に対しては使いません。目上の人や取引先など、謙遜すべき相手に対して使用しましょう。
ただし、便利な表現だからといって、多用すると、かえって失礼になる場合があるので、注意が必要です。
「僭越ながら」は、自分の身分や立場、状況、文脈に応じて使う必要があります。相手の行為に対して使ったり、間違った意味や文脈で使ったりすることは、「僭越ながら」の誤用になりかねません。
誤用によるトラブルを防ぐために、注意点を以下で解説します。
同僚や部下には使用しない
「僭越ながら」は上述のとおり、出過ぎた行為や、本来自分に不相応な大役を担う際に用いる、謙譲の表現です。
上司や先輩など、自分よりも目上の人に対して、へりくだって謙遜する時に使用します。そのため、同僚や部下に使用すると、本来の謙譲の意味から考えて違和感が生じてしまうので注意しましょう。
取引先や社外の人に対する際は、相手の役職に関わらず、へりくだった表現が求められる状況が多いです。その場合も、相手を目上の人として、謙遜の表現である「僭越ながら」を活用すると、嫌な印象を与えることなく対応を進めることができます。
多用すると失礼になる場合がある
「僭越ながら」は、自身の謙遜の姿勢や誠実さを伝えるのに便利な言葉ですが、多用するとむしろ失礼になる場合があります。
何度も「僭越ながら」を繰り返すと、相手に「へりくだりすぎ」や「媚びへつらっている」と捉えられ、ネガティブな印象を与えかねません。
「僭越ながら」は、前置きやクッションとして使いやすい表現ですが、相手に「しつこい」と思われないように、挨拶やメールでの使用は1回に留めておきましょう。
「お先に」の意味で使うのは誤用
「僭越ながら」と「お先に」を同じ文脈で使用することは誤りです。「僭越ながら」には「お先に」といった意味はありません。
「お先に」は、時間の前後や順序に関係して使用する言葉です。一方で、「僭越ながら」は、あくまで謙譲の表現であり、身分や立場の上下関係を基に使用するので、時間の前後や順序は関係ありません。
ランチを先に食べる際に、「僭越ながらいただきます」と言ったり、先に退勤する際に、「僭越ながら失礼します」と言ったりすることは誤用です。
これらの場合は、身分や立場ではなく順序に関係しているので、「お先に」を使用しましょう。
相手の行為に対しては使わない
「僭越ながら」は、基本的に自分自身がへりくだって謙遜する表現のため、相手の行為に対して使ってはいけません。誤った例と正しい例は以下になります。
誤った例文:僭越ながら、ご紹介にあずかりました佐藤と申します。
正しい例文:ただいまご紹介にあずかりました佐藤と申します。僭越ながら、代表のスピーチをさせていただきます。
前置きとして「僭越ながら」を使う際には、他者の言動ではなく、自分の行為の前に付けましょう。
僭越ながらの言い換え表現
「僭越ながら」は、目上の人に対して使う表現のため、誤用してしまわないか不安になることもあるでしょう。ですが、「僭越ながら」と同じ意味を持つ謙譲表現は多くあります。
「僭越ながら」の使用が適しているか心配になった時は、別の表現で柔軟に言い換えてみましょう。
以下では、「僭越ながら」の言い換え表現や類似表現を紹介します。状況によっては、別の言い換え表現を使用したほうが適切な場合もあるので、ぜひ参考にしてください。
恐縮ですが
「恐縮ですが(ではございますが)」は、相手に迷惑をかけた際や、相手から厚意をもらった場合に使う表現です。
「恐縮」には「身が縮む気持ち」や「申し訳ない思い」が意味に含まれているため、「僭越ながら」の言い換え表現として使用できます。申し訳なさのニュアンスを少し出したい場合は、「恐縮ですが」を使うのがよいでしょう。
例文:お忙しいところ恐縮ではございますが、企画書が完成しましたので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
お言葉ですが
「お言葉ですが」は、相手の言葉に対して、何か意見を述べる時に使用します。基本的に反対意見を述べる前の、クッションとして言い換えて使うことで、言いづらい内容を伝えやすくなります。
意見を求められた際は「僭越ながら」を、能動的に言いづらい意見を述べる際には「お言葉ですが」を、というように状況によって使い分けるとよいでしょう。
例文:お言葉ですが、A案はコストがかかりすぎるため、B案のほうがよいかと思います。
出過ぎたことですが
「出過ぎたことですが」は、「自分の身分に不相応で(立場を超えて)、過ぎたことをしますが」という意味合いの表現です。「出しゃばっている」という点で、「僭越ながら」の言い換えとして使えます。
目上の人に意見や忠告をする時や、自身が中心メンバーではない場で意見を述べる時などに使用します。
例文:出過ぎたことですが、この計画にいくつか懸念点があります。
身に余る大役ではありますが
「身に余る大役ではありますが」は、自分にとって大きなプロジェクトや仕事、重要な役職を任された際に使用します。
「こんな大役をもらえて嬉しい」という気持ちに、謙遜を交えた表現です。「ありがたい」、「光栄です」のニュアンスが含まれています。
目上の人から大きなことを任された際には、「僭越ながら」よりも「身に余る」を用いた表現のほうが適切です。
例文:身に余る大役ではありますが、誠心誠意頑張らせていただきます。
失礼を承知のうえで
「失礼を承知のうえで」は、「身の程をわきまえていないのは、理解していますが」という意味で、申し訳なさのニュアンスを含んだ表現です。
目上の人に意見する際に、前置きで使うと、自身から相手への配慮を感じさせることができます。特に注意や忠告などの意見を述べる際に用います。
上司の間違いやマナー違反などを指摘したい場合、そのまま伝えるのではなく、「失礼を承知のうえで」と言ってから本題を述べるとよいでしょう。
例文:失礼を承知のうえで申し上げますが、課長の営業先での態度は改めるべきかと思います。
微力ながら
「微力ながら」は、「自分の力は弱いですが」や「自分の能力では足りないかもしれませんが」というように、自分の実力を謙遜した表現です。
重要な仕事を引き受けた際や、大きな役割を任された際に使うと、「精一杯頑張る」という意思表示に繋がります。
例文:微力ながら、今までの経験を活かして精一杯努力いたします。
僭越ながらの意味を正しく理解し、ビジネスシーンで活用しよう
「僭越ながら」は、「自分の身分や立場からすると、出しゃばったことですが」を丁寧にした表現です。上司や先輩といった目上の人に対して、何か述べる際に、前置きやクッションとして使うことで、相手にへりくだった姿勢を感じさせつつ、スムーズに意見を伝えることができます。
一方で、「僭越ながら」は、謙遜を伝える便利な表現でありながら、多用すると失礼になる可能性があります。自身の行為に対して使うと、間違った表現になってしまうので、誤用には注意が必要です。
「僭越ながら」はもちろん、言い換え表現とその使い方まで理解し、相手や状況に合わせて適切に使用することで、目上の人からの印象もよくなるでしょう。


