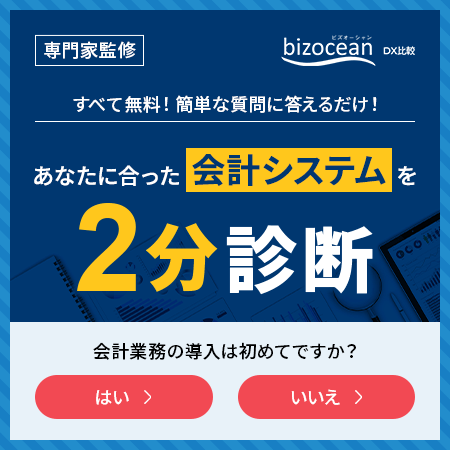懲戒解雇とは? 条件や退職金の扱い、処分の流れも解説
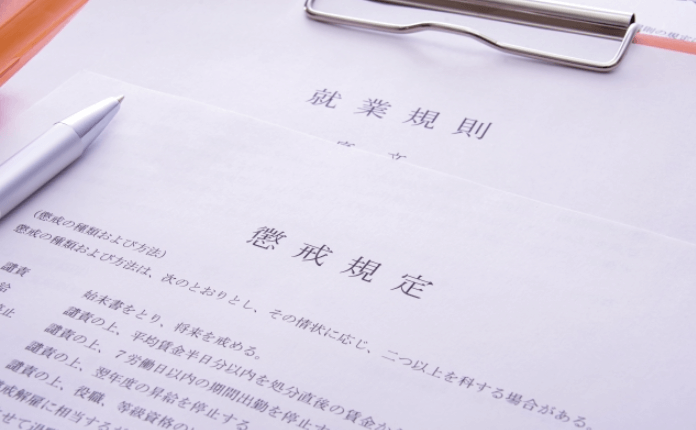
懲戒解雇は会社が従業員に対して行う処分の中で、もっとも重い処分です。そのため、懲戒権は、それが客観的に見て合理的であるかなどを慎重に判断してから行使せねばなりません。
本記事では、従業員の懲戒解雇を検討している経営者などに向けて、懲戒解雇の意味から、典型的な懲戒解雇例、懲戒解雇時の退職金の扱いなどまで詳しく解説します。

懲戒解雇とは
懲戒解雇とは懲戒処分のひとつであり、会社が従業員に課すペナルティの中でもっとも重い処分です。懲戒処分にはいくつかの種類があり、処分が軽いものから順に「戒告やけん責(譴責)・減給・出勤停止・降格・諭旨解雇」と続きます。
そして、もっとも重い処分にあたるのが「懲戒解雇」です。つまり、懲戒解雇は「極めて悪質な行為を犯した従業員に対して、最大の罰として行う解雇」です。
普通解雇を実施する場合には、会社側は少なくとも30日前までに解雇予告をしなくてはなりません。一方、懲戒解雇では、「その処分が有効であり、労働基準監督署長の認定を受けた場合」には、解雇予告なしに従業員を即時解雇できます。
なお、普通解雇は、何らかの理由でその従業員と雇用契約を維持することが困難になった場合に、認められるものです。例えば「勤務態度に問題があり、適切な指導・教育を行っても改善されない」などのケースです。
「懲戒解雇になる理由と普通退職との違い」については、下記記事も参照してください。
懲戒解雇となり得る典型的な事例
ここでは、懲戒解雇が適用される典型的事例を紹介します。
以下のような事例を参考に、自社の就業規則などで、「懲戒解雇事由」を定めておきましょう。
重要な業務命令の拒否
従業員が会社側の命令に従わずに反抗的な場合、企業秩序が乱れたり、組織運営に支障が生じたりするおそれがあります。そのため、企業側は従業員に対し、懲戒解雇も視野に入れて適切な処分を検討することになります。
例えば、転勤などの業務命令を、従業員側が正当な理由なく拒否した場合などが挙げられるでしょう。
ただし、企業側の権利濫用によって下された命令などではなく、「正当な根拠・必要に基づいて下された重要な命令」である限りで、懲戒解雇も有効となり得る点に注意しましょう。
懲戒処分の有効性の判断においては、当該の業務命令が「業務上必要な命令であったか・嫌がらせなど不当な目的で下されていないか」といった点が焦点になることがあります。
通常、「日常業務に関する業務命令拒否」では、懲戒解雇の対象にはなりません。
日常的な業務命令違反が繰り返されたとしても、それが企業秩序を乱すほどの行為になるとは考えにくいためです。
日常業務に対する業務命令違反については、まずは口頭や書面で指導や注意を行い、それでも改善されない場合に、懲戒処分として戒告やけん責などの軽めの処分で反省を求めるのが一般的です。
重大なハラスメント行為
重大なハラスメント行為も、懲戒解雇の対象となり得ます。
通常、セクハラ・パワハラなどの行為者は、一回で懲戒解雇となるものではありません。しかし、「強制わいせつ罪」「傷害罪」などの重大な刑事犯罪に該当するハラスメント行為を行った従業員は別です。これらは一回であっても、懲戒解雇が有効とされる傾向にあります。
行為自体が悪質であるほか、「注意や指導を受けたにもかかわらずハラスメント行為を繰り返す場合」も懲戒処分が検討されます。
2022年4月から、中小企業を含めたすべての事業主に対して、パワーハラスメントの防止措置が義務付けられました(通称、労働施策総合推進法第30条の2第1項)。
このように、各種ハラスメントに対する世間の目は、一層厳しくなっています。社内において重大なハラスメント行為が発覚した際には、自社イメージの失墜を防ぐためにも、懲戒解雇を含めた厳正な処分を検討する必要があるでしょう。
正当な理由がない長期間の無断欠勤
正当な理由なく、長期間の無断欠勤をした従業員も、懲戒解雇の対象となり得ます。懲戒解雇が有効になる可能性が高いのは、「企業側からの注意や出勤の督促に応じない場合」や「過去の勤務成績からみて情状酌量の余地がない場合」などです。
ただし、無断欠勤した従業員をすぐに懲戒解雇にできるわけではありません。「無断欠勤について、会社側がきちんと注意・指導している」、「それにもかかわらず、無断欠勤が続いている」という状況が存在することで、懲戒解雇も有効となり得ます。
例えば、過去には、2週間の無断欠勤でも懲戒解雇が有効と判断された裁判例がある一方で、1か月の無断欠勤でも「それまで企業側が特に注意しなかったこと」などが理由となり、解雇が無効となったケースもあります。
重大な経歴詐称
重大な経歴詐称も懲戒解雇になる典型例です。「その経歴詐称が事前にわかっていれば、採用しなかった、又は同一条件で契約しなかった」といった場合には、重大な経歴詐称として、懲戒解雇事由に該当する可能性が高いでしょう。
具体的には、2つの詐称パターンがあります。まず、学歴や職歴など、契約の決め手となった事項への経歴詐称です。次に、犯罪歴などを隠しているケースです。
ただし、「企業側が採用プロセスにおいて、当該の経歴項目を重視していなかった」場合や「労働者が単に面接時に質問がなく自発的に申告しなかった」場合などには、重大な経歴詐称とまではみなされないことが多いです。そのため、この場合、詐称を理由に懲戒解雇を行うことは難しいと考えられます。
犯罪や不正行為
業務外の犯罪も含めて、「会社に不利益を及ぼす犯罪行為」があった場合には、かなり高い確率で懲戒解雇が検討されることになるでしょう。
例えば、職場内での「横領行為」や「会社又は従業員の金品の窃盗行為」、「自らの地位や権限を利用しての利益相反行為」などが行われた場合です。
犯罪や不正行為などを理由に懲戒解雇を実行するためには、事実確認を入念に行う必要があります。
具体的には、本人や関係者などから聴き取りを行ったり、物的証拠を集めたりするなどして、まずは事実関係を詳細に把握します。そして、それらの事実を慎重に検証しつつ、懲戒解雇の正当性を判断します。
なお、従業員がプライベートで犯罪を起こした場合、当然に懲戒解雇事由に該当するわけではないが、「所属している会社の名誉や信用を失墜させた場合」には、懲戒解雇の対象となります。こうした際には、行為の性質や情状、当該従業員の会社における地位、会社の社会的評価に与える影響など、複数の事情を総合的に考慮しながら、懲戒解雇の有効性を判断します。
現代は、経営層ではない一般従業員の不祥事についても、SNSですぐに情報が拡散されてしまいます。犯罪内容が悪質かつ重大な場合、自社だけでなくステークホルダーも、大きな損失を被るおそれがあります。したがって、「犯罪・不正行為を行った従業員を速やかに処分する(した)こと」を社内外に示すことは、コンプライアンス上も重要です。
懲戒解雇が有効となる条件
懲戒権は「使用者の権利」と思いがちですが、企業は自社の従業員を自由に懲戒処分できるわけではありません。
処分を有効にするには、一定の条件を満たさなければならず、これらを無視して処分を下した場合には、司法の場で「権利を濫用した」とみなされ、処分が無効になるおそれもあります。
懲戒解雇を有効とするためには以下の条件を満たし、かつ「当該の懲戒処分について、手続き上の誤り・過失がないこと」などが不可欠です。
就業規則の規定を満たしているか
まず、あらかじめ就業規則や雇用契約書に「懲戒条項」を設け、懲戒解雇となる場合の要件を具体的に明文化している必要があります。また、就業規則の場合、その内容が全ての従業員に周知されていなければ効力を発揮しません。
その上で、「当該従業員の行為が、就業規則などで定められた懲戒解雇事由に該当するか」、「懲戒解雇処分は懲戒事由の内容及び程度等に照らして相当なものであるか(比例の原則)」、「過去の類似事案と比較しても妥当性・同等性があるか(平等取扱いの原則)」といった点を、慎重に判断することになります。
そのため、逆にいえば、懲戒事由に関しては就業規則などで懲戒解雇処分の事由として規定していなければ、横領などの重い罪であっても懲戒解雇を行うことはできないということです。この場合は、普通解雇の手順で進めていくことになります。
社会通念上相当であるか
次に、懲戒解雇は普通解雇とは異なり、「従業員への制裁」として行う解雇であるため、客観的にみて合理的であり、かつ社会通念上相当でなくてはなりません。合理性に欠ける判断による懲戒解雇は認められていません。
そのため、「就業規則の規定と照らし合わせて妥当である」など合理的理由が存在する場合であっても、「社会的に重すぎる処分となっていないか(相当な処分であるか)」が、懲戒解雇の有効性を左右します。
例えば、従業員が企業秩序を乱したとしても、「会社に実損がない場合」などは、社会通念上、懲戒解雇が相当とはいえないケースが多いです。
弁明の機会を与えているかどうか
懲戒処分の手続きが適正であったかも重要です。具体的には、「処分を下す前に、当該従業員に弁明の機会を与える必要」があります。
弁明の機会を与えずに処分した場合には、「企業側が適正な手続きを踏んでいない」とみなされ、懲戒解雇処分が無効となるおそれがあります。企業側の判断・手続きプロセスに問題があったとみなされれば、長期的で大規模なトラブルを招きかねません。
こうした事態を回避するためには、就業規則などで「懲戒処分は、懲戒委員会を経て下すこと」といった記載を行った上で、懲戒委員会を開催することで、処分の有効性を担保するなどの方法があります。
懲戒委員会では、当該従業員に対して弁明の機会を十分に与えることで、懲戒プロセスについての司法上の正当性を高めるのです。
懲戒解雇での退職金の扱いは?
従業員を懲戒解雇した場合、退職金を不支給又は減額することができるケースがあります。
例えば、「当該従業員が自社であげたこれまでの功績を、抹消するほどの悪質な行為であると認められる場合」には、退職金不支給又は減額の措置が可能です。
そもそも、退職金には「従業員の長年の労に報い、退職後の生活を保障する」という意義があり、懲戒解雇と退職金支給は別問題と考えられ、別個に判断することが必要です。
そのため、退職金の不支給又は減額の措置については、上記退職金の功労報酬的性格に鑑みて、「当該行為が、労働者のそれまでの功績を抹消・減殺するほどの著しく信義に反する行為がある」と判断されたときに、退職金の不支給又は減額がなされることになります。
退職金を不支給にするか、一部減額にするかは、当該行為の内容や性質、会社へ与えた影響やこれまでの労働者の実績などを考慮して判断することになります。
もっとも、実際に退職金を不支給にするためには、その旨を就業規則等で規定しておくことが必要です。規定が存在していなければ、懲戒解雇が適法であっても、退職金の不支給又は減額の措置を講じることができません。
以上のように、退職金不支給・減額措置の規定を設け、当該行為が労働者の功績を抹消するような悪質性の大きい行為の場合には、懲戒解雇による退職金の不支給又は減額措置を適法に行うことができます。
懲戒解雇処分の流れ
前述の通り、懲戒解雇処分の決定には「適正な手続き」が求められます。具体的には、以下の手順で進めていくことになります。
問題行為に対する調査と事実確認
まずは事実確認を行います。懲戒解雇の事由となる違反行為について、しっかりと調査し、「客観的に確認できる証拠」を収集しなくてはなりません。
この調査・事実確認が十分でないと、もし裁判で処分の有効性が争われた場合、企業側が不利になるおそれが大きくなります。
例えば、正当な理由がない長期間の無断欠勤が明々白々に行われていたとしても、それを理由に懲戒解雇を下すなら、「関係者に聴き取りをしたり、日々の指導記録を書面やデータで残したりしておく」といった証拠収集が不可欠です。
弁明機会の付与
次に、当該従業員の言い分を聴くために「弁明の機会」を与えます。弁明の機会としては、面談による事情聴取のほか、書面を提出させる方法もあります。冷静に話し合うことが難しいケースなどでも、書面によるやり取りを行うことで、処分プロセスが進展するでしょう。
面談の場合は、より実効性を高めるために、企業が弁護士に立ち合いを依頼するケースもあります。また、「言った・言わない」で揉めないために、音声や議事録を残しておくことが大切です。
就業規則などに記載されていなければ、懲戒委員会を開くことは必須ではありません。その場合であっても、面談時の音声の録音や書面でのやり取りなど、必ず記録に残る形で、本人に弁解の機会を与えてください。
懲戒解雇通知書の作成と交付
弁明の機会を設けた上で、懲戒解雇を決定した際には、懲戒解雇通知書を作成します。作成した懲戒解雇通知書を本人に交付し、懲戒解雇を伝えます。
決定した懲戒処分は、本人に「書面」で通知しておくことが重要です。また、本人から「通知書を受け取った証」として受領書などの書面にサインしてもらうべきです。なお、自宅待機を命じている場合など、出勤していない従業員に懲戒解雇を言い渡す場合は、自宅に通知書などを送付することになるでしょう。
※以下のリンクから、通知書のテンプレートを利用できます。
失業保険などの各種手続き
懲戒解雇後には、本人が失業保険を受給するための手続きを行います。
具体的には、「離職票を発行する」「源泉徴収票の交付」「社会保険からの脱退」といたった手続きを期間内に行う必要があります。会社が住民税の特別徴収を行っている場合には、特別徴収を止める手続きも行わなければなりません。
不当な懲戒解雇を行わないために
企業側の処分が重すぎた場合には、「懲戒権を濫用したもの」とみなされ、処分自体が無効となります。不当な懲戒解雇は、本人に大きな不利益を与えることはもちろん、企業側も甚大なデメリットを被ります。
例えば、企業イメージや社会的信頼が失墜したり、当該従業員への損害賠償を請求されたりするリスクがあるのです。
不当な懲戒解雇を行わないために、「就業規則などで懲戒処分について規定しておく」、「本人に弁解の機会を与える」、「適正な手続きを踏んで処分を決定する」といったポイントを必ず押さえましょう。また、国籍や性別、妊娠や出産、労基法違反を労基署に申告したことなどを理由に労働者を解雇してはいけません。懲戒解雇理由が、これら禁止事項に抵触していないか十二分に確認してください。
条件を満たせば、企業(使用者)は一定の範囲内で従業員への懲戒権を行使することが可能です。しかし、懲戒解雇は従業員にとって非常にダメージの大きい制裁であるため、その合理性や正当性がかなり厳格に判断されることを理解しておきましょう。
就業規則などに明記しておくほか、普段から従業員への教育を徹底し、「会社側がこれまでいかに必要な指導を十分に行ってきたか」を証拠として示せるようにしておくことも重要です。
まとめ
本記事では、懲戒解雇にできる可能性が高いケースや処分を有効とするための条件などについて解説してきましたが、懲戒解雇は最も重い処分であるため、厳正さが求められます。
懲戒解雇を有効とするには、就業規則などに明記するほか、日々の教育や指導も徹底しておくなど、会社側で前もってさまざまな準備をしておかなければなりません。仮に不当解雇と判断された場合には、逆に企業側に大きな損失を生じさせることにもなりかねません。
また、処分決定後にも、懲戒解雇通知書の作成や離職票の発行、税金関係など、さまざまな手続きがあります。手続き上の誤りや過失があると、後に当該社員とトラブルになるおそれがあります。
そのため、従業員を懲戒解雇する場合には、あらかじめ社内ルールや書類などの形式面をしっかりと整備し、実際に労働者を解雇する前に弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。
【書式のテンプレートをお探しなら】