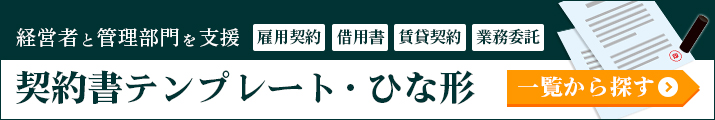失敗しない譲渡契約書の書き方│基本事項から注意点まで徹底解説【テンプレートあり】
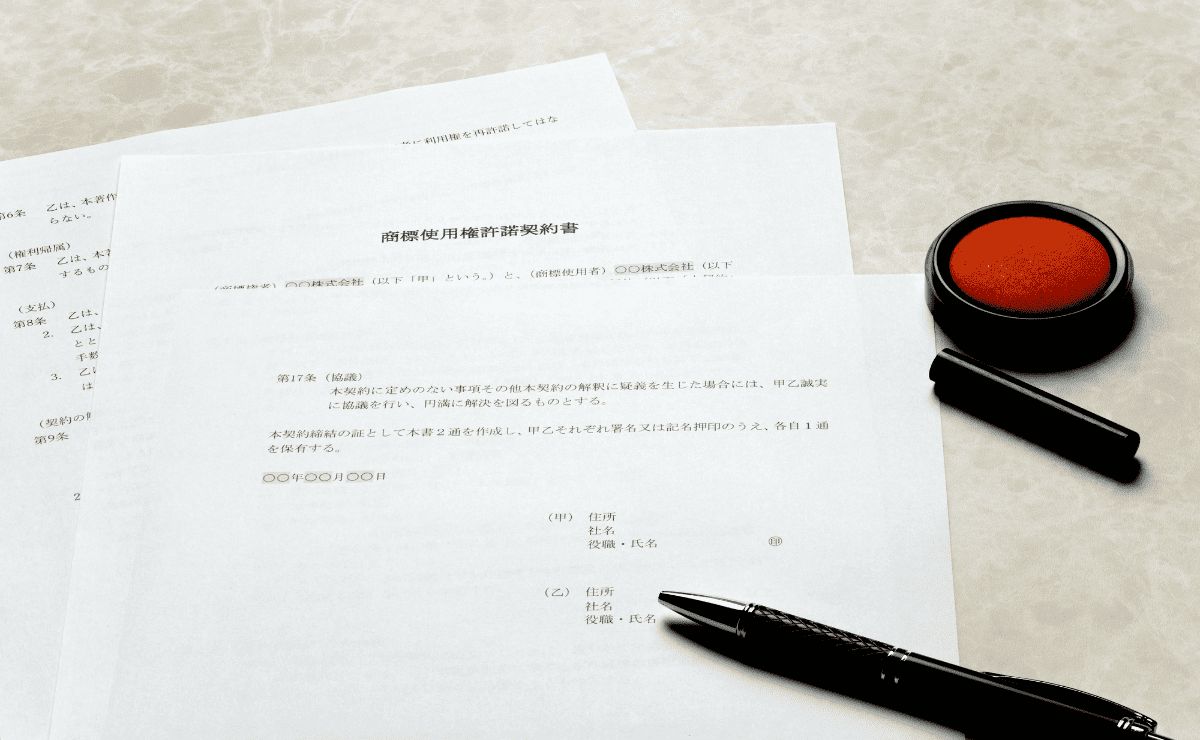
事業の譲渡は、経営者や従業員をはじめ、多くの関係者に大きな影響を与える重要な手続きです。だからこそ、事業譲渡契約書は、抜け漏れやミスがないように細心の注意を払って作成する必要があります。
しかし、実際に何を書けば良いのか、どの項目が必要なのかといった点で悩む方も多いでしょう。
本記事では、事業譲渡契約書の基本的な書き方から、作成時の重要な注意点まで分かりやすく解説します。すぐに使えるテンプレートもご用意したので、ぜひ参考にしてください。
事業譲渡契約書とは
事業譲渡契約書とは、事業を第三者に譲り渡す際に作成する契約書です。譲渡する権利・財産の範囲や対価など、譲渡にかかわる重要事項を漏れなく記載する必要があります。
事業譲渡と株式譲渡の違い
事業譲渡とは、企業が自社の事業すべて、または事業の一部を第三者に譲り渡すことです。事業を譲り渡すといっても、経営権は譲渡しません。
対して、株式譲渡とは、企業が所有する自社の株式すべて、または株式の一部を第三者に譲り渡すことです。所有している株式をすべて譲り渡した場合は、経営権も譲受者に移転します。
事業とともに経営権も譲り渡したい場合は、事業譲渡契約書とあわせて株式譲渡契約書も交わす必要があります。
無償譲渡と有償譲渡
無償譲渡とは、所有している資産を無償で移転させることです。法人が資産を無償で第三者に譲渡した場合は、『寄付』や『贈与』として取り扱われます。
一方、有償譲渡は、対価を得て資産を譲渡することです。対価が金銭の場合は売買、金銭以外の財産権である場合は『交換』になります。売買・贈与・交換のいずれも『譲渡契約』に含まれます。
事業譲渡契約書を作成する目的
原則として「契約」という行為は、当事者同士が合意していれば口頭でも成立します。
しかし、口約束だけでは、それぞれが考えていた契約内容に相違があったり、「言った、言わない」が発生したりして、大きなトラブルに発展することもあるものです。そのため、契約書を作成して、契約内容や対価などを明確にします。
とくに事業譲渡は、経営者はもちろん従業員や取引先など多くの人が影響を受けるものなので、譲渡する事業の範囲や対価などについてきっちり契約書に残し、トラブルが起こらないようにしておく必要があります。
事業譲渡契約書の書き方
事業譲渡契約書の内容は、契約内容に合わせて変更する必要があるため、決まった書式はありません。
ここでは事業譲渡契約書に記載する主な項目を紹介しますので、その内容を参考にしつつ、契約内容に合った事業譲渡契約書を作成しましょう。
契約者と譲渡日
譲渡側を「甲」、譲受側を「乙」として、事業譲渡を行う企業名を記載しましょう。また、事業の譲渡日と、状況によっては協議のうえ譲渡日を変更することも明記しておきます。
譲渡財産の範囲
譲渡する事業の内容や資産・債務などについて詳細に記載します。事業譲渡では譲渡する財産が多岐にわたるため、別途譲渡財産の目録を作成して、事業譲渡契約書に添付するのが一般的です。
公租公課の負担者
事業税・固定資産税といった各種税金や、雇用保険・社会保険といった保険料を、譲渡側と譲受側のどちらが負担するのかを記載します。
譲渡日前までは譲渡側が負担、譲渡日以降は譲受側が負担とし、譲渡当月の負担額は日割りで計算することが多いでしょう。どのような方法にするにしても、税金や保険料の計算方法とそれぞれの負担額について明記しておきましょう。
事業譲渡の対価
無償譲渡か有償譲渡か、有償の場合は支払金額や支払い方法、振込手数料の負担者などについて記載します。
従業員の雇用
事業譲渡後に従業員を解雇するのか、譲渡先で再雇用するのかを記載します。再雇用する場合は、未消化の有給や賞与、退職金などをどうするのかについても記載しておきましょう。
なお、譲渡先で従業員を再雇用する場合は、譲受側の企業と従業員とで新たに雇用契約を締結する必要があります。
必要書類の交付時期
譲渡契約書以外に、今回の譲渡で必要な書類がある場合は、書類を交付する時期について記載しましょう。通常は譲渡日に設定します。
譲渡財産の移転時期
譲渡財産を移転する日時・期限や、手続きにかかる費用の負担者などについて記載します。移転時期は譲渡日か、譲渡日から30日までとするのが一般的です。
譲渡日までの運営方法
譲渡する事業について、譲渡日までどう運営するかを記載しましょう。具体的には、譲渡日までこれまでと変わらず事業を運営すること、適切に財産を管理すること、事業の価値を落とすような行為をしないことなどを書いておきます。
取引先との契約
事業譲渡では、譲渡前の取引先との契約は承継されません。契約を引き継ぎたい場合は、事前に取引先から同意を得たうえで、承継する契約内容について記載しておきましょう。
表明保証
今回の譲渡契約が正当なものであることを証明するために、譲渡側・譲受側それぞれの表明保証について記載しましょう。
譲渡側は契約に必要な手続きをすべて終えていること、法や社内規定に則っていることなどを記載します。譲受側は譲渡日まで法律に則った事業運営を続けていること、契約に見合った権利や機能を備えていることなどを記載します。
表明保証は事業譲渡契約書の重要な項目であり、記載事項が多くなるため、別紙で目録を作成しても良いでしょう。
譲渡前後の遵守事項
事業譲渡によってお互いが不利益を被らないために、事業譲渡前と後で遵守すべき内容について記載します。
譲渡条件と解除
事業譲渡の条件と契約の解除条件について記載します。たとえば、表明保証が真実であること、契約書の内容をそれぞれが果たしていることなどを契約条件とし、守られない場合は契約解除となることを記載するのが基本です。
契約解除の方法や、譲渡完了後に契約解除はできないことなども記載しておきましょう。
協議事項
事業譲渡契約書に定められていない事項について問題が発生した場合、協議により解決することを記載しておきます。
法律と管轄
事業譲渡契約に適用される法律と、紛争が起きた場合の管轄の裁判所がどこになるのかを記載しておきます。
署名・捺印欄
譲渡側と譲受側それぞれの会社名と代表者の氏名、会社の所在地の記入欄と押印欄を用意しておきましょう。また、事業契約書を2通作成してそれぞれに記名押印し、譲渡側と譲受側が1通ずつ保管することも記載しておきます。
事業譲渡契約書の作成時に注意すべきこと
ここでは、事業譲渡契約書を作成するにあたって注意すべきポイントを紹介します。
印紙の有無を確認する
譲渡契約書は課税文書に該当するため、譲渡の対価に応じて収入印紙を貼り付けて消印する必要があります。
収入印紙を貼り忘れても契約内容に影響はありませんが、貼り忘れや消印の忘れがあると追徴課税が課せられることがあるので注意が必要です。
なお、譲渡の対価が1万円未満の場合は印紙税が非課税になるため、収入印紙を貼り付ける必要はありません。ただし、譲渡の対価について記載がない場合は200円の印紙税がかかるため、収入印紙を貼り忘れないようにしましょう。
自社で作成する
事業譲渡契約書は、譲渡側・譲受側のどちらが作成してもかまいません。しかし、譲渡契約での主導権を握るためにも、自社で作成するのが基本です。相手の原案を待ったほうが有利に進むのであれば、相手に任せても良いでしょう。
テンプレートを活用する
事業譲渡契約書を一から作成すると必要項目の見落としが出やすいので、テンプレートを活用するのがおすすめです。
ただし、テンプレートをそのまま利用すると契約内容に合わないことがあるため、契約内容に合わせて適宜内容を変更しましょう。
第三者のチェックを受ける
事業譲渡契約書に不備があったり、どちらか一方に有利すぎる内容だったりすると、契約締結後にトラブルが発生する可能性があります。
トラブルを防ぐためにも、完成した契約書を譲渡契約にくわしい第三者にチェックしてもらったほうが良いでしょう。
大切な項目を漏れなく盛り込む
事業譲渡契約書には、契約内容はもちろん、譲渡日や契約解約について、賠償責任やトラブルになったときの解決方法、対抗要件などを漏れなく盛り込むことが大切です。
不備があってトラブルが発生した場合、損害賠償を請求されたり事業が譲渡できなくなったりするリスクがあるため、すべての必要項目が記載されているかをよく確認しましょう。
まとめ
事業譲渡契約書は、事業譲渡を円滑に進めるための重要な書類です。事業譲渡契約書に抜け漏れやミスがあると、大きなトラブルが起こる可能性があるため、慎重に作成しましょう。
事業譲渡契約書を一から作成すると抜け漏れやミスが発生しやすいので、テンプレートを活用するのがおすすめです。また、完成後は譲渡契約にくわしい第三者のチェックを受け、記載内容に問題がないかを確認すると良いでしょう。
≫【解説図付き】割印の正しい位置とは?契印との違いも解説
≫譲渡契約書の書式テンプレート