オフィスワークとテレワークのいいとこどりをした「ハイブリッドワーク」に注目

オフィスワークとテレワークを組み合わせる働き方を「ハイブリッドワーク」といいますが、コロナ禍が終息に向かいつつある今、ハイブリッドワークに注目が集まっています。
そこで、今回の記事では、ハイブリッドワークの基礎知識やメリット、導入のポイント、促進に役立つツールなどについて解説したいと思います。
ハイブリッドワークの基礎知識
まずは、ハイブリッドワークに関する基礎知識についてみてみましょう。
ハイブリッドワークとは
一概にハイブリットワークといってもさまざまなスタイルがあります。
例えば、
- 従業員が自由にオフィスワークかテレワークか選択することができる。
- 週2でテレワークを実施する。
- 毎週月曜だけオフィスワーク固定で後は自由に選択できる。
これら全てがハイブリットワークにあたります。
また、ここでいうテレワークは在宅勤務に限定したものではなく、モバイル勤務やサテライトオフィス勤務、コワーキングスペースでの就業なども含まれます。
つまり、ハイブリットワークとは、従業員の事情に応じて、さまざまな選択肢の中から最適な働く場所を組み合わせるワークスタイルを指します。
ハイブリッドワークが注目を集める背景
ハイブリッドワークがどのようなものか分かったら、次はハイブリッドワークが注目を集めるようになった背景についてみてみましょう。
コロナ禍で表出したテレワークの課題
ハイブリットワークへの関心が高まった要因として、コロナ禍におけるテレワークの急速な拡大が挙げられます。
通勤負担の軽減、ライフワークバランスの実現、経費の削減など、テレワークにはさまざまなメリットがありますが、その一方で、いくつか深刻な課題も浮き彫りになりました。
コロナ禍で表出したテレワークの課題は下記の通り。
1.従業員間のコミュニケーション
テレワークの課題の1つ目は、従業員どうしのコミュニケーションです。
特にコロナ禍においては、準備が整わないままテレワークに踏み切り、そのまま長期化してしまったために、従業員どうしで直接会話する機会が極端に減り、コミュニケーションの希薄化が深刻になった企業も散見されました。
2.情報共有
テレワーク2つ目の課題は情報共有です。
必要な情報がどこにあるのか分からない、上手く検索出来ない、チャットのタイムラインを遡るのに手間がかかるなどの理由から情報共有が上手くいかず、業務の進捗を把握できなくなるといった問題が発生するようになりました。
3.生産性/業務効率の低下
従業員どうしでアイディアを出し合いたい、セキュリティの観点からオフィス以外でできる業務に制限がある、自宅に十分な通信環境が整備されていないなど、業務内容や従業員が抱える事情によりテレワークが向かない場合があります。
それにもかかわらず、コロナ禍で半ば強制的に全社一律のテレワークが実施されたことで、業務効率や生産性を低下させてしまう事例がいくつもありました。
ハイブリットワークのメリット
そこで、テレワークのよさを享受しながらも、課題を補う働き方として台頭したのがハイブリッドワークです。
ハイブリッドワークを導入することで得られる具体的なメリットは以下の5つです。
1.コミュニケーションの希薄化を解消
ハイブリッドワークを導入することで、対面でのコミュニケーションを維持することができるようになるため、チームワーク低下の防止や、従業員の不安感の払拭につながります。
また、自身の業務に集中しがちになるテレワークに対して、オフィスワークでは業務や部門を超えたコミュニケーションもできるため、新しい知見を得たりイノベーションが起こる可能性が高まります。
2.情報共有の円滑化
ハイブリッドワークの導入により、従業員どうしが対面で話す機会が増えるため、情報共有が活発化します。
3.生産性の向上
ハイブリッドワークを導入することで、従業員が自身の状況に応じて最適な環境で業務に取り組むことができるため、結果として生産性の向上につながります。
4.人材の確保
労働人口の減少が著しい日本の企業において、人材の確保は喫緊の課題であるといえます。
ハイブリッドワークを導入することで、従業員はテレワークを選択することができるようになるため、これまでやむを得ない事情で退職を余儀なくされてきた人材の離職防止につながります。
また、昨今需要の高いIT人材についても、テレワークを前提にしていることが多いため、ハイブリッドワークを導入することでIT人材の獲得も見込めるようになります。
5.オフィススペースの最適化
ハイブリッドワークを導入することで、出社する従業員の数が減り、オフィススペースに余剰が生まれます。
余ったスペースは、縮小してコストを削減をすることもできるし、逆にリフレッシュスペースを設置したりフリーアドレス制度を導入するなどして有効活用することもできます。
ハイブリッドワークを定着させるために必要なこととは
それでは、最後に、ハイブリッドワークを定着させるために押さえておきたいことをいくつかご紹介いたします。
導入の準備
定着させるためには、まずは導入しなくてはなりませんが、ハイブリッドワークを導入する際は、以下の2点を予め進めておくようにしましょう。
ルールの明確化
ハイブリッドワークをはじめるにあたり、まず必要になるのがルールです。
どこで就業するのかや、就業時間、出社日数に関連するルールについて明確化するようにしましょう。
また、テレワーク下では、オフィスワーク時と比較して、内部統制やガバナンスの強化が必要になるため、事前に業務マニュアルやセキュリティのガイドラインをまとめて、周知しておくといいでしょう。
業務のデジタル化
業務のデジタル化もまた、ハイブリッドワークの導入の際には欠かせない施策となります。
通常のテレワークでもそうですが、業務の電子化が進んでいないと、書類の作成や承認、検索、情報共有などのために不要な出社をしなければならなくなります。
グループウェアやチャットツール、web会議システムなど、さまざまなITツールやシステムを利用して、オフィス以外の場所でも円滑に業務が行えるようにしておきましょう。
ハイブリッドワークの定着に役立つITツール
前述にあるように、業務のデジタル化はハイブリッドワークの導入の際に不可欠なものになりますが、これは定着させる上でも同様です。
そこで、ハイブリットワークを定着させる上で、最も効果的なITソリューションとしてワークフローシステムを紹介させていただきます。
ワークフローシステムとは、稟議をはじめとした業務手続を電子化するシステムです。導入することで、ハイブリッドワークの定着に役立つさまざまな効果を享受することができます。
ワークフローシステムがハイブリッドワークの定着に効果的な理由
それでは、ワークフローシステムがハイブリッドワークの定着に効果的な理由をみてみましょう
ペーパーレス化の促進
ワークフローシステムにより電子化できる業務手続き(申請・承認・決裁)は、業種や部門を問わずあらゆる業務に紐づくため、ワークフローシステムを導入することで、社内文書のペーパーレス化を組織全体で促進することができます。
そのため、紙や対面が必要なアナログ業務のためだけの不要な出社も大幅に減らすことができます。
また、前述にあるように、業種や部門を問わず利用できるため、全社的なハイブリッドワークの実施にも役立ちます。
システム連携でDXを最適化
ワークフローシステムは、グループウェアや経費精算システム、勤怠管理システム、電子契約システムなどさまざまなシステムと連携して活用することが可能です。
そのことにより組織全体の業務効率化やシームレスなデータ連携が可能になり、企業のDXを最適化することができるため、テレワーク下においても効率や生産性を低下させずに業務を行うことができます。
まとめ
オフィスワークとテレワークのいいとこどりをしたハイブリッドワークは、企業・従業員の双方にさまざまなメリットをもたらします。
コロナ禍を経て、上手く行かなかった経験からテレワークをやめ再びオフィスワークに一本化する企業も増えていますが、アフターコロナの時代に対応するためにも、ハイブリッドワークという新しい働き方の可能性を模索してみるのもいいかもしれません。
【書式のテンプレートをお探しなら】

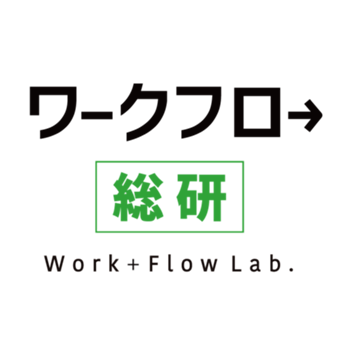 ワークフロー総研
ワークフロー総研
