第三者割当増資とは? 手続きの流れやメリット・デメリットなどを徹底解説
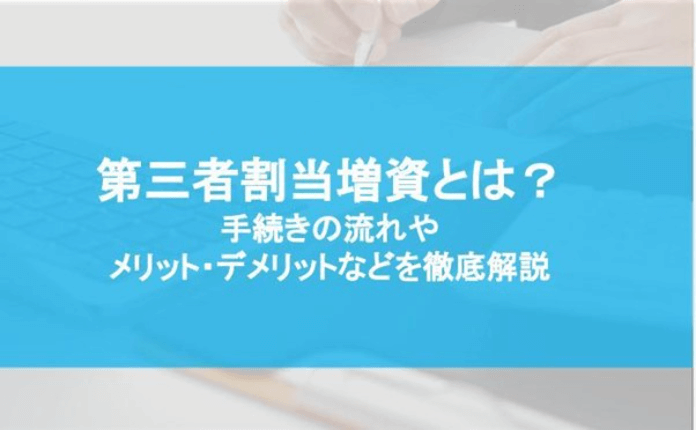
第三者割当増資は、企業が実施できる増資手法の一つです。
特定の第三者に、新たに発行する自社株式を有償で引き受けてもらうことで、事業の拡大や新規設備投資などに必要な資金を調達することができます。
既存株主に新株を割り当てる株主割当や、広く新株の引き受け先を募る公募増資とは異なり、特定の第三者に新株を引き受けてもらうのが第三者割当増資です。
財務の健全化や新株の引き受け先との関係強化を目的に行われ、M&Aに活用されるケースも多い第三者割当増資について、詳しく解説します。

第三者割当増資とは
企業が資金調達を行う方法の一つとして、第三者割当増資があります。
まずは、財務健全化に有効とされる第三者割当増資の概要と、株式譲渡や公募増資との違いを確認しましょう。
第三者割当増資の概要
第三者割当増資とは、新株発行増資の手法の一つで、特定の第三者に対して有償で新株を発行する増資です。
既存の株主に平等に新株を発行する方法ではないため、会社持株構成が変わり、株主ごとが持つ会社経営に対する影響力も変動が生じます。
第三者割当増資には、以下のような特徴があります。
- 発行会社と友好的な取引であり、経営に影響を及ぼさないことが前提である
- 発行会社の100%の議決権を取得することが目的ではないこと
- 発行会社が現金を直接調達することができ、発行会社にキャッシュインが発生する
逆に、会社持株構成に変動が生じ、会社経営に対する影響力にも変動が生じることに着目して、M&Aに近い効果を出すことでも活用されています。
株式譲渡や公募増資との違い
第三者割当増資と同じ有償増資の手法として、他に株式譲渡や公募増資があります。
これらの手法と第三者割当増資との違いは、以下の通りです。
- 株式の引受先の違い
- 株主構成は既存株主が残った状態の構成となる
- 新株を発行して発行会社に資金を入れることになる
株式譲渡は、現状株主に対してその保有株主割合に応じて、新株を割り当てる形式になります。
株主の保有株式割合が継続するので、支配割合に影響が出ず、経営は安定します。
その一方で、株主においては、資金に余裕がある方や資金に余裕がない方など状況は様々です。
新たな設備投資等によって事業を拡大・革新したい場合は、公募増資によって投資資金に余裕があったり、投資意欲が高い株主を誘導することができ、賛同できる株主を確保することができます。
これにより、株式保有割合に変動が生じ、経営権が異動することが想定できます。
第三者割当増資の目的
第三者割当増資の目的は、大きく以下の通りです。
- 新たに大規模な設備投資等を行うにあたり、賛同される方の出資を受け入れるため
- 会社間のアライアンスを結ぶ目的で、株式の所有を通して安定株主対策を実施するため
- 第三者に大量の株式を割り当てることによって、過半数または2/3以上の発行済株式保有による経営権譲渡といったM&Aと同一の効果を狙うため
第三者割当増資では、既存株主ではない特定の第三者に新株の購入権利を付与します。
そのため、既存の株主以外からも出資を募ることができ、より広く大きな資金を集めることが可能となります。
ただし、これには経営権の異動も伴うため、慎重に行う必要がある半面、M&Aの一方法として見られる可能性もあります。
また、近年で聞くことが増えた敵対的買収にも効果を発揮するため、安定株主工作の一環と見られる場合も多いです。
第三者割当増資のメリット
第三者割当増資を実施することで、どのようなメリットが得られるのでしょうか。
以下に、第三者割当増資によるおもなメリットを紹介します。
1.直接資金を投入でき、財務基盤を強固にできる
増資資金は現預金で入金され、かつ返金の必要がない資金であるため、現預金の残高が増加し、会社としても財務の安全性が高まる結果となります。
例えば、投資計画に基づいた設備投資を行う場合でも、借入金などを実行して銀行から資金を融通してもらうことなく、需要にも応えることが可能です。
ただし、事業の多角化や規模の拡大が可能となる半面、増資資金の出資者は法的に発言力を持つことになる点には注意が必要でしょう。
2.自己資本比率(純資産比率)が高まる
第三者割当増資を実施すると、現預金が増える一方で、純資産(資本金等)が増えるため、自己資本比率を高められます。
自己資本比率が高い会社は、より安全な会社であると判断されることが多いです。
仮に設備投資などの資金需要がない場合には、借入金等の他人資本を返済することによって、より安全性を高めることもできます。
3.100%買収よりもリスク回避できる
M&Aを実施する場合、株式譲渡で全て譲り受けるのが一般的ですが、経営陣が変更することにより、様々なトラブルが表面化することが多いです。
それを回避するため、第三者割当増資により現状株主が少数株主で残ることで、引継ぎを滞りなく進めることができる効果があります。
場合によっては、従来の役員も一定期間残ることによって、同様の成果を期待する場合もあります。
第三者割当増資を使った場合、税金が課されるケースが限定されるため、安心して進められるという点もメリットです。
4.スピーディーな事業承継が期待できる
M&Aに第三者割当増資を使うことにより、対象は経営を継続することができ、「切れ間」が発生しない(わからない)ことが特徴です。
出資関係には変更があっても、役員はその時点で変更する必要がないため、時間的に余裕があります。
営業に許認可関係が必要であったとしても、M&Aのタイミングで名義等を変更する必要がなく、徐々に進めることができるため、大きなトラブルの発生を避けられるでしょう。
第三者割当増資のデメリット
第三者割当増資ではさまざまなメリットが得られる反面、デメリットもあります。
以下に、第三者割当増資の主なデメリットを紹介します。
1.既存株主の利益を害する
まず、第三者割当増資により発行済株式総数が増えるため、特定の第三者以外の既存の株主が持つ持株比率は低下します。
それにより、当該会社に対する既存株主の影響力が下がることは問題でしょう。
また、第三者割当増資を行う場合、その時点での一株あたりの純資産額によっては、その価値が上下します。
一株あたりの発行価額を適正に計算しないと、贈与税や法人税が課税される場合がある点にも、注意が必要です。
2.100%議決権を獲得できない
第三者割当増資を使ってM&Aを行った場合、既存株主は少数株主として会社に残ってしまいます。
買主は100%の議決権を獲得するために、当該株式を売買や消却等の手法によって消す必要があります。
また、この際には既存株主に対して税金が課せられるケースが多く見受けられる点も、デメリットといえるでしょう。
第三者割当増資の手続きの流れ
実際に第三者割当増資を実施する際には、どのような手続きが必要となるのでしょうか。
以下に、第三者割当増資の手続きの流れを解説します。
1.取締役会による募集事項の決定
第三者割当増資を実施する際には、最初に取締役会で募集事項を決めるパターンが多いです。
有利発行を実施する場合には、既存株主が損をしてしまうので、既存株主保護を目的として、株主総会の特別決議を要求することになります。
2.株主に対する通知又は公告
取締役会で決定した募集事項は、払込期日の2週間前(あるいは払込期間の初日)までに株主に対して通知、あるいは公告する必要があります。
通知・告知が求められる募集事項は、以下の通りです。
- 募集株式の数
- 募集株式の払込金額、またはその算定方法
- 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨ならびに当該財産の内容および価額
- 募集株式と引換えにする金銭の払込み、または上記の財産(金銭以外の財産)の給付の期日、またはその期間
- 増加する資本金および資本準備金に関する事項
3.引受けの申込みをしようとする者に対する通知
募集する株式の引受け申込みを希望している者には、以下を通知しなければなりません。
- 株式会社の商号
- 募集事項
- 金銭の払込みをすべき場合は、取扱いの場所
- 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
4.引受けの申込み
募集株式の引受けを申し込む人は、以下の内容を記載した書面を交付しなければなりません。
- 申込みをする者の氏名または名称および住所
- 引き受けようとする募集株式の数
5.割当先の決定・申込者に対する通知
割当株式の割当先を決めて、割当募集株式の株式数を決定し、通知します。取締役会設置会社の場合は、取締役会決議で決定することが可能です。
6.株式の発行、登記変更
最後に、募集株式の引受け人は払込日あるいは払込期間内に、募集株式のすべての払込金額を、会社が定めた銀行などの金融機関の払込取扱場所へ払い込みます。
これにより出資の履行は完了です。
第三者割当増資の注意点
第三者割当増資を実施する際には、注意すべき点がいくつかあります。
以下に、第三者割当増資の代表的な注意点を3つまとめました。
1.積極的な情報開示が必要になる
自社の株式引き受けを求める際には、積極的な情報開示が欠かせません。
上場会社ならいざ知らず、中小企業の場合、会社の内容はよく知られていないケースもよくあります。
そこで、会社の内容をよく理解したうえで、安心して第三者割当増資の引き受けを行ってもらうためにも、情報公開は重要でしょう。
2.発行できる株式の確認が必須
株式会社には、定款で発行できる株式の総数が定められており、それを超過して株式を発行することはできません。
第三者割当増資を実施する際には、この発行可能株式の上限を確認することが必須です。
会社定款に記載された、会社が発行することのできる株式の総数を授権資本といい、 会社の設立に当たっては、授権資本のうち、実際に4分の1以上を発行すればよいとされています。
よって、この差額が会社が発行できる株式数ということになります。
3.変更登記の期限を過ぎるとペナルティが発生する
第三者割当増資を行う際には、期限内に適切に変更登記を実施するよう、注意が必要です。
会社はその登記内容に変更が発生した場合、登記の事由が発生した時から2週間以内に変更登記をしなければなりません(会社法第915条第1項)。
この変更登記を実施することなく2週間の期日を過ぎてしまった場合、登記懈怠(けたい)に該当し、過料(かりょう)として100万円以下の制裁金の支払いが科される可能性があります。
第三者割当増資のまとめ
第三者割当増資は、企業による資金調達法の一つで、新規に発行する株式を特定の第三者に有償で引き受けてもらう方法です。
同じ新株発行増資でも、その対象が特定の第三者である点において、株主割当や公募増資と異なります。
また、株式数の増加により、株主構成の変化を伴う第三者割当増資は、企業の財務を強化する目的のほか、M&Aの手法の一つとしても活用されています。
第三者割当増資にはメリットだけでなくデメリットもあるほか、手続き上の注意点も存在します。
第三者割当増資を正しく理解したうえで、その実施を慎重に検討しましょう。
【書式のテンプレートをお探しなら】


